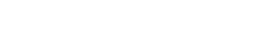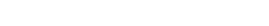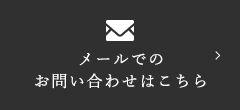2024/04/17 コラム
前科がつくとどのようなデメリットがあるのか?前科がつかないようにするためには?

前科は一度ついてしまうと生涯にわたって影響を及ぼし、就職や人間関係など様々な場面で障壁となる可能性があります。多くの人が「時間が経てば消える」と誤解していますが、実際には前科の記録は基本的に永続的なものです。本記事では、前科がもたらす7つの具体的なデメリットと、前科をつけないための効果的な3つの方法、そして前科に関する誤解と真実について詳しく解説します。
前科とは?

刑事裁判にて有罪判決を言い渡されたときにつきます。懲役の他にも、禁錮・罰金などの刑がありますが、どの刑罰であっても前科となります。前科と似た言葉に、前歴があります。
前歴とは、警察や検察などの捜査機関によって、犯罪の疑いをかけられて捜査の対象とされた事実をいいます。前歴は罪を犯したことを指すものではありませんので、前科とは扱いが異なります。
また、一度ついてしまった前科は消すことができません。
前科がつくタイミングについては、下記のコラムをご参照ください。
前科がつく7つのデメリット

前科がつくことは、人生の様々な側面に長期的かつ深刻な影響を及ぼします。「前科」は単なる記録以上の意味を持ち、社会生活における多くの制約や困難を生み出す要因となります。法的な処罰が終わった後も、前科の影響は続き、就職や人間関係、海外渡航など多岐にわたる場面で障壁となることがあります。ここでは、前科がもたらす7つの主要なデメリットについて詳しく解説します。これらのデメリットを理解することで、前科を回避することの重要性がより明確になるでしょう。
①会社を解雇される可能性がある
会社によっては、前科がつくことが「解雇事由」として記載されています。
特に信用や誠実さが求められる金融機関や公的機関では、厳格に適用されるケースが多いでしょう。また、会社の名誉や評判を下げることになりかねませんし、他の職員との関係で職場の環境が悪化することも考えられます。たとえ解雇にならなくても、昇進の機会が制限されたり、重要なプロジェクトから外されたりするなど、キャリアに大きな影響を及ぼす可能性があります。
②就業できない仕事がある
弁護士や国家資格を必要とする職業には、前科の存在は欠格事由となります。
法律で明確に定められており、例外はほとんどありません。また、教員や保育士、警備員、タクシー運転手など公共性の高い職業や子どもに関わる仕事、セキュリティに関わる仕事にも就くことができないケースが多いです。前科の内容によっては、欠格期間が一定期間に限定される場合もありますが、選択できる職業の幅が大きく狭まることは避けられません。
③就職活動で申告を求められる
履歴書において前科の記載が求められたり、前科の有無が聞かれたりする可能性があります。
特に大企業や公的機関では、採用過程で身辺調査が行われることもあります。法律上、前科について真実を話す義務はありませんが、虚偽の事実を申告して採用された場合、後にそれが発覚すると、信頼関係の破綻を理由に解雇される危険性があります。また、職種によっては定期的な身元調査が行われるため、長期的に隠し通すことは難しいかもしれません。
④警察や検察に記録が残る
前科などの記録は警察・検察に残されています。
この記録は一般の人々がアクセスできるものではありませんが、捜査機関は常に参照することができます。そのため、再犯をした場合、前科がない人に比べて重い刑罰が科せられる傾向があります。また、別の案件で捜査対象になった際にも、過去の前科が考慮され、より厳しい取り調べや処分を受ける可能性があります。司法制度において「前科」は常に影響力を持ち続けるのです。
⑤離婚事由になる可能性がある
前科がつくことは、家族関係にも深刻な影響を与える可能性があります。日本の民法では、「婚姻を継続し難い重大な事由」が離婚原因の一つとなっており、配偶者が犯罪行為によって前科を持つことは、この「重大な事由」に該当すると判断されるケースがあります。
特に暴力や詐欺などの反社会的行為による前科の場合、信頼関係が大きく損なわれ、離婚訴訟で不利な立場に立たされることがあります。また、前科により収入が減少したり就職が困難になったりすると、経済的な理由から家庭内の緊張が高まり、離婚に発展するケースも少なくありません。家族の信頼を取り戻すためには、誠実な反省と行動改善の努力が必要となります。
⑥前科がインターネット上に残る可能性がある
現代社会では、一度インターネット上に情報が出回ると、完全に削除することが困難になります。特に社会的関心が高い事件や犯罪の場合、ニュースサイトやSNSで報道され、検索すれば容易に情報が見つかる状態が続くことがあります。
このようなデジタルタトゥーは、就職活動や社会生活において大きな障壁となる可能性があります。名前で検索した際に犯罪歴が表示されると、新たな人間関係の構築や社会復帰の妨げになることも考えられます。また、報道内容が必ずしも正確でない場合もあり、事実と異なる情報が拡散されるリスクもあります。インターネット上の情報削除は技術的・法的に複雑で、専門家の助けが必要になることが多いでしょう。
⑦海外旅行で入国が許可されない可能性がある
前科を持つ方が直面する国際的な制約として、海外渡航の制限があります。多くの国では、入国審査時に犯罪歴の申告を求められ、前科の内容によっては入国を拒否される場合があります。特にアメリカ、カナダ、オーストラリアなどの国々は入国審査が厳格で、薬物関連犯罪や暴力犯罪などの前科がある場合、ビザの取得が困難になったり、入国を拒否されたりする可能性が高くなります。
また、前科の内容によっては特別なビザ申請や追加書類の提出が必要になることもあります。海外旅行や留学、国際的なビジネスを考えている方にとって、この制限は大きなデメリットとなり、キャリアや人生の選択肢を狭める要因になり得ます。
前科がつくのを回避する3つの方法

警察から接触があったり逮捕のリスクがある場合、迅速かつ適切な対応が前科回避の鍵となります。初期段階での適切な行動が、その後の人生を大きく左右する可能性があります。前科がつくと様々な制約が生じるため、できる限り早い段階で専門家のサポートを受けることが重要です。本章では、前科回避のための効果的な3つの方法について詳しく解説します。
①すぐに対応する
前科回避の第一歩は、問題が発生したらすぐに行動することです。警察から連絡があった場合や逮捕されそうな状況になった場合、初期対応が非常に重要となります。捜査の初期段階で適切に対応することで、逮捕を回避できる可能性があります。
また、すでに逮捕された場合でも、早期に対応することで勾留期間を短縮したり、起訴されるリスクを低減させたりすることができます。初期段階では証拠が少ないケースも多く、この時点での迅速な対応が、その後の展開を大きく左右します。問題を先送りにせず、真摯に向き合うことが前科を回避する第一の方法です。
②弁護士に相談し被害者との示談を行う
前科を回避するための重要な手段として、被害者との示談があります。示談とは、被害者と話し合いを行い、謝罪や損害賠償などの条件に合意することで和解する方法です。適切な示談が成立すると、被害者が処罰感情を緩和し、被害届の取り下げや宥恕状(ゆうじょじょう:犯罪被害者が加害者を許す意思を示す文書)の作成に応じてくれる可能性があります。これにより、不起訴処分の可能性が高まります。
しかし、示談交渉は法的な知識や交渉技術が必要となるため、弁護士のサポートを受けることが重要です。弁護士は適切な賠償額の提示や示談書の作成、交渉の進め方などについて専門的なアドバイスを提供し、成功率を高めることができます。被害者の気持ちに配慮しながら誠意を持って対応することが、示談成立の鍵となります。
③再犯しないようにしっかり反省する
前科を回避するためには、真摯な反省の姿勢を示すことが重要です。反省文の作成や謝罪の手紙、社会奉仕活動への参加など、具体的な行動で反省の意を示すことで、検察や裁判所からの評価が変わる可能性があります。特に初犯の場合、再犯防止に向けた明確な計画や環境改善の取り組みを示すことで、起訴猶予や執行猶予などの処分を受けられる可能性が高まります。
また、家族や雇用主からの監督誓約書や身元引受人の確保なども、再犯防止の意思を示す重要な要素となります。反省とは単なる言葉ではなく、具体的な行動と将来に向けた変化の決意を含むものであり、それが法的な判断にも影響を与えることを理解しておきましょう。
前科に関するよくある質問
前科に関しては様々な疑問や誤解があります。ここでは、多くの方が気になる質問について正確な情報をお伝えします。前科の時効や選挙権への影響、さらにはローンや住宅購入などの金融取引への影響など、知っておくべき重要な情報を解説します。
時間が経てば前科は消える?
多くの方が「時間が経てば前科は消えるのではないか」と考えていますが、残念ながらこれは誤解です。一度ついた前科は基本的に生涯消えることはありません。犯罪歴は法務省の犯罪経歴データベースに永続的に記録され続けます。
ただし、「前科の公表期間」という概念があり、一定期間が経過すると、前科の事実が一般に公開されにくくなります。例えば、刑の執行終了から10年が経過すると、犯罪者リハビリテーションの観点から、前科の情報が制限されるケースもあります。しかし、これは前科自体が消えたわけではなく、あくまで情報の取り扱いが変わるだけです。警察や検察などの捜査機関は引き続きアクセスでき、再犯時には考慮されます。
前科があると選挙権を失う?
前科があると選挙権を失うかどうかは、刑罰の内容と服役状況によって異なります。日本の公職選挙法では、禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わっていない人は選挙権を有しないとされています。
つまり、懲役や禁錮の刑で服役中の人は選挙権を一時的に失いますが、刑の執行が終了すれば選挙権は回復します。罰金刑のみの場合は、選挙権に影響はありません。ただし、選挙違反などの特定の犯罪で有罪となった場合は、刑の執行後も一定期間選挙権が停止されることがあります。また、公務員への就職や一部の公的な資格取得については、前科の内容によって永続的な制限を受ける可能性があるため注意が必要です。
前科は金融機関からの借り入れやローンに影響する?
前科があると、金融機関からの借り入れやローンの審査に影響する可能性があります。住宅ローンやカーローン、クレジットカードの申請時には、多くの金融機関が個人の信用情報を確認します。前科自体は信用情報機関のデータベースには直接記録されませんが、前科により就労状況や収入が不安定になると、間接的に審査に影響することがあります。
また、保険の加入審査においても、犯罪歴が問われるケースがあります。特に生命保険や医療保険の契約時に、告知義務として犯罪歴の申告を求められることがあり、虚偽の申告をすると保険金の不払いなどのリスクが生じます。ただし、軽微な罪の場合や十分な時間が経過している場合は、影響が軽減されることもあります。
前科がつく心配がある方は須賀法律事務所へ

前科がつくと、就職や結婚、海外渡航など、人生の様々な場面で影響を受ける可能性があります。一度ついた前科は基本的に消えることはないため、前科がつかないようにすることが最も重要です。警察からの接触があった時点や、逮捕されそうな状況になった時点で、すぐに行動を起こすことが前科回避の第一歩となります。
須賀法律事務所では、前科がつくリスクがある方々を支援するための様々なサービスを提供しています。経験豊富な弁護士が、あなたの状況に合わせた最適な法的アドバイスを提供し、前科回避に向けた具体的な戦略を立てます。
初期対応から示談交渉、不起訴処分獲得のための活動、さらには裁判での弁護まで、一貫したサポートを行っています。特に示談交渉においては、適切な賠償額の提示や交渉の進め方など、専門的な知識を活かしたサポートを提供し、成功率を高めることができます。
前科に関する不安や疑問を抱えている方は、一人で悩まず、早めに専門家に相談することをお勧めします。須賀法律事務所では無料相談を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。あなたの将来を守るための最善の方法を、一緒に考えていきましょう。