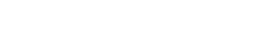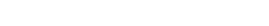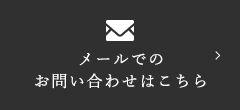2023/12/23 コラム
執行猶予付き判決と実刑判決の違いは何か?執行猶予が付く条件とは!?
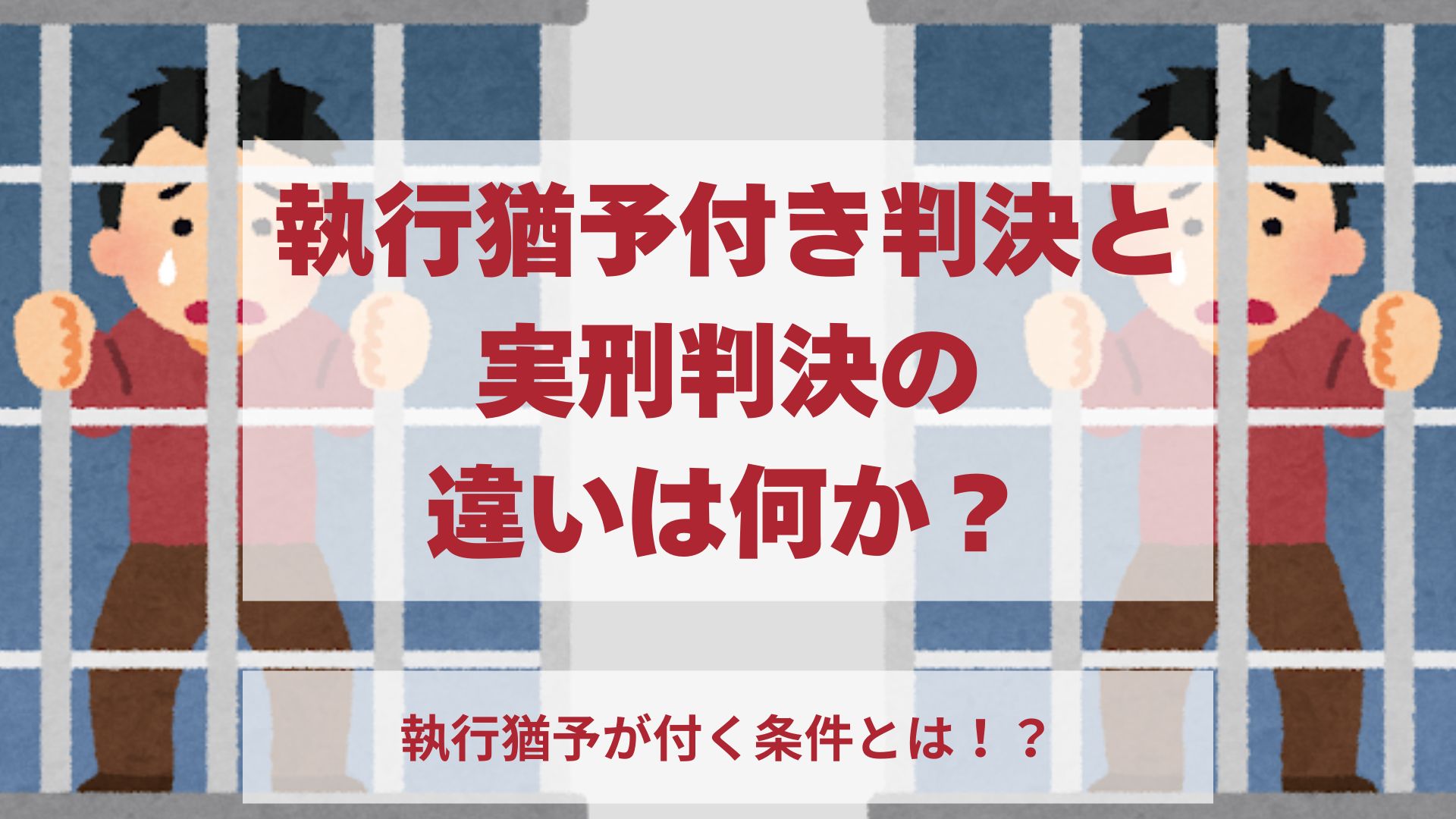
刑事事件で有罪判決が出たとき、刑務所に行かなくて済むケースがあります。それが「執行猶予付き判決」です。反対に、すぐに刑務所行きになるのが「実刑判決」。
この2つにはどんな違いがあるのでしょうか?
「執行猶予付き判決」って何?
執行猶予とは、有罪判決が出ても、すぐには刑罰を実行しないで一定期間様子を見るという制度です。
たとえば…
|
「拘禁刑1年・執行猶予3年」という判決なら、 この3年間の「猶予期間」を無事に過ごせば、 |
執行猶予は、社会が被告人に与える「更生の機会」であり、「再び過ちを犯さないこと」を前提に与えられた猶予です。与えられた時間を、反省と立て直しに使えるかどうかが、人生の次の一歩を左右します。
執行猶予中に注意すべきこと
再犯は厳禁
猶予期間中に再び罪を犯すと、執行猶予は取り消され、原判決に基づいて直ちに刑務所に収容される可能性が高まります。
前科は消えない
執行猶予がついても、有罪判決であることに変わりはなく、前科として記録されます。
▶ 前科があることで、以下のような不利益が生じる可能性があります。
就職活動や資格取得への影響
社会的信用の低下
再犯時の量刑判断で不利になる
| 前科については:前科がつくとどのようなデメリットがあるのか?前科がつかないようにするためには? |
法改正のポイント:執行猶予制度が見直されました(2025年6月施行)
令和の法改正により、執行猶予制度もより柔軟な運用が可能になりました。
ただし、その分「油断できない点」も増えています。
① 再度の執行猶予が可能に
これまで、一度執行猶予を受けた人が再度執行猶予を受けるのは極めて困難でした。
しかし改正後は、2年以下の拘禁刑で、かつ特別な事情(深い反省・更生の見込みなど)がある場合には、再度の執行猶予が認められる可能性があります。
➡「一度の過ちでは人生を終わらせない」という配慮がなされた制度です。
② 猶予期間を過ぎても刑の執行が可能に
もう一つ重要なのが、猶予期間が終わったあとでも刑の執行が可能になるケースがあるという点です。
たとえば、
|
執行猶予期間中に罰金以上の罪を犯し、その後に起訴(公訴提起)された場合 猶予期間が終わっていても、その新しい事件の判決が確定するまで執行猶予の効果が継続 |
つまり、「猶予期間が終わったからセーフ」とは限らないのです。判決が出るタイミングや起訴の時期によっては、猶予取り消しのリスクが残るという点には要注意です。
罰金刑に執行猶予がつくケースはある?
刑法第25条により、50万円以下の罰金刑に限って執行猶予を付すことが可能ですが、実務上は極めて稀です。
通常、罰金刑は確定すると一括で納付義務が生じます。
支払いが困難な場合、検察庁に相談することで分割払いや猶予が認められることもあります。
支払わなければ、財産の差押えや、最終的に労役場留置(代替拘禁)となることもあります。
罰金刑が確定したのに期限までに支払えなかったときは、
その人を「労役場」と呼ばれる施設に一定期間拘束する」という形で、罰金の代わりに刑罰を執行します。
*労役場留置(代替拘禁)とは、罰金を支払えない場合の代わりの刑罰です。
「実刑判決」とは?

執行猶予がつかない有罪判決は「実刑判決」と呼ばれます。
実刑になった場合以下のような生活を送ります。
1. すぐに身柄拘束・収容
判決が確定すると、その場で身柄を拘束され、刑務所に収容されます。
控訴しても勾留が続くことが多く、すぐに自由な生活は送れなくなります。
2. 刑務所での生活リズム
刑務所の生活は、厳格なルールと時間管理のもとで行われます。
▶ 典型的な1日の流れ(例)
6:45 起床
7:00 点呼・洗面・朝食
8:00〜17:00 作業(刑務作業)
→ 工場での製品加工や清掃など。
12:00〜13:00 昼食・休憩
17:00〜19:00 夕食・入浴・自由時間(読書・テレビなど)
21:00 消灯
3. 外部との関わりは?
手紙のやり取り:原則自由。ただし検閲あり。
面会:家族などに限られ、回数や時間に制限あり。
お金の使用:刑務所内で使える「購買品」(文具や日用品)の範囲で可。
4. 不自由な点
プライバシーがほぼゼロ:基本的に共同生活。個室は特別な場合のみ。
食事・入浴などは指定時間のみ
ルール違反には懲罰:私語・寝坊・指示違反で「反則」とされることも。
5. 出所後の生活に影響も…
社会復帰の難しさ:就職・住まいの確保に苦労することも多い。
前科の履歴は残る:再犯時に不利になることも。
実刑判決によって刑務所での生活が始まると、
「自分の意思で行動できる自由」は大きく制限されます。
ルールに沿った毎日を送る中で、外の世界との距離や、失ったものの重さを実感する人も少なくありません。
刑務所は、ただ罰を与える場所ではなく、「社会復帰のための反省と改善の場」ともされています。
とはいえ、再スタートには相当の覚悟と努力が必要です。
執行猶予がつく条件と取り消しのルール
刑事事件で有罪判決が出たとしても、すぐに刑務所に行かなくて済む場合があります。それが「執行猶予付き判決」です。
でもこの執行猶予、「誰でも」「どんな場合でも」つくわけではありません。
また、一度ついても「ルールを破れば取り消される」ことも。
今回は、執行猶予がつく条件と、外れてしまうケースについて、やさしく解説します。
執行猶予がつくには?
執行猶予を付けるかどうかは、裁判所が判断します。
ただし、付けるには「一定の条件」があります。
① 刑の重さが「そこまで重くない」こと
法律上、以下のような刑なら執行猶予をつけることができます。
拘禁刑3年以下
50万円以下の罰金
これ以上に重い刑(たとえば殺人で死刑など)は、執行猶予の対象外です。
② 前科の有無や内容も重要
裁判所は、被告人の過去の前科もチェックします。
前科がない人は、執行猶予がつく可能性が高くなります。
執行猶予中でも、2年の拘禁刑以下であれば、再度執行猶予がつく余地があります。
以前に拘禁刑以上の刑を受けたことがあっても、5年以上経っていれば、再び執行猶予がつくこともあります。
執行猶予が取り消される?
執行猶予がついている間は、「ちゃんと社会の中でやり直せるか」を見られている期間です。
でも、その間に問題を起こすと、せっかくの執行猶予が取り消されてしまうことがあります。
ケース①:必ず取り消されるとき(必要的取消)
次のような場合、執行猶予は絶対に取り消しとなり、刑務所に行くことになります。
- 執行猶予中に新たな犯罪を犯して、拘禁刑になった
- 判決前に犯していた別の犯罪で、あとから拘禁刑以上の刑が確定した
- 判決前に拘禁刑以上の刑を受けていたことが後から発覚した
つまり、「また重大な罪を犯した」「前から重い前科があった」ことがわかったら、執行猶予は即アウト、ということです。
ケース②:裁判所の判断で取り消されるとき(裁量的取消)
次のようなケースでは、取り消すかどうかは裁判所が判断します。
- 執行猶予中に罰金刑を受けた
- 保護観察中にルール違反を繰り返した
- 判決前に重い前科があると判明した
ここでは「反省してるか」「悪質だったか」などが考慮されます。
■ 執行猶予中の再犯の場合
たとえば、こんなケースを考えてみましょう。
| Aさんは「拘禁刑1年・執行猶予3年」の判決を受けていた。 しかし猶予期間中に万引きをして起訴され、「拘禁刑1年6か月・執行猶予3年」の判決が下された。 |
この場合、以下のような処理がされる可能性があります:

最初の拘禁刑1年については、執行猶予が取り消されて実刑となり、刑務所に収容される可能性が高い。
ただし、新たに言い渡された拘禁刑1年6か月の部分については、「再度の執行猶予」が認められる可能性があります。
つまり、Aさんは1年服役した後、釈放されて通常の生活に戻り、3年間は執行猶予期間になるということになります。
▶ 改正前と改正後の違い
このようなケースでは従来(改正前)であれば、合計2年6か月の実刑(服役)が必要でした。ところが改正後は、再度の執行猶予制度が導入されたことで、新しい刑(2年以下)については特別な事情があれば猶予される可能性が出てきました。
▶ 社会復帰を早めるための制度へ
再犯とはいえ、その内容や反省状況、社会復帰への支援体制などによっては、裁判所が「もう一度やり直すチャンスを与える」と判断することもあります。
この法改正により、本人の更生の見込みがあれば、すべてを実刑にせず、服役期間を短縮することが可能になりました。結果として、再スタートへの支援・社会復帰を早める効果が期待されています。
執行猶予をつけるにはどうすればいい?

裁判官に「執行猶予で更生できる」と思わせる材料が必要!
法律上の条件を満たしていても、最終的に執行猶予がつくかどうかは裁判官の判断次第です。以下のような事情が、執行猶予の判断に大きく影響します。
① 被害者との示談が成立している
被害者が「もう刑務所に入れなくてもよい」と考えていることは、執行猶予にとって大きなプラス材料。
慰謝料を支払い、謝罪を済ませていることも有利になります。
② 深く反省している
供述や反省文で、心から後悔している様子が伝わるかどうか。
被害者への謝罪だけでなく、「なぜ自分が間違ったのか」「今後どう生きるか」の自己分析も重要です。
③ 社会的な受け皿がある
安定した仕事・家庭環境・支援してくれる家族がいるかどうかは重要。
保護観察官や弁護士からの報告でも、「社会で更生できる体制」があると評価されます。
④ 再犯のおそれが低いといえる材料
生活環境の改善(引越し、交友関係の見直し)
カウンセリングの受診やアルコール治療など、再発防止の具体的努力
弁護士ができること
経験ある弁護士に依頼すれば、次のような形で執行猶予獲得のための準備ができます:
- 示談交渉のサポート
- 反省文や上申書の添削
- 家族の協力による誓約書作成
- 裁判官に響くような弁論内容の設計
執行猶予をつけてもらうには「条件」と「信頼」がカギ
- 法的に条件を満たしているか?
- 裁判所に「社会内での更生が可能」と信じてもらえるか?
- そのためにどんな準備ができるか?
これらを一つずつ丁寧に整えることが、執行猶予を得る最短ルートです。
当事務所では、初回相談無料で法律相談を受け付けております。
お気軽にお電話またはLINEにてお問い合わせください。
執行猶予中でも海外旅行はできる?パスポートの取得条件と注意点を分かりやすく解説!