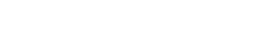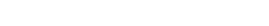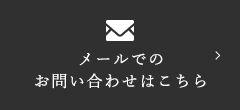2025/05/22 コラム
「酔って覚えていない」は通用する?酔って暴力事件を起こした場合の刑事責任と対応策

「飲みすぎて何も覚えていない」「気づいたら警察にいた」──
酒に酔った状態で暴力事件を起こし、あとから「記憶がない」と気づくケースは少なくありません。
「酔っぱらっていて事件を起こしたことを覚えていない場合罪に問われないのでは?」と考える方もいますが、実際には“酔っていた”というだけで免責されることはほとんどありません。
むしろ、被害者がいる場合は逮捕・勾留され、暴行罪や傷害罪として処罰される可能性が十分にあります。
「酔っていて覚えていない」状態での暴行と、しらふでの暴行とでは、刑罰の重さは異なるのか?
もし事件を起こしてしまった場合、どのように対処すればいいのか?
本記事では、酒に酔って暴力をふるった場合の刑事責任の考え方から、示談や弁護士ができる対応策まで、法律の視点からわかりやすく解説します。
|
【目次】 |
【刑事責任に影響する「責任能力」とは?】
暴力を振るうという行為に及んでしまった加害者が、刑事上どのような処分を受けるかを決める際に重視されるのが、「責任能力」の有無です。
たとえば、精神障害がある被疑者・被告人について、心神喪失と判断されて無罪となるケースがありますが、これはその者に責任能力がないと評価されるためです。
責任能力とは、
自身の行為が社会的に許されるかどうか(善悪)を判断する能力と、
その判断に基づいて行動を抑制する能力
を指します。
そして、責任能力がないとされた場合、そもそも犯罪は成立しません。
これは刑法上、違法行為があっても、有責性(非難可能性)がなければ処罰できないという原則があるためです。
一般的には、たとえ酩酊状態であっても、自ら飲酒していた場合は責任能力が否定されることはほとんどありません。
酒に酔って暴力行為に及んだとしても、「飲酒は自己の選択である」という前提に立ち、刑事責任を免れることは困難です。
ただし例外的に、極度の酩酊により現実認識が著しく阻害されていたようなケースでは、心神喪失や心神耗弱が認められる可能性もあります。
以下で、酩酊の程度と刑事責任の関係について詳しく解説します。

酩酊の種類と刑事責任への影響
酩酊(めいてい)とは、酒などのアルコールの影響によって心身の働きが異常をきたす状態を指します。
刑事事件においては、酩酊の種類によって責任能力があるかどうかが判断されます。主な分類は以下の3つです。
◉ 単純酩酊(たんじゅんめいてい)
-
多くの人が経験する「通常の酔っぱらい」状態
-
千鳥足になる、ろれつが回らない、声が大きくなるなど
-
判断力が鈍っても、基本的には自制心が保たれているため、責任能力は認められる
-
この状態での暴力行為は、通常どおり処罰対象となります
◉ 複雑酩酊(ふくざつめいてい)
-
アルコールによって著しく興奮したり、異常な行動をとる状態を指します
-
たとえば「会話が成り立たない」「1人で踊り出す」「大きな音でも起きない」など、ほぼ理性を失った状態が典型です
-
このような状態では、記憶は断片的だが、おおまかな状況は覚えていることが多いとされます
-
多くのケースで、「心神耗弱」にあたると判断される傾向があり、限定的な責任能力は認められることになります
-
刑法第39条2項により、「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」とされており、有罪でも刑が軽くなる可能性があります
◉ 病的酩酊(びょうてきめいてい)
-
少量の飲酒でも幻覚・妄想・意識喪失・記憶喪失などの重度の精神症状が生じる状態
-
発作的に暴力をふるう、現実と妄想の区別がつかない、といった極端な症状が現れる
-
医学的診断と病歴などの証拠が揃ったときに限り、「心神喪失・耗弱」と判断され罪に問われなかったり、刑が軽くなる可能性がある
-
ただし、極めて限定的で、自ら飲酒したケースではほとんど認められません
裁判での扱いはどうなる?
裁判では、酩酊の種類や程度に加えて、
-
飲酒量や時間、酔い方の特徴
-
周囲の証言(理性的だったか、会話できたか)
-
飲酒のきっかけ(自発的かどうか)
-
行為の計画性・犯行後の行動(逃走・証拠隠滅など)
といった事情が総合的に考慮されます。
つまり、「酔っていた」だけでは責任能力を否定できる根拠にはならず、むしろ悪質と判断されるリスクもあるのです。
【「記憶がない」は有利になる?不利になる?】
「酔っていて覚えていない」という発言は、事件を起こした後の取調べや裁判でしばしば見られます。
刑事責任を判断する際に重要とされるのは、「行為当時に責任能力があったかどうか」です。
つまり、その人が暴力をふるったときに、善悪の判断ができたか、自分の行動をコントロールできたかが問題となります。
一方で、「記憶がないかどうか」は、あくまで事件後の精神状態を示すものであり、刑事責任の有無とは直接関係しません。
記憶がないことで不利になるケースも
記憶喪失が主張されたとしても、それが責任能力の欠如につながらない限り、処罰は通常どおり行われます。
むしろ、記憶がないことによって次のようなデメリットが生じることがあります。
-
被害者に謝罪の言葉を伝えられない
-
事件の内容を否定も認めもできず、反省の態度が示しづらい
-
示談交渉で真摯な意思が伝わりにくく、相手に不信感を与える
このように、記憶喪失の主張は、場合によっては「反省していない」「責任逃れをしている」と受け取られ、裁判で不利に働くことすらあります。
記憶を失った状態と、しらふでの暴行とでは刑罰の重さは変わる?
基本的には、刑罰の重さは変わりませんが、しらふの場合よりも罪が重くなる可能性があります。
どちらも故意による暴行であり、酩酊していたからといって軽くなることは少ないのが実務上の傾向です。
「酒に酔うと暴れる傾向がある」と判断された場合には、再犯のおそれがあるとして重く評価されることすらあります。

【酔ったときに起こりやすい主な犯罪】
-
暴行罪(刑法208条)
殴る、蹴る、押す、胸ぐらをつかむ、唾を吐くなど、相手に対する不当な有形力の行使があれば成立します。
ケガがなくても暴行罪に問われます。
【2年以下の懲役・30万円以下の罰金】
-
傷害罪(刑法204条)
暴行の結果、相手にケガを負わせた場合に成立。鼻血、あざ、骨折、精神的ダメージも「傷害」に含まれることがあります。
【15年以下の懲役または50万円以下の罰金】
-
器物損壊罪(刑法261条)
物に対する破壊行為を対象とし、コップを割る、ドアを蹴る、スマホを壊すなどが該当します。公共物も含まれます。
【3年以下の懲役または30万円以下の罰金】
-
公務執行妨害罪(刑法95条)
警察官や消防士、公務中の職員に暴力や威嚇を加えた場合に適用される罪です。
たとえば、酔って騒ぎを起こした際に警察官に暴言や暴力を振るったり、職務質問を拒否して押し返す、パトカーを叩くなどの行為がこれに該当します。
【3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金】
|
傷害罪は特に重くなりやすく、医師の診断書や被害の程度が量刑に大きく影響します。 公務執行妨害罪は初犯でも逮捕・勾留されやすく、略式処分で済まないケースが多いです。 暴行罪や器物損壊罪は軽微なら示談・不起訴の可能性もありますが、被害者の感情次第で処分が重くなることも。 |
「無理やり飲まされた」上で記憶を失って暴力を振るった場合の処分は? 飲ませた側の責任は?
-
処分が軽くなる可能性はあるが、責任がなくなるわけではない
強引に飲酒を強要された事情が認められれば、情状として考慮される可能性はあります。ただし、実際に暴行行為があった場合には、処罰は避けられないのが一般的です。 -
飲ませた側にも法的責任が及ぶ場合がある
強要罪や過失傷害罪、安全配慮義務違反(職場の場合)など、飲ませた行為そのものが刑事・民事上の責任を問われることがあります。
【示談はできる?「謝罪できない・覚えていない」状況での対応策】
「酔っていたため、相手に何をしたか覚えていない」「謝りたくても何を謝ればいいかわからない」酩酊状態での事件では、こうした悩みを抱える加害者が少なくありません。
しかし、たとえ記憶がなくても、示談は可能です。
重要なのは、「結果として相手を傷つけてしまったこと」を真摯に受け止め、謝罪と補償の意思を示すことです。
記憶がなくても謝罪は成立する
刑事手続きでは、「覚えていない=責任がない」とはなりません。
したがって、「覚えていないけれど結果として被害が生じたことに対して謝罪し、償いたい」という姿勢を示すことは、十分に有効な対応とされます。
ただし、記憶がないまま本人が被害者に直接謝罪しようとすると、かえって誤解や反感を招くおそれもあります。
弁護士が入ることで伝わる「誠意」
このようなときこそ、弁護士を通じて謝罪と示談の意思を適切に伝えることが効果的です。
弁護士は次のような対応を行います。
|
弁護士が介入することで、加害者の反省と誠意が形式的・感情的なトラブルなしに相手へ伝わりやすくなります。
示談のメリット:不起訴や刑の減軽につながる可能性も
示談が成立すれば、次のような結果が期待できます。
-
初犯であれば不起訴処分となる可能性が高まる
-
起訴された場合でも、刑が軽くなる、執行猶予がつくなどの情状酌量が認められやすい
-
被害者が「処罰を望まない」と明言した場合、処分に大きな影響を与える
ただし、被害感情が強い場合や、態度に誠実さが感じられない場合は、示談が難航することもあります。
酩酊による事件であっても、責任から逃げずに対応する姿勢こそが、今後の人生にとって最善の選択となります。
記憶がない場合でも、早期に弁護士に相談し、適切な示談交渉を進めることが重要です。
|
示談についてはこちら: |

【被害に遭った場合の対応方法】
酔っ払った相手に絡まれ、暴力を受けた──。
そのような被害に遭ったとき、相手が記憶をなくしていそうな様子だと、「後から事実を否定されるのでは?」と不安になる方も多いでしょう。
実際、加害者側が「覚えていない」と主張するケースでは、証拠の有無が非常に重要になります。
✅ 写真や動画を撮る
-
加害者の顔、服装、言動(できれば音声付き)をスマホで撮影
-
自分のケガ(アザ・出血・腫れなど)や壊された物(スマホ・眼鏡など)も撮っておく
-
現場の様子や周囲の混乱、第三者の存在も撮影できるとベスト
✅ 目撃者の連絡先を聞いておく
-
「見ていましたよ」と声をかけてくれた人がいれば、連絡先を聞いておく
-
店員・警備員・通行人など、第三者の証言があると後日の警察対応や裁判で有利に働きます
✅ 警察をすぐ呼ぶ
-
現場で暴行を受けた場合、必ず110番通報してください
-
現場に警察が来れば、実況見分が行われ、公式な記録(被害届・調書)が残ります
-
警察を呼ぶことが、「相手が酩酊状態だった」という客観的な証明にもつながります
✅ 医師の診断書を取る
-
暴行を受けた場合、早めに病院で診察を受け、診断書を取得しましょう
-
これは傷害罪や損害賠償請求において非常に重要な証拠となります
相手が「覚えていない」と言っても、あなたが受けた被害は事実です。
証拠を適切に残すことで、警察・弁護士・裁判所も事実を立証しやすくなります。
|
被害届についてはこちら: |
当事務所では、初回相談無料で法律相談を受け付けております。
お気軽にお電話またはLINEにてお問い合わせください。