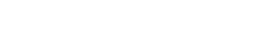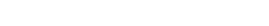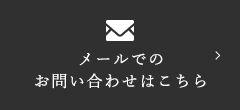2025/02/10 コラム
副業がバレたらクビになる?解雇・懲戒処分の基準やトラブル回避のポイントを解説
近年、副業に関する関心が高まる中、「副業禁止」と明記した就業規則を設ける企業も多くなっています。しかし、実際に副業が会社にばれた場合、即座に解雇や懲戒処分となるのかは、ケースバイケースです。本記事では、弁護士の視点から、副業禁止の会社において解雇や懲戒処分が認められる基準と、その合理的な理由について解説します。
【副業禁止規定の背景と目的】

多くの企業が副業を禁止する理由は、以下のような観点にあります。
- 企業の信用維持:従業員が副業で企業イメージに反する行動をとることを防止するため。
- 就業規則の統一:従業員間のトラブルや利益相反の回避を目的としています。
- 業務への影響防止:副業が本業に悪影響を及ぼす可能性を排除するため。
ただし、就業規則に「副業禁止」とあっても、全ての副業が即解雇の対象になるわけではありません。実際の解雇や懲戒処分は、「合理的な理由」が必要とされます。
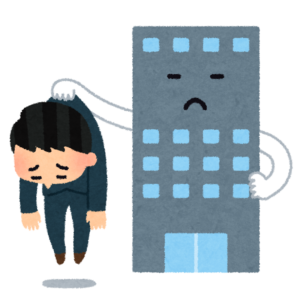
【 副業がバレたらクビになる?解雇・懲戒処分の基準を解説】

副業に関して会社が懲戒処分を行う際、以下のポイントが重要な基準となります。
就業規則の明確性と合理性
- 就業規則の内容:副業禁止規定が明確かつ具体的に記載されているか。たとえば、禁止される副業の種類や条件が具体的に示されている場合、処分の根拠として認められやすいです。
- 合理的な範囲:会社の業務や信用に実際に悪影響を及ぼすか否かが重要です。副業が本業に支障をきたさない場合や、企業イメージに直接関係しない場合、即時解雇の合理的理由とは認められない可能性があります。
副業の内容とその影響
- 副業の種類:飲食業、オンラインショップ、ブログ運営など、具体的な副業の内容によって判断が異なります。企業の業種や業務内容と競合する場合、懲戒処分の対象になりやすいです。
- 業務時間の管理:副業が本業の勤務時間中に行われた場合や、疲労による業務パフォーマンスの低下が認められる場合は、解雇理由となり得ます。
副業で裁判になった実例
- 実際の判例: 運送会社の運転手が年に1,2回の貨物運送のアルバイトをしたことを理由とする解雇に関して、職務専念義務の違反や信頼関係を破壊したとまでいうことはできないため、解雇無効とした事案。
- 判決: 副業回数が年に1,2回であり、本業への支障がなかったため、解雇処分が無効とされた。
【副業がバレてもクビにならないケースとは?】

多くの副業が実際には「解雇」には至らないケースが多数存在します。具体例としては以下の通りです。
- 副業が業務に影響を与えていない場合:勤務時間外に行われ、かつ企業の利益や信用に直接影響を及ぼさない場合は、懲戒処分に至らないケースがほとんどです。
- 会社が実際に損害を被らなかった場合:副業が会社の競合に該当せず、また業務効率にも影響がない場合、解雇理由として合理的と認められにくいです。
- 内部指導や注意に留まる場合:初回の副業発覚時は、口頭注意や文書による指導で済むケースが多く、段階的な対応がなされることが一般的です。
【副業がバレた際の流れ】

副業がバレた際には、注意指導が行われ、それでも会社の方針に従わない場合、懲戒処分へと進むことが考えられます。副業がバレた際の流れについて詳しく説明します。
①注意指導
副業がバレた際、通常は会社の方針に沿った注意指導が行われます。
会社が副業を認めていないケースや、副業が本業に支障をきたしていると判断された場合、従業員は注意指導を受ける可能性があるでしょう。
注意指導の例
- 副業の実態把握
- 違反行為への警告
- 改善の要請
- 業務委託契約などの条件変更
従業員がこの指導に従わない場合、社内規定に基づき懲戒解雇となる可能性もあります。その場合、副業を続けるか、本業に集中するかという重要な選択を迫られるでしょう。
注意指導は副業が発覚した際の最初の対応として非常に重要で、従業員は会社の方針を改めて理解することや、適切な対処が求められます。
②指導に従わない場合は懲戒処分
多くの会社では、副業の可否について異なるルールを定めています。副業が禁止されているにもかかわらず、従業員が許可なく副業を行っていると判明した場合、通常は最初に指導が行われます。
この指導は副業の中止を求めるものであり、もし従業員がこれに従わない場合、懲戒処分が科される可能性があるでしょう。懲戒処分の種類としては、軽いものから重いものまで様々です。
懲戒処分の種類
- 注意
- 戒告
- 減給
- 停職
- 解雇
実際に、副業が本業に悪影響を与えているにもかかわらず、それを改めなかった従業員が解雇された事例も存在します。解雇は、会社と従業員間の信頼関係が完全に失われた場合にのみ取られ、従業員にとって非常に大きな影響を及ぼす処置です。
副業に関するルールは会社によって大きく異なります。したがって、従業員は自身の雇用契約や社内規定をしっかりと理解する必要があり、懲戒処分のリスクを避けるためには、会社からの指導には真摯に対応する姿勢が欠かせません。
③合意退職の提案
副業が理由で解雇に至る場合、雇用主側から従業員に対し「合意退職」を提案されることが少なくありません。これは、正式な解雇手続きを行う前に、会社と従業員がお互いに合意して退職するという方法です。企業としては、この合意退職によって、不当解雇として訴えられるリスクを減らす意図があります。
合意退職に応じる際には、解雇予告手当や退職金の交渉など、従業員にとって有利な条件を引き出せる可能性はあります。しかし、正式な解雇手続きと比較すると、従業員が受けられる法的保護は弱まるでしょう。
副業が発覚した後の流れとして、従業員がこの合意退職の提案を拒否した場合、次の段階として解雇の手続きが進む可能性が高いです。特に、副業に関して明確な社内規定が存在する場合、それに違反したことを理由とする解雇は「懲戒解雇」となり、その際には解雇予告手当や退職金が支払われないことも考えられます。
従業員が会社から合意退職を勧められた際には、その提案を慎重に検討し、自身にとって最も有利な選択をすることが重要です。必要であれば、弁護士などの法律の専門家への相談も、有効な手段と言えるでしょう。
【副業がバレた際の5つの対処法】

副業がバレた際は「本業には影響がない」と明確に伝えることが大切です。円滑に対処できるよう、具体的な手段を解説します。
①スキルアップのための副業だと伝える
副業で身につけた能力が、本業に良い影響を与える可能性も考えられます。もし副業が会社に知られた際には「副業を通じて得たスキルが、本業においてもプラスになっている」という点を伝えることが、有効な対処法の一つです。
例えば、副業でプレゼンテーションのスキルが向上したり、新しいソフトウェアの操作を習得したりした場合、それらの技能が日々の業務でどのように役立っているかを具体的に説明し、会社の利益に貢献していると示してみましょう。
このように率直なコミュニケーションをとることによって、副業がネガティブな問題として認識されるのを避けられます。また、自身の成長に繋がり、最終的に会社にも貢献しているというプラスの評価を得られる可能性も高まります。
②趣味の一環として副業をしていると伝える
副業がバレて解雇されるリスクを避けるには、副業が趣味の範囲で個人的な楽しみであると、正直に伝えるのが一つの手段です。一般的に、趣味の副業であれば収入は少なく、心身の負担も小さいと考えられるため、本業への影響は少ないと説明できます。
会社には副業の収入が限定的であり、本業の業務や成果には支障がないと明確に伝えて理解を求めましょう。ささやかな趣味の範囲であると伝えれば、会社に受け入れてもらいやすくなります。
③短い期間のみ副業をしていると伝える
家業の手伝いや、お盆や年末年始といった短期間のみ副業を行うケースもあるでしょう。もしそのような一時的な副業が会社に知られた場合は、その期間が限定的であると伝えれば、本業への影響はないと理解を得られる可能性が高まります。
継続的な副業ではないため、今後は本業に専念する意思を示すことで、会社も納得してくれるかもしれません。期間限定の副業であれば許可を得やすいため、始める前に事前に相談しておくのも有効な手段です。
④やむを得ない理由があることを伝える
副業が発覚して解雇の可能性が出てきた場合、やむを得ない理由があることを説明しましょう。例えば「生活費が足りないため」とか「借金やローンの返済のために、どうしても副業が必要だった」といった状況を率直に伝えることが、解雇を回避するための対処法となります。
伝える際には謙虚な態度を心がけて嘘偽りなく、具体的な金額などを示しながら、経済状況がどれほど厳しいかを伝えると効果的です。副業をせざるを得なかった理由をしっかりと伝えれば、会社側の理解を得られる可能性は高まります。
⑤副業を辞めるか副業を本業にするか決断する
具体的な副業への対応策として「副業を完全にやめる」か、「副業を本業にする」という二つの選択肢が考えられます。
副業を断念すれば、本業に集中する姿勢を示すことができ、解雇のリスクを避けられます。しかし、その反面、収入の減少は避けられません。一方、副業に力を入れてキャリアチェンジを目指す場合、新たな可能性が広がる一方で、現在得ている安定した収入を失うというリスクを伴います。
もし、理由をつけて両方を無理に続けようとすると、後々嘘が発覚した場合に信用を大きく損ない、状況がさらに悪化しかねません。そのため、誠実な判断が求められます。
副業による解雇という事態を避けるためには、これらの選択肢それぞれの利点と欠点を慎重に比較検討し、ご自身の持続可能な生活設計に合った道の選択が重要です。
【副業がバレて不当解雇された際の対処法】

不当解雇だと感じた場合は、まず弁護士に相談することが大切です。弁護士は、解雇の有効性や、あなたがどのような権利を持っているかについて、法律に基づいてアドバイスをしてくれます。次に、具体的な対処法を見ていきます。
就業規則に反していないかを確認する
副業が原因で解雇されるかもしれない状況になったら、まず最初にご自身の働き方が会社の就業規則に違反していないかを確認しましょう。
就業規則には、従業員が守るべきルールや、解雇理由となる行為、副業を禁止する規定などが書かれています。これらの規則を確認すれば、副業による解雇が法的に見て正当かどうかを判断する手がかりになります。
- 就業規則に副業禁止のルールがある場合: 副業をしたことが規則違反となり、会社は解雇という措置を取る理由を持つ可能性があります。
- 就業規則に副業に関する記載がない場合: 副業を理由とした解雇は、不当解雇である可能性が高くなります。
もし就業規則が手元にない場合は、会社に対して見せてもらうか、コピーをもらう権利があります。不当解雇だと感じた場合に就業規則を確認することは、その後の対応を検討する上で最初の重要なステップです。
ご自身の権利を守るためには、就業規則の内容をきちんと把握しておく必要があり、特に副業を始める前にはこの点に注意しておきましょう。
解雇理由を明確にする
副業が理由で解雇された場合、その解雇が法律上の「不当解雇」にあたるかどうかを見極めるためには、まず会社がどのような理由であなたを解雇したのかをはっきりさせる必要があります。
不当解雇への対応を考える上で解雇された従業員は、会社に対して解雇理由を記載した証明書を発行してもらう権利があります。この解雇理由証明書には、解雇の理由が具体的に書かれていなければなりません。
たとえ副業が解雇の理由として示されている場合でも、その副業が会社の利益を損なうなど合理的な理由がない限り、その解雇は不当と判断される可能性があります。
対応の流れ
- 解雇理由証明書を入手する: まず会社に解雇理由証明書の発行を求めます。
- 内容を詳しく確認する: 受け取った証明書に書かれている解雇理由を詳細に検討します。
- 必要に応じて弁護士に相談する: 解雇理由に納得がいかない場合や、不当解雇の可能性があると感じた場合は、弁護士に相談して専門的な意見を聞きましょう。
- 次のステップを検討する: 弁護士のアドバイスを踏まえ、労働基準監督署への相談や労働審判の申し立てなど、次の具体的な対応を検討します。
もし解雇の理由が曖昧であったり、納得できるものではないと感じた場合には、不当解雇として法的な手段を取ることも選択肢の一つとなります。
解雇の無効化や金銭請求を行う
副業を理由とした解雇が「不当解雇」と判断できる場合、従業員には解雇の効力を否定したり、金銭的な補償を求めたりする権利が発生します。不当解雇とは、労働法で認められた正当な理由がない解雇のことです。
これに該当する場合、従業員は労働審判や裁判といった手続きを通じて、解雇が無効であるという判断を求めることができます。さらに、不当解雇によって得られなくなったはずの給与や、未払いの解決金、残業代などの金銭的な請求も可能です。
法的な対応としては、まず会社との間で話し合いによる解決を試み、それでも解決しない場合には労働局に相談し、その後に労働審判や裁判へと進むのが一般的な流れです。従業員は、これらのプロセスを通じて、自身の正当な権利を守ることができます。
【弁護士が提案する副業トラブル回避のポイント】

副業禁止規定に抵触しないための予防策として、以下のポイントを押さえておくと安心です。
- 就業規則の確認:副業を始める前に、自社の就業規則をしっかり確認しましょう。副業が明示的に禁止されている場合、その内容を理解し、会社に悪影響を及ぼさないように計画を立てることが重要です。
- 上司や人事への相談:副業開始前に、可能であれば上司や人事部門に相談し、問題が生じないか確認することが望ましいです。
- 副業の内容と時間管理:本業に支障をきたさないよう、副業の内容や勤務時間外での活動に留めるよう工夫することが求められます。
- 法律相談の活用:副業トラブルに関して疑問がある場合は、早期に弁護士に相談することで、トラブルの拡大を防ぐことができます。
【副業がバレてトラブルになる心配がある方は須賀法律事務所へ】

副業禁止の会社において、実際に副業がばれた場合でも、合理的な理由がなければ即解雇や厳しい懲戒処分には至りません。就業規則の内容、副業の実態、そしてその影響を総合的に判断することが重要です。
労働トラブルについてはこちらのコラムを参照ください。
▶労働トラブル発生!労働基準監督署(労基)と弁護士、どちらに相談すべきか徹底比較
当事務所では、労働問題や副業に関するトラブルについて、無料相談を実施しております。副業に関する疑問やトラブルが生じた場合は、ぜひお気軽にお問い合わせください。