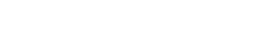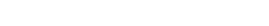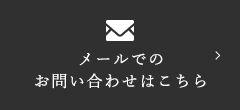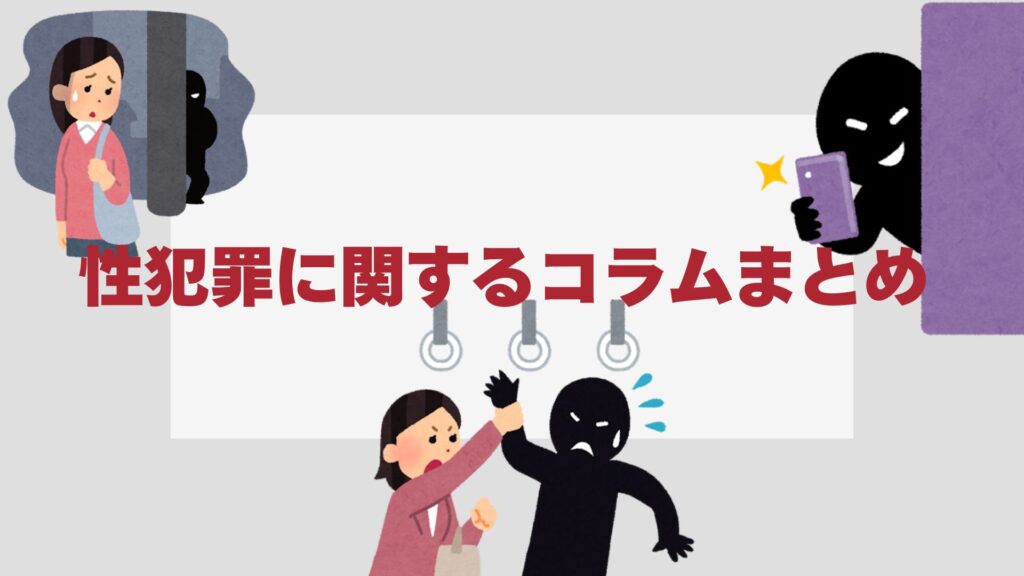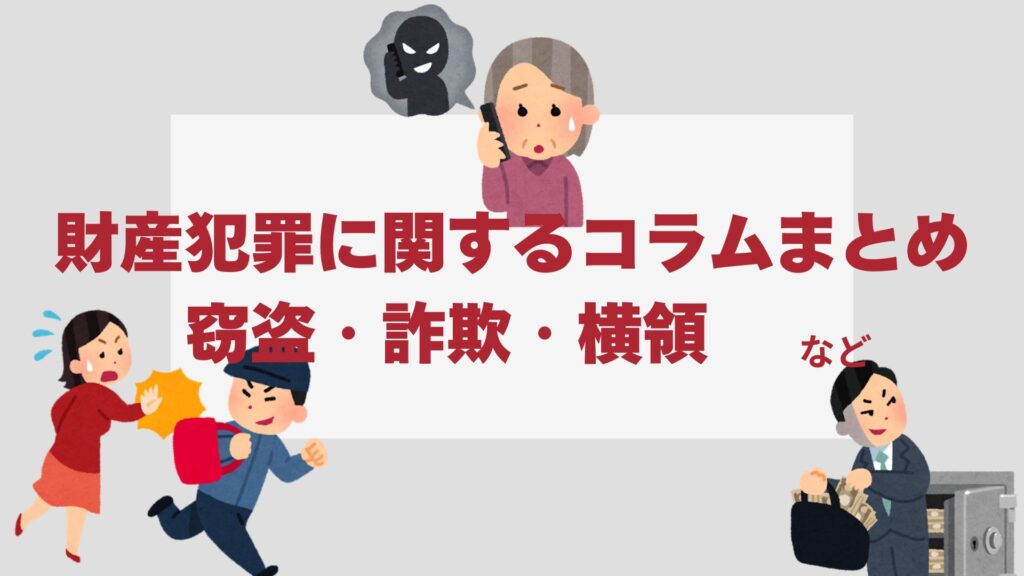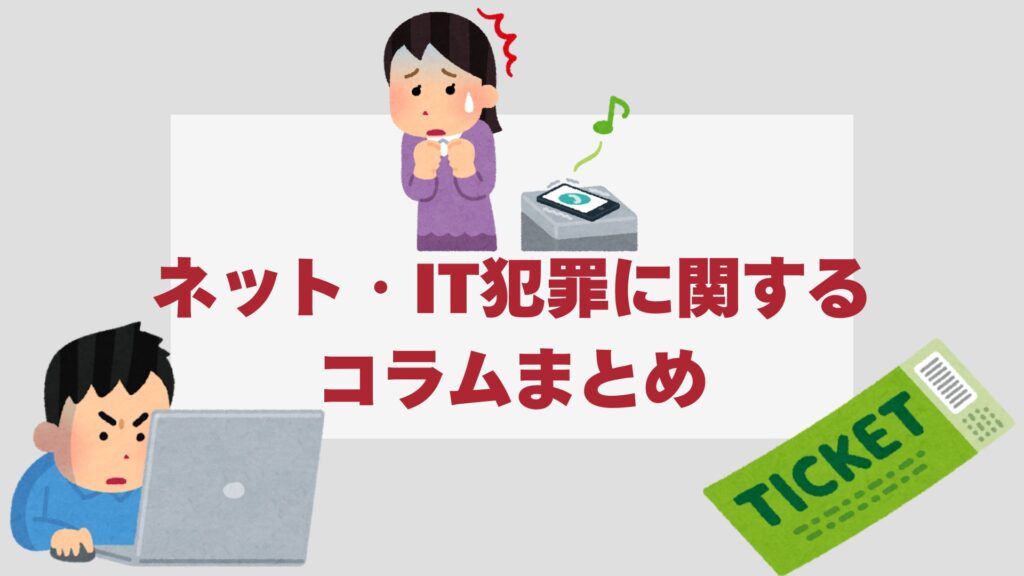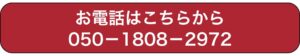2025/09/30 コラム
【弁護士監修】警察からの連絡~裁判まで|刑事手続きの基礎知識と実務対応【コラム一覧】
.wpacc { max-width: 840px; margin: 1rem auto; } .wpacc .item { margin: .5rem 0; } .wpacc .btn { width: 100%; text-align: left; background: #f7f7f7; /* 薄いグレー */ border: 1px solid #e6e6e6; border-radius: 12px; padding: .9rem 1rem; font-weight: 700; cursor: pointer; } .wpacc .btn:focus-visible { outline: 2px solid #555; outline-offset: 2px; } .wpacc .btn::after { content: “+”; float: right; font-weight: 700; } .wpacc .btn[aria-expanded=”true”]::after { content: “−”; } .wpacc .panel { border: 1px solid #eaeaea; border-top: none; border-radius: 0 0 12px 12px; padding: .75rem 1rem 1rem; background: #fafafa; margin-top: -8px; } /* 固定ヘッダーで隠れないように(ページ内リンク対策) */ .wpacc .item[id] { scroll-margin-top: 96px; } /* お好みで余白・文字サイズ調整 */ .wpacc p { margin: .5rem 0; line-height: 1.8; } 無料相談はこちら(フォームは24時間受付・全国対応)
「警察から“任意でお話を”と連絡が来た」「任意同行を求められて不安」「取調べで何を話すべきか迷う」「家宅捜索の令状が届いた/差押えされた」——刑事手続の初動は、ある日いきなり訪れます。
そんな“いざ”のときに迷わないため、状況別にまず何をすべきか/やってはいけないかを確認できます。
コラムラインナップ
-
被害届・刑事告訴に関するコラム
被害の内容を警察に伝える「被害届」と、加害者の処罰を強く求める「告訴」では、その意味や効果が異なります。ここでは、それぞれの特徴や手続の流れ、注意点について解説します。 -
任意同行・事情聴取の対応に関するコラム
任意同行・事情聴取は“任意”であっても実質的な拘束に感じることがあります。同行・出頭の可否、同席、録音、帰宅の意思表示など基本ルールを押さえましょう。 -
取調べ対応に関するコラム
取調べでは、供述書への署名・押印、黙秘権の使い方、誘導や圧力に対する対処が肝心です。虚偽自白の兆候を知り、弁護士と方針を合わせて臨みましょう。 -
家宅捜索に関するコラム
家宅捜索・差押えの現場では、令状の確認、立会人の要請、差押目録の記載確認など、即時の判断が必要です。無用なトラブルを避けつつ権利を守りましょう。 -
警察から呼び出しに関するコラム
警察からの呼出や自宅への訪問があると不安がつのります。もっとも、逮捕の要件や初動の選択肢を知れば回避できる局面もあります。出頭や連絡の仕方、弁護士への早期相談が鍵です。 -
家族が逮捕されたら
家族が突然逮捕された場合は、勾留阻止や早期釈放に向けた初動が重要です。接見禁止の有無や面会方法、準抗告等を確認し、必要資料を速やかに整えます。 -
在宅事件の進み方(逮捕されないケース)
在宅事件は逮捕されずに捜査が進む類型です。もっとも、書類送検・起訴の可能性はゼロではありません。呼出対応や資料提出の作法を把握しておきましょう。 -
私人逮捕・正当防衛の基礎に関するコラム
現場での衝突は、私人逮捕・正当防衛の誤解がトラブルを拡大させます。成立要件や限界を理解し、過剰防衛や不当拘束を避ける知識を持ちましょう。
刑事事件は、ちょっとしたトラブルでも一度手続きが進めば生活や仕事に大きな影響を及ぼします。しかも「前科と前歴の違い」「示談の効力」「責任能力の有無」など、専門的で分かりにくいポイントが多いのも事実です。
このコラムでは、略式起訴や罰金刑、前科・前歴、自首や示談の注意点、そして裁判で押さえておきたいルールまで、弁護士の視点から分かりやすく解説します。
-
略式起訴(略式命令)は手続が早い一方で、罰金の納付により原則として前科がつきます。 罰金を払えない場合の流れ(労役場留置)も知っておくと安心です。
-
「前歴」は捜査歴等を指し、「前科」は有罪判決の確定で付く別概念です。 生活・就業への影響、そして前科を避けるための現実的な選択肢も押さえましょう。
-
自首は量刑に影響し得ますが、すべての事案で有利とは限りません。 成立要件やリスクを理解したうえで、弁護士と方針を決めましょう。
-
示談は不起訴や量刑に影響し得ますが、強要された示談書の有効性や、相手が受け取らない場合の供託など、 実務上の落とし穴に注意が必要です。
「ちょっとした口論が暴力事件に発展してしまった」「ケンカをしただけなのに警察沙汰になった」──暴力犯罪に関するご相談は後を絶ちません。
傷害罪や暴行罪は、相手に怪我を負わせていなくても立件されることがあり、逮捕・勾留に至るケースも少なくありません。
-
-
傷害罪や暴行罪は、相手に怪我を負わせていなくても立件されることがあります。さらに、DVは家庭内トラブルから刑事事件化する典型的なケースです。そのため、早期の弁護活動や被害者との示談が重要になります。
-
DV等の事案では、刑事対応と並行して家事の調整が必要になることがあります
-
脅迫や恐喝は、実際に暴力を振るわなくても「相手を畏怖させる」言動によって成立します。特に、SNSや職場でのやり取りから事件化するケースも増えているため、注意が必要です。
-
警察官などの公務を妨害した場合には公務執行妨害罪に問われます。また、企業や店舗の業務を妨害した場合には業務妨害罪に当たります。さらに、カスタマーハラスメントや過剰なクレーム対応も刑事事件化する可能性があるため、注意が必要です。
-
他人の物を壊す行為は器物損壊罪に当たります。さらに、たとえ軽微な破損であっても告訴があれば処罰対象になります。特に文化財や公共物を損壊した場合には、非常に重い責任を負う可能性があります。
「気づいたら警察に連行されていた」「合意があったはずなのに逮捕された」──痴漢や盗撮、性犯罪に関するご相談は後を絶ちません。
一度逮捕されてしまうと、社会的な信用や仕事、家庭への影響も大きく、頭を抱えてしまう方がほとんどです。このようなケースでは、早期に正しい対応をとることが極めて重要です。弁護士に相談することで、示談交渉や不起訴処分の可能性を高める道が開けることもあります。
-
痴漢とは、わいせつな意図で卑わいな言動や行為などの性的嫌がらせのことです。直接的な接触がなくとも、痴漢行為に当たる場合があります。「迷惑防止条例違反」で処罰されると、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金刑になるケースが多いです。
-
盗撮は、相手の承諾なく衣服や身体を撮影する行為で、近年は「撮影罪」が新設され厳しく取り締まられています。条例違反にとどまらず、刑法や新設された特別法で処罰対象となる場合もあり、検挙数が増加している分野です。
-
執拗なDMや待ち伏せ・尾行などは、記録化のうえ警察相談・警告や規制法の運用で停止を図ります。 緊急時は110番・避難、証拠はそのまま保持してください。
-
不同意性交罪や不同意わいせつ罪は、相手の同意がない性的行為を処罰する罪です。2023年の刑法改正で新設され、これまでの「強制性交等罪」よりも幅広い行為が処罰対象となりました。「合意があった」と思っていた場合でも立件される可能性があり、誤解や冤罪も多い分野です。
-
売春は「売春防止法」によって禁止されており、実際に金銭の授受を伴う性交を行った場合に処罰対象となります。単なる合意による性交では処罰されませんが、勧誘や斡旋、場所の提供など周辺行為は厳しく取り締まられています。
-
未成年者との性行為や交際は、本人の同意があっても処罰される場合があります。児童ポルノ禁止法や青少年保護育成条例など、多層的な法律で規制されており、SNSでの画像送信やメッセージのやり取りも摘発対象となることがあります。
-
SNSや動画投稿サイトにわいせつな画像や動画をアップロードする行為は、児童ポルノ禁止法やリベンジポルノ防止法に抵触する可能性があります。被害者からの削除請求や刑事告訴に発展するケースも多く、ネット犯罪の典型例となっています。
「軽い気持ちで万引きをしてしまった」「会社のお金を使い込んでしまった」「だまされて知らずに詐欺に加担してしまった」──財産犯罪は日常生活の身近な場面で起こり得る事件です。
-
窃盗や万引きは、身近な犯罪として最も多く取り扱われる分野です。たとえ初犯であっても実刑判決を受ける可能性があり、再犯であればより厳しい処罰となります。
-
詐欺は、相手をだまして財産的利益を得る行為です。さらに、SNSやマッチングアプリを利用した「恋愛詐欺」なども増加しており、注意が必要です。
-
横領は、預かっている他人の財産を自己のものにする行為です。特に、業務上横領は非常に重く扱われ、長期の実刑判決になることも少なくありません。
-
「子どもが万引きをして警察に呼ばれてしまった」「ケンカで相手に怪我をさせてしまった」「SNSのやり取りが性犯罪になると言われた」──少年事件は保護者にとって突然の出来事であり、大きな不安をもたらします。
-
まず、少年法の適用範囲や特定少年・逆送の基準を理解すると見通しが立てやすくなります。 さらに、警察対応から送致、観護措置、審判までの流れを把握することで、無用な不安を軽減できます。
-
ときに、虐待の疑いで児童相談所の一時保護がなされ、面会が制限される場合があります。 このとき、手続の根拠と対応策を知ることが極めて重要です。 また、再発防止の観点から、日常で子どもに伝えるべき法律・防犯教育も欠かせません。
-
さらに注意すべきは、同意があっても処罰対象となり得る未成年との性行為や、 SNSでのわいせつ画像の授受・アップロードです。実名報道・前科のリスクがあるため、初動が肝心です。
-
いじめは学校内の問題にとどまらず、暴行・脅迫・名誉毀損などの犯罪に該当し得ます。 したがって、証拠の確保と学校・警察との連携、そして被害回復を見据えた対応が欠かせません。
「SNSで誹謗中傷を受けてしまった」「ネットに無断で写真や動画を転載された」「ディープフェイクを使われて被害にあった」──ネット・IT犯罪は、誰もが被害者にも加害者にもなり得る現代的なトラブルです。
-
SNSの投稿・コメントによる誹謗中傷は名誉毀損罪・侮辱罪に発展し得ます。削除請求や発信者情報開示が有効です。
-
恋愛詐欺・フィッシング詐欺は巧妙化。証拠保全と返金・刑事対応の検討を急ぎましょう。
-
人気公演の高額転売は「チケット不正転売禁止法」で規制対象。SNSや転売サイト経由でも摘発例があります。
-
漫画・アニメの台詞や画像、映画の内容を無断で投稿すると著作権侵害になり得ます。
-
「海外サイトならOK」は誤り。日本では賭博罪に当たり、利用者が摘発されるケースもあります。
-
当事務所は、薬物事件に豊富な実績を持つ弁護士チームとして、示談交渉だけでなく治療プログラムの提案や再犯防止策まで幅広くサポートしています。
「免許の更新を忘れて運転してしまった」「接触していないのに“ひき逃げ”と言われた」「ガードレールに当てたけれど、通報すべき?」「自転車のルールが不安」――交通のトラブルは、思いがけず刑事手続に発展することがあります。とはいえ、正しい順番で対応すれば落ち着いて対処できます。
-
刑事責任とは別に、被害者への損害賠償(治療費・休業損害・慰謝料等)が問題となります。 交渉の準備と主張立証のポイントを理解しておきましょう。
-
免許の有効期間切れや失効状態での運転は「無免許運転」に該当し、刑事処罰・行政処分の対象です。 更新を失念していた場合でも、情状や対応次第で処分が変わり得ます。
-
接触がなくても、被害者が転倒・負傷した場合は「ひき逃げ」が成立し得ます。 事故後の救護・報告義務を怠ると、重大な刑事責任を負うため初動が重要です。
-
ガードレール等への接触は物損事故であっても、通報・報告・必要な救護等の義務が課されます。 連絡を怠ると行政処分・刑事責任に及ぶおそれがあります。
-
自転車は「車両」です。努力義務といえど、事故時の過失評価や安全配慮義務に影響し得ます。 ルールを理解してトラブルを未然に防ぎましょう。
/* 最小JS:クリックで開閉。data-single-open=”true” なら他を自動で閉じます。 */ document.addEventListener(‘click’, function(e){ const btn = e.target.closest(‘.wpacc .btn’); if(!btn) return; const item = btn.closest(‘.item’); const panel = document.getElementById(btn.getAttribute(‘aria-controls’)) || item?.querySelector(‘.panel’); const root = btn.closest(‘.wpacc’); const singleOpen = (root?.dataset.singleOpen === ‘true’); const expanded = btn.getAttribute(‘aria-expanded’) === ‘true’; // 1開・他閉 if(singleOpen){ root.querySelectorAll(‘.btn[aria-expanded=”true”]’).forEach(b=>{ if(b !== btn){ b.setAttribute(‘aria-expanded’,’false’); const p = document.getElementById(b.getAttribute(‘aria-controls’)) || b.closest(‘.item’)?.querySelector(‘.panel’); if(p) p.hidden = true; } }); } // 対象トグル btn.setAttribute(‘aria-expanded’, String(!expanded)); if(panel) panel.hidden = expanded; }); // キーボード対応(Enter/Space) document.addEventListener(‘keydown’, function(e){ if((e.key === ‘Enter’ || e.key === ‘ ‘) && e.target.classList?.contains(‘btn’)){ e.preventDefault(); e.target.click(); } });
当事務所の特徴
刑事事件は逮捕や勾留といった身柄拘束につながる可能性が高く、初動対応の遅れがその後の人生に大きな影響を与えます。
当事務所は暴行・傷害、窃盗・詐欺、薬物事件、性犯罪など幅広い刑事事件の弁護経験を有しています。
-
初回相談は無料
-
全国対応・オンライン相談可能
-
逮捕・勾留に対する即時対応が可能
-
示談交渉・不起訴獲得・執行猶予の実績多数
-
被害者・加害者いずれの立場でも迅速に対応可能
刑事事件は一度手続きが進むと取り返しがつかなくなることも少なくありません。
迷ったらすぐにご相談ください。