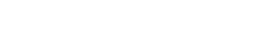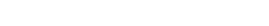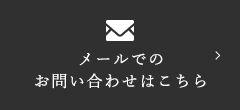2025/10/05 コラム
密漁で逮捕?趣味の釣りや潮干狩りでトラブルを避けるための基礎知識

「釣っただけで逮捕?」趣味が密漁になるケース
近頃、「レジャーで釣りをしていただけなのに、密漁で逮捕された」といった相談を受ける機会が増えています。海や川でのんびり釣りを楽しむ行為が、知らぬ間に“犯罪”になっていたというケースは意外と多く、2023年の密漁の検挙件数は全国で1,653件にも上ります。
このうち、漁業関係者によるものはわずか125件。実に約9割が、一般の人による密漁だったのです
(参考:農林水産省「密漁対策の現状と取組」)。
この数字からも、「趣味のつもりだった」「悪気はなかった」という人が逮捕・送検されている現状が浮き彫りになっています。
■ そもそも密漁とは?
密漁とは、以下のような法律に違反して、魚介類や海藻などの水産資源を採る行為を指します。
| 主な法律 | 例となる違反行為 |
|---|---|
| 漁業法 | 他人の「漁業権」のある場所で勝手に採る |
| 水産資源保護法 | サケが川を遡上しているときに捕まえるなど |
| 漁業調整規則(都道府県ごと) | 禁漁期間中にウニを採る、大きさ制限を超えたハマグリを採る など |
つまり、「この魚をこの場所でこの時期に、この道具で採っていいのか?」がすべて細かく決められているのです。
密漁になりやすい!注意すべき魚介類・海藻
特に第一種共同漁業権の対象となっている水産物を無断で採ると、漁業権の侵害として処罰対象になります。以下は密漁として摘発されやすい例です。
よく摘発される対象例(一部)

| 種類 | 備考 |
|---|---|
| アサリ、ハマグリ | 潮干狩りの定番でも、場所と量によっては密漁に |
| ウニ、アワビ | 密漁の代表例、特に夜間の潜水は要注意 |
| マダコ、サザエ | 漁業権の対象である海域が多い |
| イセエビ | サイズや時期の制限あり |
| コンブ、ワカメ | 漁業権・保護区の対象に指定されやすい |
| シラスウナギ(ウナギの稚魚) | 密漁による高額取引が問題化 |
- 特にアワビ・ナマコ・シラスウナギは特定水産動植物に指定されていて、無断採取すると3年以下の懲役または3000万円以下の罰金に(時効:5年)
- 漁業権の侵害では100万円以下の罰金が科されます(時効:3年)
⚠️令和2年に法改正があり以前は20万円以下の罰金でしたが、密漁の深刻化により大幅に引き上げられました。
■ 漁業調整規則:各都道府県ごとのルール
密漁かどうかを判断する上で最も重要なのが、都道府県ごとの「漁業調整規則」です。
これは、国の漁業法に基づいて、各地の実情に合わせて以下のようなルールを定めています:
-
禁漁期間(例:ウニは5~8月採っちゃダメ)
-
採取方法の制限(素潜りOK・四つ手網NG など)
-
大きさや量の制限(例:マダイは20cm未満は採っちゃダメ)
-
漁具の制限(トローリングや撒き餌、ライト使用の禁止など)
✅ 一般的にOKとされやすい方法
-
竿釣り
-
手釣り
-
たも網
-
徒手採取(手で拾う)
❌ NGとされやすい方法
-
トローリング(船でひっぱる釣り)
-
四つ手網、投網など一気に大量に採れる道具
-
撒き餌を使う釣り(※都道府県によっては禁止)
-
夜間照明(火光)を使う漁
|
各都道府県の漁業調整規則はこちらから確認できます。水産庁HP |
■ 水産資源保護法では「サケの川上り採捕」などを禁止
水産資源保護法では、水産資源を守るための具体的な漁法禁止も定められています。
特に有名なのが「サケを川で捕ってはいけない」というルール。
これは、サケが産卵のために川をのぼる時期に採捕すると、次世代の個体が激減するためです。
また、爆発物・毒物を使って魚を獲るといった極端な行為ももちろん禁止。違反すれば懲役や罰金刑が科されます。
■ 密漁を避けるためには?
-
釣りや潮干狩りの前に、「その地域の漁協」や「県の水産課HP」で調べる
-
海産物のサイズ・量・時期を守る
-
「無料で誰でも採っていい場所」だと思い込まない(保護区域も多い)
密漁とは、悪意がなくても法律やルールを破った時点で成立します。
特に海辺や川でのレジャー時は、「何がOKで何がNGか」を事前に確認しておくことが大切です。
■通報はどうやって起きるのか?
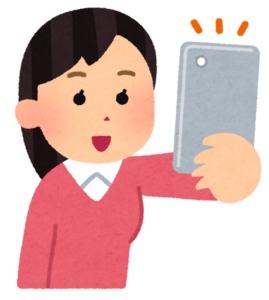
最近では、SNSに投稿した写真や動画が密漁発覚のきっかけになることが増えています。
たとえば、「大漁だった!」とアップした写真の中に、実は密漁禁止のアワビやサザエが写っていた…というようなケースです。投稿を見た人からの通報で発覚することも珍しくありません。
また、地元の住民や漁業関係者が、不審な採取行為を見かけて通報することもあります。海や川の近くでは、違法採取に対して目を光らせている人が多いのが実情です。
さらに、密漁が多発している地域では、警察や海上保安部のパトロールが強化されていることもあります。とくに夜間のアワビ密漁や、潜水器具を使った違法採取などは、重点的に取り締まりの対象となっています。
「バレなければ大丈夫」は通用しません。
今は、SNSや通報、そしてパトロールで、レジャー感覚の違法採取でもすぐに見つかる時代です。
■「釣れてしまったらすぐ返せばセーフ」は本当?
釣りをしていたら、たまたま密漁対象の魚介類が釣れてしまうこともあります。このような場合は、その場でただちに海に返せば「採捕」とはみなされない」こともあります。
ただし、次のような行為があれば密漁扱いになる可能性があります:
-
クーラーボックスやバケツに入れて持ち帰ろうとした
-
撮影やSNS投稿をした
-
死なせてしまった状態で海に戻した
このように、「返したから大丈夫」というのは必ずしも通用しないため、密漁対象になり得る生物はそもそも釣らない・採らない姿勢が大切です。
川・湖での釣りには「遊漁券」が必要!
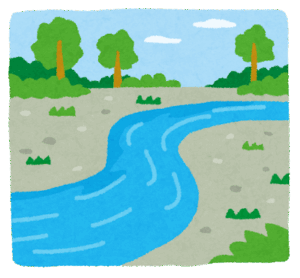
海釣りでは基本的に必要ありませんが、実は多くの川・湖では遊漁券が必要になります。
釣りの許可証のようなもので、買わずに釣るとルール違反になることもあります。
なぜ遊漁券が必要なの?
理由はシンプル。魚は“自然任せ”ではなく、漁協が管理・保護しているからです。
たとえば、以下のような魚たちは…
-
アユ
-
イワナ
-
ヤマメ
-
ニジマス
…実は、漁協(漁業協同組合)によって放流・養殖されていることが多く、自然任せで繁殖しているわけではありません。
つまり、こうした魚を釣るということは、漁協が育てた“資源”を利用することになるのです。
そのため、釣り人はその対価として遊漁券を購入する義務があります。
■ 遊漁券とは?どこで買えるの?
遊漁券は、漁協が管理している川・湖で釣りをする際に必要な「入場券」のようなものです。
1日券、年券など種類があり、金額は地域や漁協によって異なります。
現在では、以下の方法で購入できます:
-
コンビニ(一部地域)
-
釣具店
-
川の近くの売店・案内所
-
ネット(アプリやオンラインサービス)
スマホで買える!便利な遊漁券購入サービス
「どこで買えばいいか分からない…」という方は、次のような全国対応のオンラインサービスが便利です。
-
地域別に川や漁協を検索でき、スマホで遊漁券を購入
-
QRコード提示で現場チェックもスムーズ
-
サイト上で対象河川やエリアを選択して券を購入可能
-
コンビニ印刷にも対応
■ 必要かどうかは「河川名+遊漁券」で検索!
「この川って遊漁券必要?」と迷ったときは、川の名前で検索するのが最も確実です。
🔍 例:「多摩川 遊漁券」
「桂川 アユ 釣り 遊漁券」
「鬼怒川 フィッシュパス」
各河川には、管理している漁協があり、遊漁のルール(対象魚種・解禁期間・道具など)も明記されています。遊漁券を買ったから全てOKというわけではなく、○○cm以下の魚はとってはいけないなどのルールもあるので注意してください。
■ 遊漁券が不要な川もあるけど…
中には「遊漁券が不要な川」も存在します。ただし、そういった川では…
-
魚の数が少ない
-
サイズが小さい
-
放流されていないため釣れにくい
という傾向があり、あまり釣りには適していないことが多いです。
密漁で逮捕されたら?知っておきたい流れと対応方法

密漁の疑いで警察や海上保安庁に発見された場合、その場で現行犯逮捕されることもあります。
逮捕から送検までの一般的な流れ:
-
現行犯逮捕または後日逮捕
-
密漁中に見つかるか、SNSなどで発覚するケースも。
-
-
警察での取調べ(最大72時間)
-
供述や証拠の確認。黙秘権や弁護士接見の権利あり。
-
-
検察へ送致(送検)
-
原則48時間以内。重大な場合は勾留請求されることも。
-
-
起訴 or 不起訴の判断
-
悪質性・量・反省の有無などで決定。
-
密漁事件の特徴①:海上保安庁からの呼び出しがあることも
海岸や港湾、磯場などでの密漁は、警察ではなく「海上保安庁」が捜査主体となることが多いです。
たとえば:
-
船や磯場で密漁をしていた
-
潜水器具を使ってウニなどを採っていた
-
釣り中に規制対象のイセエビを持ち帰った
などの場合、後日、海上保安庁から「任意出頭の要請」が届くことがあります。
この段階では逮捕されていなくても、刑事事件としての捜査が進んでいる状態なので、油断せず適切に対応する必要があります。
密漁事件の特徴②:「在庁略式」となることもある
密漁事件では、検察官が略式命令(略式起訴)を選択するケースがあります。
特に「在庁略式」と呼ばれる形式で、
-
勾留せず在宅のまま
-
検察庁での呼び出しと略式命令
-
罰金刑(10万~50万円程度)が科される
といった流れで比較的短期間で処理されることもあります。
ただし、これも「前科がつく処分」であることに注意が必要です。
前科がつくと…
-
海外旅行やビザ取得に影響
-
資格職(教員・公務員など)への影響
-
転職時のトラブル
など、想像以上に生活への影響が大きいため、できるだけ不起訴や略式罰金で終わらせる努力が重要です。
密漁の処分は「悪質性」で大きく変わる
同じ密漁でも、「処分の重さ」は以下のような要素で大きく変わります:
-
採った量が多い/反復性がある → 悪質と判断されやすい
-
漁協とのトラブルや暴言 → 示談に影響
-
反省・賠償の意思 → 起訴猶予につながる可能性
したがって、早い段階から弁護士に相談し、誠意ある対応を主張していくことが非常に重要です。
密漁で捜査を受けたとき、早めに弁護士に相談すべき理由
密漁事件は、被害地の漁業協同組合(漁協)が刑事告訴を行うことで進行するケースがほとんどです。
✅ 弁護士に依頼するメリット:
-
漁協側に適切な謝罪・賠償の意思を示せる
-
「悪質性は低かったこと」を法的に主張可能
-
再犯防止策や反省の姿勢を明確に表明できる
-
起訴猶予や略式罰金での終結を目指せる
📌 特に重要なポイント:
漁協によっては「示談には一切応じない」という方針を取っているところもあります。
こうした場合でも、弁護士が交渉すれば、「刑事処分を軽くする材料」を集めることが可能です。
✅ まとめ:密漁での逮捕・呼び出しには冷静な対応を
「趣味の釣り」「ちょっとした潮干狩り」――そんな軽い気持ちでも、漁業権や漁業調整規則、水産資源保護法などに違反していれば、密漁として処罰の対象になります。実際に密漁で検挙される人の約9割は一般人であり、「知らなかった」「悪気はなかった」は通用しません。
海上保安庁や警察から呼び出しがあったり、在庁略式という形で略式罰金処分となることも多く、前科がつくリスクもあります。密漁事件は、漁協が被害者となって告訴する構造であるため、早期に弁護士に相談し、誠意を示すことで不起訴や軽微な処分にとどめられる可能性があります。
レジャー感覚の採取でも、法律違反であることに変わりはありません。もし捜査や呼び出しを受けたら、一人で判断せず、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談することが重要です。
|
▶ 密漁の呼び出し・逮捕・書類送検でお困りなら
刑事事件に強い弁護士へ、できるだけ早くご相談ください。
ご事情を丁寧に伺い、適切な対応をご提案します。