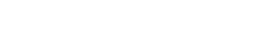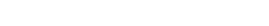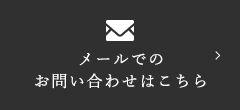2025/07/23 コラム
LINEストーカーはどこから?法律の境界線や罰則・示談の成立する可能性など徹底解説!

LINEでの執拗なメッセージ送信や通話、相手が嫌がっているにも関わらず連絡を続ける行為は、ストーカー規制法の対象となる可能性があります。「どこからがストーカー行為にあたるのか」「法的な処罰はあるのか」など、多くの方が疑問に感じているのではないでしょうか。
本記事では、LINEを使ったストーカー行為の法的な境界線、ストーカー規制法による罰則の内容、被害者との示談成立の可能性について詳しく解説します。被害者の立場から知っておくべき法的知識や対処法についても触れていきますので、ぜひ最後までお読みください。
ストーカーはどこから?法律が定める基準をわかりやすく解説!

「LINEストーカーがどこからなのか」という疑問に答えるには、ストーカー行為そのものの定義を理解しておく必要があります。そのためには、まず「ストーカー規制法(正式名称:ストーカー行為等の規制等に関する法律)」がどういった法律なのかを知っておくことが重要です。
ストーカー規制法は、国民の身体や生活の安全・平穏を守ることを目的とし、ストーカー行為を規制・処罰する法律です。この法律では「つきまとい等」と呼ばれる8種類の行為パターンを被害者やその家族に対し繰り返し行うことを禁止し、一定の目的で反復継続する場合「ストーカー行為」として厳しく規制しています。ここで詳しく見ていきましょう。
ストーカー規制法
ストーカー規制法では、ストーカー行為の対象を「特定の相手に対して、恋愛感情やそれが満たされないことから生じた怨恨の感情に基づき、同一人物に対して『つきまとい等』を繰り返し行うこと」と定めています。
つきまとい等とは、自宅や勤務先・学校での待ち伏せや押しかけ、無言電話や連続した連絡、SNSやメールでの執拗なメッセージ送信、相手やその親族への付きまとい、GPSを使った位置情報の監視、面会や交際の強要、名誉を傷つける発言や投稿、性的羞恥心を与えるような行為など、法律で定められた8つの行動パターンが該当します。これらの行動が反復して行われた場合、「ストーカー行為」として取り締まりの対象になります。
違反者には、後ほど詳述するように懲役刑や罰金刑などの刑事罰が科されます。また、警察や公安委員会は被害者の申し出があれば防犯対策や臨時の避難などの支援を行うこともでき、被害拡大の防止や早期解決のための体制が整えられています。
ストーカー規制法は、被害者の命や生活を守るための大切な法律です。被害に遭った場合は、LINEのやりとりやメッセージ、通話履歴などどこから被害にあっているのか証拠をきちんと残し、早めに警察へ相談することが何よりも重要です。
禁止されている「つきまとい」や「ストーカー行為」の基準
ストーカー規制法で禁止されている付きまとい等の行為はどこからなのか、もっと具体的に解説していきます。
たとえば、恋愛感情や怨恨感情などを満たすために被害者の住居や勤務先、学校付近での待ち伏せや押しかけ、尾行や見張り、不審にうろつくといった行動は、典型的です。また、帰宅直後に「おかえり」などとLINEやSNSで伝えたり、行動や服装を知らせて監視していることを示すような行為も含まれます。
面会や交際、復縁の強要、贈り物の受け取り要求のほか、大声を出す、家の前でクラクションを鳴らすなどの粗暴な言動もつきまとい行為に該当します。無言電話や拒否後の連続電話、しつこいメールやSNSメッセージ送信、汚物や動物の死骸を送りつける行為、名誉を傷つける内容を告げたり、インターネット等で広めたりする行為、わいせつな写真や言葉によって相手の性的羞恥心を害する行為も、すべて規制されている行為です。
こうした行為が反復して行われた場合の被害者の不安や恐怖は計りしれません。警察や専門家への相談は、ストーカー行為の抑止力となる可能性がありますので、ぜひ早めに検討してください。
SNS・GPS監視でストーカー認定される基準
近年、SNSやGPS機能を悪用したストーカー行為が社会問題となっています。ストーカー規制法では、SNSでの監視やしつこい連絡、GPSによる位置情報の追跡など、相手の同意なく繰り返し迷惑行為を行うことが処罰の対象となっています。
たとえば、相手から拒否されているにもかかわらず、SNSで執拗にメッセージを送り続けたり、友人の投稿にまで「○○さんは元気?」と頻繁にコメントしたり、偽アカウントから何度も友達申請を送る行為が該当します。
GPSを無断で取り付けて位置情報を取得したり、行動を把握して待ち伏せや偶然を装って接近する行為も厳しく規制されています。最近では、相手のスマートフォンに無断でアプリを仕入れて位置情報を取得するという手口もあるようです。
法的にストーカーと認定されるには「反復継続性」と「相手の明確な拒絶」が重要な要素となります。「どこから」というのは難しいですが、一度の行為ではなく相手が嫌がっているにも関わらず何度も続けることが、「ストーカー行為」として認定されるポイントです。
LINEのやりとりでどこからがストーカー扱い?

すでにお伝えしたように、普段使っているLINEも、相手が応答していないにも関わらず継続的にメッセージを送信したり、しつこく連絡を試みたりしている場合は、状況次第でストーカー規制法の対象となる恐れがあります。
特に恋愛関係にある方や別れた相手、友人関係において、どの程度のメッセージ交換が「過度」と認定され、どこからが法律問題に至るのかを把握しておくことは非常に大切です。
ここからは、LINEを使った迷惑行為の具体的な判定基準、実際に起こった事例、そして加害者になることを防ぐための対策について、法的根拠を交えながら分かりやすくお伝えしていきます。
短時間での大量メッセージと連投
LINEなどのコミュニケーションアプリで、短い時間内に大量のメッセージを一方的に送り続けられる「連続投稿」は、送られた側としては大きな負担や恐怖を感じることがあります。このような連続投稿は、内容にかかわらず多くのサービスでも問題視されており、実際に迷惑メールと同じような扱いを受ける可能性があります。
あなたが返信していないのに相手から短時間でメッセージが次々と届く場合、通知が埋め尽くされてしまい、大切な連絡を見逃してしまうことも考えられます。また、このような迷惑行為については運営側の自動検出システムが働き、加害者のアカウントが制限されたり停止されることもあります。
自分の安全や気持ちを守るためにも、連続した大量のメッセージ送信に困っている場合は、証拠としてメッセージを保存し、第三者や専門機関に相談することが大切です。LINE上でやり取りを続けるかどうかはあなた自身が決めるべきことですが、こちらが返信している状態では単なるやりとりとみなされ、ストーカー行為と認定されにくくなることもあります。
返信し続けてしまっている場合も、ストレスや不安を感じたときは、無理してコミュニケーションを続けず、「どこから苦痛に感じているのか」状況に応じて毅然とした対応やブロック、警察等への相談も視野に入れてください。
位置情報の要求・通話強要の監視行為
所在確認の要求・通話の強制による監視的行為は、恋人や友人が相手の行動を過剰に監視する行為を指します。具体的には、スマートフォンのGPS機能を利用した位置情報の継続的な確認、頻繁な通話の強制、メッセージへの返信を執拗に求める行為などが含まれます。
このような所在確認の要求・通話の強制による監視的行為は、被害を受ける方の心理的負担を著しく増大させます。常に監視されているという恐怖感や、自由な行動が妨げられる窮屈さから、うつ状態や不安症状を引き起こす危険性があります。
所在確認の要求・通話の強制による監視的行為を受けている場合は、まず信頼のおける方に相談することが大切です。専門の相談窓口やカウンセラーのサポートを受けながら、適切な距離感を維持することが問題解決への第一歩となります。
警察から警告が出された後の対処法を解説!

もしあなたが相手からのつきまといや迷惑行為について警察に相談し、加害者に対して警告が出された場合、その後の対応や流れを正しく把握しておくことが大切です。
警察による警告は、いきなり罰則を科すためのものではなく、「この行為は違法のおそれがあるためやめるように」と正式に注意するための措置です。しかしながら、この警告は今後のストーカー規制法にもとづく禁止命令や刑事処分につながる第一段階でもあるため、非常に重要な意味を持ちます。
警告を受けた加害者が行動を改める場合もありますが、逆にエスカレートするリスクもゼロではありません。警察が説明してくれた内容は、あなたの身を守るための根拠となりますので、不明点があれば遠慮なく確認し、不安な点は丁寧に質問しておきましょう。
また、警察からの対応の内容は、できる限り自分でも記録として残しておくことが重要です。口頭だけでなく書面で通知が交付された場合は、大切に保管してください。繰り返し似たような行為を受けた際には、前回の警告履歴が公安委員会による禁止命令の発出や、正式な刑事手続きのきっかけとなることがあります。
警告が出たあとの期間は、事件の分岐点となることもあります。再び不安を感じたり、行為が再発した場合は、すぐに記録を取りながら再度警察に相談してください。あなた自身の安全を最優先にしながら、適切な支援機関や法律の専門家とも連携して対応することが、安心した日常を取り戻す第一歩となります。
ストーカー規制法違反の罰則とは?

ここまで、どこからがストーカー規制法に該当するのかや実際にストーカー規制法に違反した場合どうなるのかについて解説しました。そこで気になるのが、「どれくらいの罰則を受けるのか」ということです。きちんと抑止力になる程の重い刑罰になるのでしょうか?
ストーカー規制法では、まず、禁止命令や接近禁止命令に違反した場合に科される罰則として、「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が定められています。これは禁止命令を受けた後、ストーカー行為にまでは至らないつきまとい等や、命令違反そのもの(反復なしまたは一部行為のみ等)の場合の罰則で、刑罰は比較的軽くなります。
警察や公安委員会による警告や禁止命令がなくても、ストーカー行為を反復継続して行った場合の罰則は、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科せられます。たとえば執拗なLINEや待ち伏せなどを繰り返した場合が該当します。
そして、禁止命令を受けたにもかかわらず再びストーカー行為を行った場合は、より重い「2年以下の懲役または200万円以下の罰金」が科されることになります。つまり、禁止命令が出ていれば、LINEを執拗に送ることや待ち伏せ等も重い罪になってしまうのです。
このように、法令違反の内容や命令違反の有無、行為の悪質性によって、刑事罰の重さは段階的に引き上げられています。もし被害に遭われた際は、所轄署への届出と同時に、メールやLINEの保存や写真撮影といった証拠収集を心がけることをお勧めします。
被害者との示談はできる?

和解による解決というのは、関係者同士が話し合いを通じて問題を収束させる手段として一般的に認識されておりますが、どのような条件が整えば成立するのか、また具体的な手続きの流れについて適切に把握されている人は決して多くないといえるでしょう。
ここからは、相手方との和解協議が実現できるシチュエーションや気をつけるべき事項、協議を円滑に進めるためのアプローチ方法について丁寧にお話しさせていただきます。和解という選択肢をお考えの皆様に必ず押さえていただきたい大切な要素を、わかりやすい形でお伝えいたしますので、どうぞお役立てください。
示談金の相場と注意点
ストーカー規制法違反事件における示談金の相場は、一般的に30万円から200万円程度と幅があります。金額は「精神的苦痛に対する慰謝料」が中心となり、加えて被害の程度やストーカー行為の悪質さ、禁止命令違反の有無、被害がどこから続いたかどうか、そして被害者の生活や健康への影響の大きさなどが考慮されます。
ストーカー事件の示談は、交通事故などの損害賠償事件と異なり、加害者と被害者が直接やり取りを行うことは厳禁です。加害者側の弁護士を通じて警察や担当窓口経由で進めるのが原則であり、交渉内容や示談書面にも専門的な知識が求められます。
また、過去の交友関係で生じていたトラブルも示談の対象になりやすいため、被害内容についてしっかり整理して代理人や支援機関に伝えることが重要です。示談交渉のなかで金額が高くなるケースとしては、行為が長期間にわたり執拗だった場合や禁止命令違反が伴う場合、被害者が重度の精神的疾患を患った場合などが挙げられます。
示談成立後は原則として追加請求ができないため、示談内容や金額について慎重な検討が必要です。不安や疑問があれば、必ず弁護士や警察、公的な相談機関に相談してください。
示談の交渉は成立する?
ストーカー行為などの刑事事件における示談は、法律上可能な場合がありますが、被害者の意思が何よりも尊重されます。特に、ストーカー規制法違反のように被害者が強い不安や恐怖を抱えている事案では、示談そのものを望まないケースも多く、必ずしも成立するとは限りません。
加害者側に弁護士が就いている場合は、警察や検察経由で被害者の意思が確認され、被害者側にも示談金や内容を検討する機会が設けられる場合があります。また、成立する場合でも、精神的苦痛に対する適正な損害賠償額や、今後一切接触しない旨の誓約などが示談書に明示される必要があります。内容に不安があれば、被害者側も弁護士や支援団体を通じて慎重に判断することが大切です。
示談書には、誓約違反があった場合の責任や再発防止策などを明記し、将来的なトラブルを避ける工夫が欠かせません。裁判に比べて時間や手続きの負担が少ないという利点もありますが、被害者の安全と安心を最優先に考え、必要な支援を受けながら判断することが最も重要です。
LINEブロックとプライバシー設定
LINEのブロック機能とプライバシー設定は、快適なコミュニケーション環境を維持するために重要な機能です。LINEでユーザーをブロックすると、相手からのメッセージや通話を完全に遮断できます。
ブロックされた相手は、あなたがオンラインかどうかを確認できなくなり、メッセージの既読表示も表示されません。LINEのプライバシー設定では、友だち追加の許可設定、タイムラインの公開範囲、電話番号・ID検索の制限、位置情報の共有設定など、様々な項目を細かく調整できます。
これらの設定を適切に管理することで、個人情報の保護とプライバシーの確保が可能になります。不要な連絡を避けるため、知らない人からの友だち追加を制限し、必要に応じてブロック機能を活用しましょう。
また、定期的にプライバシー設定を見直すことで、安全なLINE利用が可能になります。適切なLINEブロックとプライバシー設定により、ストレスフリーなコミュニケーションを実現できます。
証拠スクショ・相談の進め方
トラブルや問題を相談する際、証拠スクショは状況を正確に伝える重要なツールです。文字だけでは伝わりにくい詳細な情報を視覚的に示すことで、相談相手の理解を深め、適切なアドバイスを受けやすくなります。相談を成功させるためには、まず事前準備を徹底することが重要です。
相談前に関連する画面のスクリーンショットを複数枚撮影し、「エラーメッセージ」「設定画面」「遣り取りの状況」などを時系列順に整理し、どこからが問題か確認しましょう。証拠スクショの撮影では、問題発生の瞬間を逃さずキャプチャすることが大切です。
また、日時が分かるように画面全体を撮影し、個人情報については事前にモザイク処理を実施しておくことで、安心して相談できます。相談時は、証拠スクショと併せて問題の経緯を時系列で説明することが効果的です。
「いつ・どこで・何が」を明確にし、スクショ番号を振って順序立てて説明することで、相談相手が状況を把握しやすくなります。証拠スクショを活用した相談は、問題解決への近道となります。
LINEストーカーと疑われない方法を解説!

LINEは便利なコミュニケーションツールですが、使い方を間違えるとストーカー行為と判断されてしまう危険性があります。疑われないためにも、LINEの使い方については十分気をつけましょう。
メッセージ頻度
LINEを安心して使うためには、相手とのやりとりに違和感や不安を感じた時点で、自分自身の気持ちや安全を最優先に考えることが大切です。返信していないにもかかわらず何度もメッセージが届いたり、短時間に大量の連絡を受けると、とても強いプレッシャーや不安を感じるものです。
このような連投は、たとえ内容が一見普通の会話であっても、気づかないうちにストーカー行為とみなされる場合があります。自分の気持ちを尊重し、返信する気がないときや負担に感じたときは、無理に応じる必要はありません。
返事がないにもかかわらず連絡が続く、内容が徐々に執拗になったり、感情やトーンが変わる場合は、相手とのやりとりを控えたり、ブロックや通知オフ、プライバシー設定の見直しを行ってください。
不快なやりとりが増えたときや、身の危険を感じたときは、メッセージの内容や時間帯、頻度を証拠として保存し、信頼できる人や警察、専門窓口に早めに相談することが、自分の安心と安全を守る第一歩です。LINEを安全に使い続けるためにも、無理をせず、あなた自身の感覚と境界線を大切にしましょう。
誤解されない連絡のタイミング
LINEを通じて頻繁に連絡が来るだけでなく、その「時間帯」や「状況」が配慮されていない場合、受け取る側にとっては大きなストレスになります。たとえば早朝や深夜などに繰り返しメッセージが届いたり、自分が学校や仕事で対応できない時間に何度も着信音が鳴るような場合、こちらの都合を無視されたストレスだけでなく、恐怖すら感じることがあります。
特に、こちらが返信していないにもかかわらず一方的に連絡が増えている時や、内容が「なぜ返信しないのか」といった詰問調に変わってくる場合は要注意です。相手が「緊急だと思った」「気になって」と善意を装っていても、受け取り手が不安や負担に感じている時点でコミュニケーションは破綻しています。
安心できる関係なら、相手にも生活やタイミングがあることを互いに尊重するはずです。もし、一方的な時間帯での連絡が繰り返され、精神的につらいと感じたなら、それはすでにあなたの心のサインです。無理に応じたりせず、履歴は証拠として保存し、信頼できる人や専門機関に早めに相談するようにしましょう。
ストーカーについてのご相談は須賀法律事務所へ

ストーカー行為とは、執拗な付きまとい行為やLINEなどのSNS上での繰り返し投稿など、相手の日常生活を脅かす行為です。これらは「迷惑防止条例違反」や「ストーカー規制法」により重い刑事罰の対象となります。
しかし、ストーカー行為というものがどこから該当するのか難しい点もありますよね。被害者にとって精神的苦痛は計り知れず、放置すれば更なる深刻な事態を招く危険性があります。ストーカー事案は時間の経過とともに急速に悪化する特徴があります。
加害者の逮捕前に専門弁護士へ相談することで、示談交渉や警察との効果的な連携を通じて事態の早期収束を図ることができます。須賀法律事務所では「もっと早く相談していれば」という後悔を防ぐため、迅速な初期対応を何よりも重視しています。
来所の必要がないオンライン相談体制により、危険を感じた瞬間から弁護士が即座に対応を開始します。電話やチャットでの相談から全工程をオンラインで完結できるため、安全で確実な法的保護を受けることが可能です。
ストーカー被害は刑事事件に留まらず、職場での人間関係悪化や家族への影響など、生活全般に及ぶ問題を引き起こします。当事務所では各分野の専門弁護士が連携し、労働問題から離婚相談まで、被害者の生活再建を総合的にサポートいたしますのでまずはご相談ください。
須賀法律事務所についてはこちらをご覧ください。
当事務所では、軽犯罪法に関する法律相談を受け付けております。
お気軽にお電話またはLINEにてお問い合わせください。