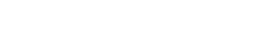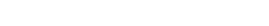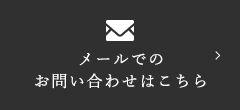2025/07/30 コラム
【虚偽自白】やってないのに「やった」と言ってしまった…取り調べで嘘の自白をしたときの対処法
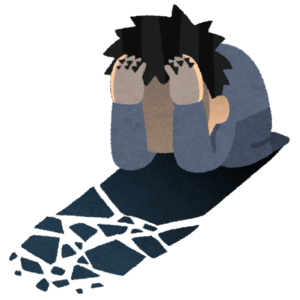
「やっていないのに、つい“やった”と言ってしまった」──取り調べでの“虚偽自白”は、決して珍しい話ではありません。
長時間にわたる取り調べ、精神的なプレッシャー、疲労や不安、そして「もう帰してほしい」という気持ち…。そうした状況下で、「やってないことでも認めれば今の苦しみから解放される」と思い込み、自白してしまうケースは少なくありません。
特に記憶が曖昧だと警察の話をそのまま受け入れてしまい、次第に自分でも「そうだったのかもしれない」と錯覚して、
-
「そうだったかもしれません」
-
「記憶はあいまいですが、たぶん…」
こうした発言は、取り調べ官に都合よく切り取られ、「自白した」とされる原因になります。
この記事では、虚偽自白が起きる原因とその危険性、そして「言ってしまった後にどうすればいいのか」という対処法を、弁護士の視点からわかりやすく解説します。
長時間の取り調べや心理的圧力
取り調べは1日数時間に及び、数日、場合によっては数週間にわたって繰り返されます。その間、自由を奪われた密室で、捜査官と1対1で対峙し続けることになります。
はじめのうちは「自分はやっていない」と訴え続ける人も、次第に否認がまったく通じない現実に直面します。
「何を言っても聞いてもらえない」──その無力感に、次第に心が折れていくのです。
先が見えない苦しさが判断を狂わせる
取り調べがいつ終わるのかも分からない。「この苦しみがあと何日続くのか」すら見通せない状況は、被疑者の心を確実に蝕んでいきます。
そして、捜査官からこう告げられることがあります。
「否認しているといつまでも終わらないよ」
「認めればすぐ帰れる可能性もある」
「裁判で否認するとかえって刑が重くなることもあるよ」
こうして、否認のデメリットばかりを強調されることで、「自白した方が得策かもしれない」という錯覚に陥ってしまうのです。
対決に疲れ、迎合してしまう心理
取調官との対峙は、精神的に強い緊張を伴います。
厳しく詰められるだけでなく、時には「君のことを理解している」「正直になった方がいい」といった温情ある態度が交じることもあります。
このような心理的な揺さぶりにより、疲れ切った被疑者は「もうどうにでもなれ」という迎合的な気持ちになりがちです。
最初は否認していた人が、徐々に曖昧な発言をし始め、
-
「そうだったかもしれません」
-
「記憶はあいまいですが、たぶん…」
と口にした瞬間、それが“供述の核心”として記録に残ることになります。
「今だけ耐えれば終わる」は危険な思い込み
虚偽の自白をしてしまう大きな理由のひとつに、「今を乗り越えれば終わる」という心理的な逃避があります。
・早く帰りたい
・疲れていて考える余裕がない
・強く否定するとさらに追及されそうで怖い
──こうした状況の中で、「とりあえず認めておこう」と考えてしまうのです。
しかし、それは一時的な安心であって、その後に待っているのは起訴や裁判、そして前科という現実です。
身代わり出頭という深刻なケースも
まれに「家族や恋人の代わりに自分がやったと言った」という“身代わり出頭”のケースも存在します。
これは一見すると“優しさ”や“守りたい気持ち”に見えますが、法的には重大な虚偽の供述であり、別の罪に問われる可能性もあります。
違法な取り調べとは?
「取り調べで認めてしまったけど、本当はやっていない」
そんな虚偽自白が、裁判で問題になるケースは少なくありません。
刑事訴訟法319条は、「任意にされたものでない自白は、証拠として用いることができない」と明記しています。つまり、違法な取り調べで得られた自白は、そもそも証拠として認められない可能性があるのです。
違法とされる手続きとは?
以下のような取り調べが行われた場合、自白は「違法」と判断されるおそれがあります。
- 暴言・心理的圧力
「反省している奴が黙秘なんてしないんだ」などの暴言で自白を迫る
「否認すると家族も調べる」「出られなくなるぞ」などの脅し文句
- 長時間の拘束や取り調べ
1日何時間にもわたり、休憩もなく続く取り調べ
拘束期間を引き延ばし、疲労・混乱のなかで虚偽の供述を誘導
※一般的には、1日8時間以内が基本で、午前5時から午後10時までの間に行われることが多いです。ただし、特別な許可がある場合や、逮捕直後の緊急性が高い場合には、深夜に及ぶこともあります。
- 黙秘権の侵害
黙秘権を告げずに取り調べを行う
黙っていることを責め立て、「話さないなら不利になる」と誤認させる
- 利益誘導・偽計による供述
「認めたらすぐに釈放される」といった虚偽の約束
「他の人はもう認めている」などのウソで心理的に追い詰める
- 違法な証拠収集をもとにした自白
令状なしの家宅捜索・押収
違法に得た証拠を見せて「お前の犯行だ」と断定し自白を迫る
- 弁護士との接見を妨害
弁護士と会う機会を与えない
接見の時間や回数を制限する
取調べの録音・録画(可視化)制度
2019年の刑事訴訟法改正により、裁判員裁判対象事件や検察官の独自捜査事件では、取調べの全過程を録音・録画(可視化)することが義務化されました。
これにより、違法な取調べの有無を客観的に検証できる環境が整い、供述の任意性や信頼性が高まっています。
しかし、この制度はまだすべての事件や取り調べに適用されているわけではありません。
対象が限定されており、軽微な事件や警察主導の捜査では可視化されないケースも多いため、録音・録画がない場合は特に慎重な検証が必要です。
裁判で違法性が認められれば、自白は排除される
上記のような違法行為があったと証明できれば、自白の任意性が否定され、調書が証拠として認められない可能性があります。
実際、過去の裁判例でも、
-
「長時間の取り調べで判断力が低下していた」
-
「虚偽の情報で心理的圧力をかけられた」
と認定され、自白が排除されたケースは少なくありません。
【実例】袴田事件──虚偽自白とずさんな証拠で死刑判決
1966年、静岡県で発生した袴田事件は、「虚偽自白」の危険性を象徴する日本の冤罪事件のひとつです。
一家4人が殺害され、元プロボクサーの袴田巌さんが犯人として逮捕・起訴されました。根拠は彼の「自白」でした。
しかしその後の再審では、次のような重大な問題が明らかになりました:
-
取り調べの誘導で作られた自白だった
-
血の付いた衣類が事件から1年以上経って“突然”見つかる
-
血痕の状態などから「証拠が捏造された疑い」が指摘される
最終的に、再審で自白の信用性は否定され、2023年に無罪判決が確定。
この事件は、自白がいかに危ういものであるかを日本中に知らしめた重要な判例となりました。
自白の撤回は簡単ではない
自白を裁判所が「信用できない」と判断するには、厳しいハードルがあります。
-
供述調書には署名・押印があり、裁判所はそれを「意思表示の証拠」として重視する
-
「なぜ撤回したのか」「どんな状況で自白したのか」を合理的に説明しなければならない
-
単に「やっぱり違った」と言うだけでは、信頼を得られない
撤回するなら、「誤った自白だった理由」を明確にし、状況証拠や心理的背景まで含めて戦略的に主張する必要があります。
💡 「撤回=無罪」ではなく、「なぜ誤ったのか」「どんな取調べだったのか」を丁寧に伝える姿勢が、冤罪回避への第一歩です。
嘘の自白をしてしまったときの対処法

虚偽の自白をしてしまったと気づいたとき、大切なのは「できるだけ早く正しい対応を取ること」です。一度の自白であっても、供述調書として記録に残れば、裁判で極めて大きな影響を及ぼします。ここでは、冤罪を避けるために取るべき具体的なステップを解説します。
できるだけ早く弁護士に相談を⚖️
自白後の対応は、今後の処分や裁判の結果を左右します。弁護士に早期に相談することが何よりも重要です。
弁護士は以下のような対応をサポートできます:
-
自白の撤回に向けた弁護方針の立案
-
取り調べの違法性があったかの検討
-
他の証拠との整合性を整理し、裁判で反論材料にする
特に、弁護士との面会は、取調べに一人で臨む精神的負担を大きく減らし、適切な判断を助けます。
取り調べの内容は、できる限り記録する📝
虚偽の自白をしてしまった背景には、警察官からの心理的圧力や長時間の取調べがあったケースも多くあります。
取り調べのやりとりや、そのときの精神状態などを「できるだけ早く」「できるだけ詳しく」メモしておくことが重要です。
-
どんなことを聞かれたか
-
どのように誘導されたか
-
自分がどう答えたか、その理由
記憶が新しいうちに記録しておくことで、後の弁護活動や裁判で「なぜ嘘の自白をしてしまったのか」を説明する大きな材料になります。
自白の撤回は「戦略的」に進める必要がある
「やっぱりやっていません」とただ言い直すだけでは、撤回は通りません。撤回を裁判所に認めさせるには、
-
自白が虚偽である合理的な説明
-
取り調べが違法だった事情(長時間、脅迫的な言動など)
-
他の客観的証拠との矛盾
などを、筋道立てて示す必要があります。このためにも、弁護士と綿密な準備を進めていくことが欠かせません。
「虚偽の自白をしてしまった」と申し出るタイミングが重要
自白を撤回する際は、その「タイミング」も大きく影響します。たとえば
-
起訴前:警察・検察段階での撤回は、処分(起訴・不起訴)に影響を与える可能性があります
-
起訴後:裁判での主張となるため、証拠との矛盾を整理した上で提出する必要があります
💡 できる限り早い段階で申し出ることが有利です。
また、撤回が遅れるほど「証言が変わった」として信用性に疑問を持たれるリスクが高まります。
「もう手遅れかも…」と思わず、まずは信頼できる弁護士に相談しましょう。
冷静に、かつ戦略的に対応することで、被疑者本人の権利と人生を守ることができます。
虚偽自白を防ぐために

取り調べ前に知っておきたい「自分の権利」
虚偽の自白を防ぐうえで最も重要なのは、取り調べ前から「自分の権利」を理解しておくことです。刑事手続きにおいて、誰にでも保障されている権利として以下のようなものがあります。
-
黙秘権:話したくないことは話さなくてよい。これを理由に不利な扱いをされることはない。
-
弁護士選任権:取り調べ前でも、弁護士に相談することができる。依頼すれば国選弁護人がつくことも。
特に初めて捜査対象となった人は、「何か言わないといけない」と思い込んでしまいがちですが、無理に話さないことが“自分を守る”正しい選択になる場面は多くあります。
家族や支援者にできること
本人が取り調べを受けている間、家族や支援者が取れる行動は想像以上に大きな意味を持ちます。
-
できるだけ早く弁護士に連絡し、接見を依頼する
-
本人の性格、病歴、精神状態などを説明し、適切な配慮を求める
-
冤罪が疑われる場合には、取調べの違法性について意見書を提出する
取調べの場に入れなくても、外からできる支援は多くあります。大切なのは「一人で抱え込ませないこと」です。
嘘の自白をしてしまったら、一人で悩まず相談を
突然疑われ、取調室に呼ばれたとき、冷静に判断できる人はそう多くありません。
ましてや、長時間の取り調べや精神的な圧力の中で、「とにかく今の苦しみから解放されたい」と思い、「やっていないのに“やった”と言ってしまう」ことは、誰にでも起こり得ることです。
しかし、自白してしまったからといって、すべてが終わるわけではありません。
適切なタイミングでの撤回、証拠や供述の見直し、そして何よりも信頼できる弁護士のサポートがあれば、冤罪を防げる可能性は十分にあります。
警察も決して、冤罪を作ろうとしているわけではありません。むしろ多くの警察官は、強い責任感と正義感を持って事件に向き合っています。
ただし、真面目な警察官ほど、「この人が犯人に違いない」と確信してしまい、他の可能性が見えにくくなることがあります。
その結果、供述を誘導してしまったり、「〜だよな」といった言葉で被疑者が迎合してしまう――そんなことも現実に起こり得るのです。
だからこそ、一人で抱え込まず、少しでも不安を感じたら、すぐに弁護士に相談してください。
虚偽自白から抜け出すには、「いま、どう動くか」が大切です。弁護士は、あなたが本当の声を取り戻すための一番の味方です。