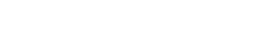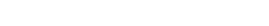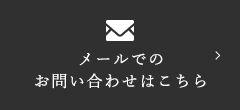2025/05/26 コラム
ガードレールに接触して通報しなかったら?保険・点数・損害賠償のリスクと弁護士のサポート内容を解説

事故を起こしたあと、「怖くなってそのまま帰ってきてしまった」「パニックでどうしていいかわからず通報しなかった」――そんな後悔を抱えて、1人で不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
「ガードレールに軽く接触したけど、人身じゃないし…」「面倒だから通報しなくていいかな」──そんなふうに判断して、そのまま帰宅してしまった方もいるかもしれません。
しかし、物損事故とはいえ、警察に通報しなかったことで後から大きなトラブルに発展するケースは少なくありません。
たとえば、事故証明がなく保険が使えない、道路管理者から修理費を請求される、通報義務違反で違反点数がつくといった事態です。
本記事では、ガードレールに接触したのに警察に通報しなかった場合にどのようなリスクがあるのか、そして弁護士に相談することでどんなサポートが受けられるのかをわかりやすく解説します。
今まさに不安を感じている方に向けて、適切な対応方法をお伝えします。
|
【目次】 |
【警察に通報しなかったらどうなる?通報義務違反と違反点数】
事故の後に警察へ報告する義務は、道路交通法第72条で定められています。
たとえ物損事故でも、通報しないと「事故報告義務違反」にあたるのです。
違反とみなされた場合には、以下のような行政処分が科されます。
|
これだけなら「軽い処分」と思うかもしれませんが、問題はそれだけではありません。
公共物を壊して通報しないと「当て逃げ」扱いも?
ガードレールや道路標識などの設備は、市区町村や国などの公共物です。これを破損し、通報もせずにそのまま現場を離れた場合、状況次第では以下のような評価をされるリスクがあります。
-
「当て逃げ」「事故隠し」と判断される
-
悪質と見なされ、行政処分や刑事責任が重くなる可能性も
実際、自治体やNEXCOが破損を発見した後、
-
ドライブレコーダー映像の確認
-
防犯カメラのチェックや目撃者情報の収集
-
塗料の色や破片などからナンバーを特定
といった手段で、あとから加害車両が特定されるケースが増えています。
さらにこんなリスクも…
通報をしなかった場合、次のようなトラブルが起こることもあります。
|
「通報しておけばよかった…」という事態になる前に、もし「通報していなかったかも」「対応に迷っている」という方は、できるだけ早めに正しい対処をとることが大切です。それが、保険トラブルや不要な処分を防ぐ最善策となります。
【事故証明がなければ保険が使えない?】
前の章でお伝えしたように、物損事故で警察に通報しなかった場合は「報告義務違反」に問われる可能性があります。
しかし、それだけではありません。もっと現実的で深刻なのが“お金の問題”です。
保険会社は「事故証明」を重視している
自動車保険(特に対物賠償保険)を使って損害を補償してもらうには、通常、「事故証明書」が必要になります。
事故証明は、警察に連絡して事故として受理されたときにしか発行されません。
つまり、通報していなかった場合は事故証明が出ず、保険金の支払い対象外になることがあるのです。
通報していないと、こんな損失が…
たとえば、ガードレールを破損したとき、警察に通報していなければ保険が使えず、以下のような経済的リスクが生じます。
|
保険会社に相談しても、「事故証明がないので補償できません」と即座に断られるケースも少なくありません。
証明がなければ「事故そのものがなかった」扱いになることも
保険会社が事故の存在を確認できなければ、そもそも「保険契約の対象となる事故が発生したかどうか不明」とされてしまうことがあります。
-
「事故証明がない」
-
「現場写真もない」
-
「相手方との連絡履歴もない」
こうなると、たとえ被害が出ていても、保険対応が一切進まない可能性があるのです。
「少しこすっただけだから」「面倒なことにはしたくない」と通報を省いたことが、
数万円~十数万円という思わぬ出費に直結するリスクがあることを、ぜひ知っておいてください。
【損害賠償はどこから請求される?】
ガードレールやフェンス、標識などに接触して壊してしまった場合、警察に通報しなかったとしても、後日損害賠償の請求が届くことがあります。そして、その請求元は「壊した相手」によって異なります。
公共物を壊した場合
接触の対象が道路のガードレールや標識、街灯などの公共設備だった場合、所有しているのは次のような機関です。
-
市区町村(市道や生活道路など)
-
都道府県(県道など)
-
国(国道や公共インフラの一部)
-
NEXCO(高速道路の施設など)
これらはすべて「公物(こうぶつ)」とされており、破損が発見されると管理者側で調査が行われます。
-
ドライブレコーダーや防犯カメラの映像
-
ガードレールに付着した塗料や破片の照合
-
目撃者情報や警察との連携
こうした手段で、後から加害車両を特定されるケースも少なくありません。
請求内容としては、以下のようなものが一般的です。
|
個人所有物を壊した場合
たとえば以下のようなケースでは、損害賠償の請求元は「個人または法人」となります。
-
一戸建ての塀やフェンスに接触
-
店舗駐車場のポールや看板を破損
-
アパートの壁や駐車場ブロックをこすった場合 など
このような場合、所有者本人や管理会社から直接連絡が来たり、内容証明郵便で請求されることがあります。
公共物と異なり、金額の設定に幅があるため、トラブルになることも珍しくありません。また、「相手が感情的になっている」「高すぎる修理費を提示されている」といった相談もよくあります。
公共物・私有物にかかわらず、物を壊して通報しなかった場合、あとから高額の請求が届く可能性があることをしっかり認識しておく必要があります。
早めの対応が、損害やトラブルの拡大を防ぐ第一歩です。
【事故後に通報しなかった…その後の適切な対処法】
「ガードレールにぶつけたけど、パニックになって通報せずに帰ってきてしまった…」
「今さら警察に連絡しても大丈夫?」
そう悩んでこの記事にたどり着いた方もいるかもしれません。
ですが、ご安心ください。
たとえ事故当日に通報していなくても、今からできる対応があります。
今からでも通報・自己申告はできる
事故の発生から時間が経っていたとしても、まずやるべきことは、自分から警察に連絡して状況を説明することです。
|
すでに通報せず現場を離れたという事実は変えられませんが、誠実な対応を取ることで、悪質な「当て逃げ」とは区別される可能性があります。これは、その後の処分や損害賠償の交渉で大きな意味を持ちます。
放置はNG!あとから発覚するケースも
「連絡がない=バレていない」と思って放置するのは危険です。
-
管理者が破損に気づいて調査する
-
防犯カメラやドラレコ映像が確認される
-
ガードレールの塗料・破片からナンバーが特定される
こうした流れで、数日~数週間後に「突然連絡が来る」ケースは現実にあります。
このとき、すでに通報していないことが問題視され、処分が重くなることもあります。
記録や証拠を残しておく
後から事故を説明するときに備えて、次のような情報を整理しておくと安心です。
-
接触した場所の写真や周囲の状況
-
車両の損傷箇所(スマホで撮っておく)
-
日時や当時の道路状況のメモ
-
同乗者がいれば証言をメモ
こうした記録があることで、後日の説明や保険対応がスムーズになります。
「今さら連絡しても意味がない」と思うかもしれませんが、何もしないことが最悪の選択肢です。
まずは、できることから落ち着いて対応していきましょう。

弁護士に相談すべきタイミングと理由
「何をどう説明すればいいか分からない」
「損害賠償を求められているが、対応できるか不安」
そんなときは、できるだけ早めに弁護士に相談することをおすすめします。
特に以下のような状況では、一人で対応するより弁護士を介した方がスムーズで確実です。
|
弁護士ができること
弁護士に依頼することで、以下のようなサポートが受けられます。
-
現在の状況を整理し、リスクを冷静に分析
-
警察への申告内容についての助言や文面作成のサポート
(言い方ひとつで印象が変わるため、特に重要) -
保険会社への説明補助、必要に応じて交渉も代理
(事故証明がなくても他の証拠で立証できる場合あり) -
自治体・道路管理者からの請求額の妥当性チェックと減額交渉
-
相手方とのやり取りをすべて代理し、示談書や内容証明を作成
-
裁判になった場合の全面的な代理人対応(必要な場合のみ)
「自分で対応しようとしてさらにこじれてしまった」
「最初に謝ってしまって不利な立場にされた」
というご相談も少なくありません。
通報しなかった事実は変えられなくても、これからの対応は変えられます。
法律の専門家に早めに相談することで、金銭的・精神的な負担を大きく減らせる可能性があります。
【まとめ:通報と誠実な対応がトラブル回避のカギ】
「少しぶつけただけ」「人にケガをさせたわけじゃない」
そう考えて、警察への通報をせずにその場を離れてしまう方は少なくありません。
しかし実際には、通報をしなかったことで、保険が使えなくなったり、損害賠償を全額請求されたり、違反点数が加算されたりと、大きな不利益につながるケースが多くあります。
特にガードレールや標識などの公共物は、後から必ず発覚する可能性があるものです。
「誰にも見られていない」と思っていても、ドライブレコーダーや監視カメラで記録されていることも珍しくありません。
大切なのは、通報しなかったことを悔やむのではなく、今から誠実に対応することです。
状況が複雑になっている場合や、対応に不安がある場合は、早めに弁護士に相談して、客観的な視点で助言を受けることをおすすめします。
トラブルを最小限に抑えるためにも、「知らなかった」で済ませず、冷静に、正しく対処していきましょう。
当事務所では、初回相談無料で法律相談を受け付けております。
お気軽にお電話またはLINEにてお問い合わせください。