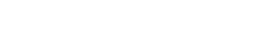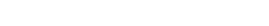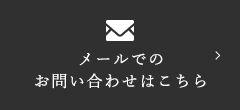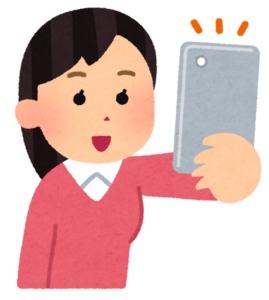2025/05/04 コラム
子どもが加害者にならないために!家庭で教えるべき法律と日常の防犯対策を弁護士が紹介します

「うちの子に限って」「そんな大げさなこと…」と思っていませんか?
しかし、弁護士として数々のトラブルを見てきた経験から言えるのは、「悪気はなかった」「みんなやってるから・・」が原因で、子どもが“加害者”になってしまったり、犯罪に巻き込まれるケースがとても多いということです。
スマホやSNSの普及で、簡単に他人の情報を拡散できる時代。何気ない一言、遊び感覚の行動が、名誉毀損や脅迫、わいせつ行為などの犯罪に問われることもあります。
だからこそ、加害者にも被害者にもならないために「家庭で法律と防犯意識を教えること」が重要なのです。このコラムでは、子どもがやってしまいがちな行動と、それが法律的にどう見なされるのかを弁護士の視点で解説し、家庭での予防策をご紹介します。
学校・友達との関係で気をつけたい法律
■ 「ふざけ」が暴行罪や脅迫罪になる?
友達をからかったり、軽く押したりする場面は、日常によくある光景です。しかし、これが度を越すと「暴行罪」や「脅迫罪」に問われることがあります。
たとえば:
-
叩くまではいかなくても、物を投げる、威圧するなどの行為が暴行罪の対象に
-
「殺すぞ」「学校に来んな」などの発言が、脅迫罪に該当するケースもあります
最近では、LINEグループでの無視や悪口がいじめにつながり、学校側から警察へ通報される例も見られます。
■ SNSでの投稿が「侮辱罪」や「名誉毀損」に?
-
他人の顔写真を勝手にアップロード
-
「○○って本当にバカ」「キモい」などの書き込み
これらが侮辱罪や名誉毀損罪になる可能性があります。
未成年でも刑事処分(補導・児童相談所送致など)の対象になることがあり、将来に大きな影響を及ぼすこともあります。
■ 家庭でできる防止策
-
「どんな言葉でも、相手の立場になって考える」習慣を育てる
-
SNS投稿は“誰が見ても問題ないか”を一度立ち止まって確認させる
-
ふざけて動画を撮る行為の危険性を、事例と一緒に説明する
|
事例:友達を押して転ばせ、笑いながら撮影→ 傷害罪で書類送検 男子生徒らが、廊下で友人を後ろから押して転ばせる様子を動画で撮影。 「ドッキリ動画」としてTikTokに投稿したところ、動画を見た学校関係者が通報。被害生徒は転倒時に手首を骨折しており、撮影者と加害者は共に傷害罪容疑で書類送検されました。 【解説】
|
性に関するトラブルから子どもを守るために
■ 「好きだから触った」は言い訳にならない
交際や好意を表現する中でスキンシップが増えることがあります。
しかし、相手の同意がない接触は、たとえ未遂でも不同意わいせつ罪などの犯罪になり得ます。
たとえば:
-
教室で「じゃれ合い」として肩を抱く、手を握る
-
好きな子に後ろから抱きつく
-
相手が嫌がっているのにやめない
これらの行為が、警察に通報されるケースもあります。
特に、男子→女子の行為は性加害として扱われやすく、親の知らない間に「加害者」になっていることも。
■ メッセージのやり取りでも条例違反になることがある
未成年同士の交際でも、性的なメッセージや画像のやり取りは注意が必要です。
特に多いのが「軽い気持ちで送った写真が他人に流出」するケース。
これは、以下の法律に抵触する可能性があります:
-
青少年健全育成条例(淫行等の禁止)
-
児童ポルノ禁止法(提供・所持・拡散)
-
リベンジポルノ防止法(私事性的画像記録の提供等)
被写体が同級生でも、18歳未満の裸や下着姿の画像はすべて違法とされる可能性があります。加えて、保存・転送しただけでも処罰対象になるケースもあるため、「もらったから大丈夫」では済まされません。
■ 家庭でできる予防教育
-
「同意がなければすべてダメ」は最低限のルールとして徹底
-
メッセージや画像は“相手に渡した時点でコントロールできなくなる”ことを繰り返し伝える
-
「犯罪になるかもしれない」視点でスマホやSNS利用を見直す
万引き・いたずらも犯罪です
■ 「ちょっとくらいなら…」が人生を変える
子どもが軽い気持ちでやってしまいがちな万引きやいたずら行為も、立派な犯罪です。
実際、「友達にノリで誘われて」「罰ゲームで」など、遊び感覚で行ったことが窃盗罪や器物損壊罪として処罰対象になるケースは少なくありません。
中には、初犯でも警察に通報され、補導歴がついてしまうケースもあり、進学や就職に影響を与えることもあります。
■ イタズラや破壊行為も「器物損壊罪」に
-
自転車のサドルを外す
-
コンビニ前の看板を倒す
-
公園の遊具に落書きする
これらも、たとえ軽度な行為であっても、被害届が出れば犯罪として扱われる可能性があります。
最近は「その場で逃げても、防犯カメラで後から身元が特定される」事例が非常に増えています。
■ 家庭でできる声かけ
-
「見つかる・見つからない」ではなく「やっていいか・悪いか」で考えよう
-
「ノリ」や「罰ゲーム」は犯罪を免罪符にしない
-
万一やってしまったときは隠さずすぐに相談することが、被害を最小限にする
|
事例:お菓子をポケットに入れて出た→ 窃盗罪で警察に通報 中学生の男子生徒が、コンビニでガムとジュースを購入する際、レジに並ぶ友人の後ろでお菓子をポケットに入れて店を出た。 【解説】 「万引き=子どもだから注意で済む」というのは過去の話です。 万引きは窃盗罪に当たる犯罪です。 成人であれば刑事裁判で有罪になれば10年以下の懲役または50万円以下の罰金になる罪で、未成年でも児童相談所送致や保護観察の対象になることがあります。
「友達にそそのかされた」「つい出来心で」では済まされません。 |
スマホとネットの落とし穴
■ 投稿ひとつで“加害者”に変わる時代
子どもたちの生活に欠かせないスマートフォンとSNS。
しかし、使い方を誤ると、名誉毀損罪・侮辱罪・著作権法違反・リベンジポルノ防止法違反など、数多くの法律に違反する危険があります。
「バズりたい」「ウケを狙いたい」「ネタにしたい」という気持ちが、加害者として人生を左右する結果になることも。
スマホは便利な道具である一方で、“証拠が残る凶器”にもなりうるという認識が必要です。
■ 他人の画像・音楽・動画は「著作権法違反」のおそれ
-
YouTubeで流れている音楽を勝手にBGMに使う
-
有名人の画像を無断でアイコンに使う
-
漫画の一部をキャプション付きでSNS投稿する
こうした行為は、著作権侵害に該当することがあります。
子どもにとって「ネットにある=自由に使っていい」ではないことを、しっかり伝えておく必要があります。
|
事例:クラスメイトを盗撮して『きもい』と投稿→ 名誉毀損で謝罪・停学処分 高校生の女子生徒が、授業中にクラスメイトの男子を隠し撮りし、TikTokに「授業中のきもいやつw」とコメントを添えて投稿。 【解説】 たとえ冗談やノリでも、本人が不快に感じたり、社会的評価を傷つけられたと感じれば“名誉毀損”や“侮辱”が成立する可能性があります。 特にSNSでは「不特定多数に拡散されること」が重大な要素となり、本人や家族、学校にも影響が及びます。 |
■ 家庭で教えるべき“ネット5か条”
-
他人を勝手に撮らない・投稿しない
-
見た目や性格をからかう投稿は絶対NG
-
軽い気持ちでも、記録は一生残る
-
もらった画像や動画も、拡散すれば違法の可能性あり
-
「投稿する前に親に見せても大丈夫か」で判断するクセを
親ができる!家庭でのルールと声かけ
■ 加害者・被害者を「他人事」にしないために
法律や防犯の知識は、学校だけでなく家庭での積み重ねが重要です。
特にスマホやSNSの使い方、友人関係の距離感、性に関することは、親が一番近くで教えられる場面でもあります。
親が「うちは大丈夫」と油断していると、子どもは危険に気づかないまま加害者になることも。
ルールは押しつけるのではなく、“一緒に考える・話し合う”姿勢がカギです。
■ 年齢別:家庭で伝えるポイント
| 年齢層 | 声かけ・教育のポイント |
|---|---|
| 小学生 | ・良いこと悪いことを感情ではなく理由で説明する ・「人が嫌がることはしない」の意味を具体例で ・動画や画像のやりとりは親の許可制にする |
| 中学生 | ・友達とのトラブル事例を一緒にニュースで見て話し合う ・「同意とはなにか」を会話に取り入れる ・SNSのルールを家庭内で決めよう |
| 高校生 | ・「法律でどう見られるか」を共有して法的リスクを伝える ・LINEでの言葉づかいや投稿マナーから振り返る ・困ったときは早く相談すればリスクを減らせることを伝える |
■ “もしも対話”で日常から想像力を育てる
いきなり「ダメ」と言っても響きにくい時期だからこそ、「もしもこうなったらどうする?」と一緒に考える会話が効果的です。
たとえば:
-
「友達に変な画像を送ってって言われたらどうする?」
-
「友達が万引きしようとしてたら、止められる?」
-
「友達が他人の動画を勝手に投稿してたらどう感じる?」
こうした問いかけで、子ども自身に判断の材料を与えることができます。
■ 親子で一緒に作る“スマホルール”
-
他人の顔が写っている写真は投稿前に必ず確認する
-
気になる言葉づかいのスクショはすぐに親に見せてOK
-
深夜の通知やSNSは自動で止まる設定を一緒にする
-
ルールを破ったときは「怒らず、理由を話し合う」スタンスに
子どもが「ルールは親から押しつけられたものではなく、自分も納得して決めたもの」だと感じることで、主体的な行動と予防意識が育ちます。
弁護士からのアドバイス
■ 「知らなかった」では済まされない時代です
近年、子どもが関わる事件の多くに共通しているのは、
「悪気はなかった」「そんなつもりじゃなかった」「軽い気持ちだった」という言い分です。
しかし、法律の世界では“その行為が違法だったか”がすべての判断基準になります。
そして、未成年であっても補導・書類送検・保護観察などの処分が下るケースは現実にあります。本人だけでなく、親や家族も巻き込まれていくのです。
■ こんなとき、弁護士にすぐ相談を
-
警察や学校から連絡があった
-
子どもが他人の画像・動画を投稿してしまった
-
トラブルに巻き込まれて精神的に不安定になっている
-
相手の保護者と直接やり取りするのが怖い・不安
弁護士は、ただトラブルを処理するだけでなく、
子どもがこれからどう立ち直っていけるかを一緒に考えるサポーターでもあります。
親御さんだけで抱え込まず、早めの相談が最善の結果につながることを知っておいてください。
■ 「加害者」にも「被害者」にもならないために
このコラムで紹介した内容の多くは、「ちょっとした油断」や「日常の気の緩み」から始まるものばかりです。
そしてその“ちょっとした行為”が、相手にとっては一生の傷になることもあります。
逆に、子どもが被害者になっても「軽く扱われる」ことがないよう、正しい知識を身につけておくことも大切です。
■ 弁護士として伝えたい、家庭にできる3つの予防策
-
ニュースや身近な話題を親子で一緒に見る・話す
-
SNSやスマホの使い方に“ルールと相談の窓口”を作っておく
-
子どもの話を否定せず、「一緒に考えよう」と言える雰囲気を日頃から築く
防犯・法律教育は「家庭の対話」から
学校では教わらない、でも社会で生きるうえでとても大切なこと。
それが「法律」や「人を傷つけない行動」についての知識です。
親が“ちょっとした会話”の中で、子どもの心に種をまくことが、加害者にならない最大の防御になります。
一つひとつの行動を、自分で判断できる子どもに育てるために。
今日からできることを、家庭で少しずつ始めてみてください。
子どもが被害者にならないために!家庭で教えるべき法律と日常の防犯対策を弁護士が紹介します
当事務所では、初回相談無料で法律相談を受け付けております。
お気軽にお電話またはLINEにてお問い合わせください。