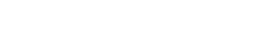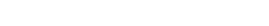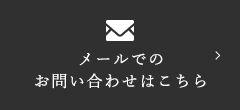2025/03/17 コラム
業務上横領の時効は何年?会社から訴えられる可能性と賠償責任を解説

会社のお金や物を管理する立場の人が、それを勝手に自分のものにしてしまうことは犯罪です。このような行為は「業務上横領」と呼ばれ、法律で厳しく罰せられます。会社で働く人なら誰でも関わる可能性があるため、正しく理解しておきましょう。
業務上横領とはどんな犯罪か?
業務上横領とは、仕事の一環として預かっているお金や物を、勝手に使ったり持ち去ったりする行為を指します。例えば、会社の経理担当が会社のお金を自分の口座に移したり、販売員が売上金をそのまま持ち帰ったりするケースが該当します。
刑法では「業務上他人の物を占有する者が、その物を横領したとき」に成立すると定められています。簡単に言えば、仕事で預かっているお金や物を、勝手に使ったり処分したりすると犯罪になるということです。
普通の横領罪との違いは?業務上横領はより重い罪になる!
横領罪には「業務上横領罪」と「単純横領罪」の2種類があります。
- 単純横領罪:他人から預かったお金や物を横領した場合に成立します。例えば、友達から借りたお金を返さずに使い込むケースです。
- 業務上横領罪:仕事の一環として預かっているお金や物を横領した場合に成立します。
業務上横領罪は、会社や組織の信用を損なう行為であり、社会への影響が大きいため、単純横領罪よりも厳しい罰則が科されます。具体的には、単純横領罪の刑罰が「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」であるのに対し、業務上横領罪は「10年以下の懲役」となっています。罰金刑がなく、より重い刑罰が科されるのが特徴です。
実際にどんなケースが業務上横領に該当するのか?
業務上横領は、意外と身近な場面で起こることがあります。以下のようなケースは、すべて業務上横領に該当する可能性があります。
✅ 経理担当が会社の口座からお金を引き出し、自分の生活費に使った。
✅ レジ担当が売上金をポケットに入れて持ち帰った。
✅ 会社の備品(パソコンやスマホ)を勝手に持ち出し、転売した。
✅ 取引先から受け取った商品を横流しし、個人的に利益を得た。
このような行為は、「バレなければ大丈夫」と思われがちですが、会社の経理や監査の仕組みは年々厳しくなっており、発覚するケースが増えています。また、業務上横領が発覚すると、解雇されるだけでなく、逮捕や裁判を受ける可能性が高くなります。
「ちょっとくらいなら…」という気持ちが大きなトラブルを引き起こすこともあります。会社のお金や物を扱う際には、絶対に私的に使わないように注意しましょう。
【業務上横領の時効は何年?刑事・民事の違い】
業務上横領が発覚した場合、「時効が過ぎれば責任を問われないのでは?」と考える人もいるかもしれません。しかし、刑事責任と民事責任では時効の期間が異なり、たとえ刑事時効が成立しても、民事で損害賠償を請求される可能性があります。ここでは、業務上横領の時効が何年なのか、時効が成立する条件や会社側の対応について解説します。
業務上横領の刑事時効は7年!
刑事事件の時効は、犯罪の種類によって決まっています。業務上横領の刑罰は「10年以下の懲役」と定められているため、刑事時効は7年です。これは、「最も重い刑罰の長さによって時効の期間が決まる」という刑事訴訟法のルールに基づいています。
業務上横領の民事時効は最大10年!
刑事時効が成立しても、民事で損害賠償を請求される可能性があります。民事の請求にはいくつかの種類があり、それぞれ時効の期間が異なります。
-
不法行為に基づく損害賠償請求 → 3年(民法724条)
➡ 会社が「被害に遭った」と認識してから3年以内に請求しなければ時効成立。 -
債務不履行(契約違反)に基づく損害賠償請求 → 5年(民法166条)
➡ 会社と従業員の契約関係を根拠に賠償請求する場合は5年が時効。 -
不当利得返還請求 → 10年(民法703条)
➡ 横領したお金は「不当な利益」として、10年以内なら返還を請求される可能性あり。
たとえ会社が被害届を出さなくても、民事裁判を起こされる可能性は十分にあるため、刑事時効が過ぎたからといって安心はできません。
【逮捕・裁判・弁済の流れ】
業務上横領は、会社の内部調査や税務監査、従業員の通報などがきっかけで発覚することが多いです。では、時効が成立する前に横領がバレた場合、どのような流れになるのでしょうか?ここでは、会社の対応や逮捕のリスク、示談による解決方法について解説します。
会社にバレたらどうなる?発覚後の会社の対応
業務上横領が発覚した場合、会社は以下のような対応を取ることが一般的です。
✅ 社内調査の実施
➡ まずは内部監査や経理部門の調査により、横領の事実を確認します。金額や手口を特定し、横領を行った人物の責任を追及します。
✅ 警察への相談・刑事告訴の検討
➡ 横領の金額が大きい場合や悪質なケースでは、会社が警察に被害届を提出し、刑事事件に発展することがあります。
✅ 損害賠償請求・民事訴訟の検討
➡ 会社が「横領された金額を取り戻したい」と考えた場合、刑事告訴とは別に、民事訴訟を起こして賠償請求することもあります。
会社の判断次第では、刑事事件と民事訴訟の両方で追及される可能性があります。
逮捕されるとどうなる?捜査・起訴・裁判の流れ
警察が業務上横領の事実を認知すると、以下のような流れで捜査が進みます。
① 警察が捜査を開始し、任意の事情聴取を受ける
➡ 横領の疑いが強まると、警察から事情聴取を求められます。ここで不審な供述をすると、逮捕される可能性が高くなります。
② 証拠が揃うと逮捕され、取り調べが行われる
➡ 業務上横領は「10年以下の懲役」という重い罪のため、逮捕される可能性が高い犯罪です。逮捕後は最大72時間、警察の留置場に拘束され、その後、検察に送致されます。
③ 検察の判断で起訴されると裁判へ
➡ 証拠が十分な場合、検察官が正式に起訴し、裁判で有罪になると懲役刑が科されます。
逮捕を回避するには?早めの示談交渉が重要
業務上横領がバレた場合、逮捕を防ぐための最善策は「示談交渉」です。
✅ 会社に対して誠意を持って謝罪し、横領金を全額返還する
✅ 弁護士を通じて示談交渉を行い、刑事告訴を取り下げてもらう
示談が成立し、会社が刑事告訴を取り下げた場合、警察や検察が事件を不起訴処分にする可能性が高くなります。また、早期に示談を行えば、会社側が被害届を出す前に穏便に解決できる場合もあります。
業務上横領は、発覚した時点で厳しい状況に陥る可能性が高いですが、早めに示談交渉を行い、誠実に対応することで、最悪の事態を回避できる場合があります。
【まとめ】
業務上横領は、仕事上預かったお金や物を私的に使う犯罪であり、刑事時効は7年、民事での損害賠償請求は最長10年となります。時効が成立しても、民事で賠償請求される可能性があり、「時効=完全に責任を逃れられる」わけではありません。
また、時効が成立する前に横領が発覚した場合、会社は社内調査・警察への告発・損害賠償請求を検討し、警察が捜査を開始すると逮捕・起訴・裁判へと進む可能性があります。
逮捕を回避し、刑事告訴を防ぐには、早期に示談を成立させることが重要です。会社へ誠意を持って謝罪し、弁護士を通じた交渉で返済を進めることで、不起訴処分や穏便な解決の可能性が高まります。業務上横領は社会的信用を大きく損なう犯罪であり、安易な気持ちで手を染めるべきではありません。
当事務所では、横領事件に関する法律相談を受け付けております。
この記事の執筆者

須賀 翔紀(弁護士)
須賀事務所 代表弁護士。刑事弁護・犯罪被害者支援を専門とし、これまでに500件以上を担当。
監修
須賀法律事務所
初出掲載:2025年3月17日
最終更新日:2025年12月27日