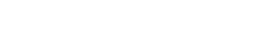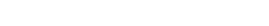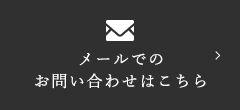2025/11/26 コラム
業務上横領罪の懲役は何年?初犯の減刑・時効についてわかりやすく解説!
業務上横領罪は、勤務先から任された財産を不正に自分のものにする行為であり、発覚した場合には厳しい処罰が待っています。
しかし、業務上横領事件では、発覚後すぐに弁護士へ相談し、被害者との話し合いを進めることで、処分を軽くできる可能性があるのはご存じでしょうか。
本記事では、業務上横領罪で科される懲役刑の年数や、被害金額によってどのように刑罰が変わるのかについて、具体的な事例を交えながら詳しく解説していきます。
初めて罪を犯した場合に執行猶予がつく確率や、刑事・民事それぞれの時効期間についても触れていきますので、現在トラブルに直面している方の判断材料としてお役立てください。
|
【目次】 |
業務上横領罪の定義とは?

刑法第253条には、業務として管理している他人の財産を不正に自分のものにした者への罰則が記されています。この条文では「10年以下の懲役」という刑罰が設定されており、通常の横領よりも厳格な処罰内容となっているのです。
ここで使われる「業務」という表現は、社会的な立場に基づいて日常的に反復して実施する職務活動を意味します。企業の会計担当が売上を取り扱ったり、販売員が顧客からの入金を一時的に保管したりするケースが代表例です。
また「横領」の意味は、自らが預かっている他者の資産を、正当な理由なく私物化してしまう違法行為を指しています。
業務上横領の罪に認められる要件4つを解説!

業務上横領罪として法的責任を問われるには、法律で設けられた複数の基準をすべて充足する必要があり、これらの基準が一つでも満たされていなければ、業務上横領罪は法的に成立しないことになるのです。
司法の場では、これらの基準が整っているかを丁寧に検証したうえで、有罪・無罪の判断を下します。どういったケースが罪に問われるのか見ていきましょう。
①業務内で行った
業務上横領罪が法的に認められるための最初の基準は、不正行為が「業務」の枠組みで実行されたことです。
法的な意味での業務とは、社会における一定の役割に基づき、継続反復的に遂行される職務を表しています。正規雇用の従業員に限らず、非正規雇用や短時間勤務者であっても、その担当職務が恒常的な特性を有するものなら業務として扱われるのです。
例を挙げると、飲食店で日々の売上管理を任されているパートタイマーや、週何日か勤務する経理スタッフも、その担当職務は業務性を帯びていると判断されます。
これに対し、知人から単発で金銭を預けられて無断使用した状況は、一般的な横領罪(刑法第252条)に該当し、罰則は5年以下の懲役へと軽減されるでしょう。
②委託・信頼に基づいて移された
業務上横領罪における次の基準は、資産が信頼委託の関係に基づいて管理されていたという点です。
これは、経営者や組織が職員を信用して資産の管理責任を託しているという関係構造を表しています。会計部署の職員が企業の通帳や社印を預かるケースや、店舗管理者が日々の売上金を保管するケースなどが典型的な状況です。
こうした信用関係が存在するがゆえに、それに背いて不正を働いた際の違法性がより強く評価されることになります。
単純に他者の資産を盗む窃盗とは性質が異なり、信用された地位を悪用したという観点で、社会的批判がより厳しくなるのです。委託の様式は、正式な契約文書がなくとも、職務内容から自然に認識される状況も対象に含まれます。
③自己の所有物でないこと
業務上横領罪の第三の基準は、管理対象となっている資産が「他者の財産」であることです。法的な所有権限が自身以外の個人や団体に帰属する資産でなければ、横領罪は法的に構成されません。
企業の運営資金や取引先から受領した商品対価など、明白に他者に属する資産が該当します。しかしながら、所有権の帰属先が不明瞭な状況も現実には発生します。
具体例として、営業活動費として企業から支給された現金を私用に充てた状況では、その金銭の所有権は引き続き企業にあると見なされるため、横領罪に当てはまる可能性があります。さらに、自身の銀行口座へ企業の売上金を暫定的に預け入れ、その後引き出して消費した場合も、引き出し金額や使途の内容次第では横領と評価されることがあるでしょう。
④不法領得行為である
業務上横領罪の最終的な基準は、不法領得の意図を抱いて領得行動を実施したことです。
不法領得の意図とは、他者の資産を自己の財産として取り扱い、その経済的価値を自己の利益のために活用したり処分したりする心理状態を持つことを意味します。わずか数日間だけ借用する心積もりで使用した状況は、この基準を充足しないと評価される余地もあるのです。
具体的状況としては、企業の金銭を自己の債務返済に投入したり、個人的な購買活動に消費したりした場合が代表的な不法領得行動となります。また、企業の取扱商品を無断で販売して代価を私有した場合も、明瞭に不法領得の意図があったと評価されるでしょう。
この基準の評価では、行動時の内面的な意図だけでなく、その後の行動様式も重要な立証材料として取り扱われます。
業務上横領の量刑は10年以下の拘禁刑と定められている!

刑法第253条には、業務上横領罪に対する法定刑として「10年以下の懲役」が明記されています。
2025年6月1日に施行された刑法改正により、「懲役」と「禁錮」が廃止され、「拘禁刑」という新たな刑罰に統一されました。ただし、身体を拘束する刑罰である点は従来と変わりません。
この罪には罰金刑の規定がないため、有罪となった場合は懲役刑(拘禁刑)の宣告を受けます。一方で、執行猶予が付与される場合もあります。
つまり、現実に宣告される刑期は、個別事案の具体的状況によって相当に変動するのです。被害金額の規模、犯行の事前計画性の程度、被害者への賠償状況、本人の悔悟の深度などが包括的に査定されて最終的な刑期が確定します。
初回の犯行で被害額が小さく、賠償が済んでいる場合は、およそ6〜7割のケースで執行猶予が付与されています(裁判所統計年報による)。被害額が数千万円から億単位の規模に達するような悪質な状況では、実刑判決が宣告される可能性が上昇します。
業務上横領の被害額による刑量の目安とは?
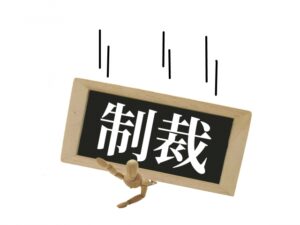 業務上横領罪における刑罰の程度は、とりわけ被害金額の規模に強く影響されます。司法機関は被害額を最重要の量刑判断基準として位置づけており、金額規模が拡大するにつれて厳格な刑罰を科す傾向が見られます。
業務上横領罪における刑罰の程度は、とりわけ被害金額の規模に強く影響されます。司法機関は被害額を最重要の量刑判断基準として位置づけており、金額規模が拡大するにつれて厳格な刑罰を科す傾向が見られます。
以下では、被害金額の段階ごとに、どの程度の刑期が宣告される見込みがあるのかを具体的に確認していきましょう。
被害額100万円以下
会社のお金を横領してしまった場合でも、その額が100万円未満で、なおかつ今回が人生で初めての犯罪行為だったという状況なら、刑務所には入らずに済む可能性が高いです。
具体的には、裁判で「懲役1年6ヶ月」といった判決が出たとしても、その後に「3年間は様子を見ます」というような猶予期間が設けられ、その期間中に何も問題を起こさなければ刑の執行が免除されるという仕組みです。
想定されるのは、横領してしまったお金を既に会社や被害者に返しているケースや、相手方と直接話し合って「もう許します」という合意ができている場合です。こうした状況では、判決そのものがより軽くなる傾向があります。
ただし注意が必要なのは、犯行の計画性です。例えば数ヶ月前から周到に準備していた痕跡が見つかったり、少額とはいえ5回も6回も繰り返していたことが明らかになったりすると、金額の少なさに関わらず実際に服役することになる判決が出る場合もあります。
また、過去に窃盗や詐欺など似た性質の犯罪で処罰された記録がある方については、猶予がつかない可能性が高くなります。
被害額100万円〜1000万円
横領の金額が100万円を超えて1,000万円あたりまでの範囲となると、裁判所の判断は要件によりさまざまです。
初めての犯罪で、しかも被害者へのお金の返済が完了している状況であれば、「懲役2年6ヶ月、執行猶予3年」といった猶予付きの判決になることが多いでしょう。しかし反対に、被害弁償が1円も進んでいない状態だったり、手口が計画的で非常に悪質だと判断されたりすれば、猶予なしで直接刑務所に入ることになる判決も十分にあり得ます。
この金額レベルで最も重要な要素となるのが、被害を受けた会社や個人との関係性です。
例を挙げると、被害者が裁判所に対して「本人は深く反省しているので、できれば寛大な処分を」という内容の嘆願書を提出してくれているような場合、猶予がつく可能性は高まります。
対照的に、被害者が「絶対に厳罰を望みます」と強く訴えていたり、お金を返す意思すら見せていなかったりする状況では、実刑になる確率が跳ね上がります。
被害額1000万円以上
横領額が1,000万円以上となってくると、刑務所に入る判決が出る可能性は極めて高いと考えておく必要があります。
たとえ人生で初めて罪を犯したという状況であっても、被害の大きさから「社会への影響が深刻すぎる」と評価され、懲役4年から6年程度の実刑が下されるパターンが一般的です。
もし被害総額が億単位に達するような超悪質なケースでは、法律上の最高刑である懲役10年に迫るような重い処罰を受けるリスクもゼロではありません。
こうした高額事案においては、被害者にお金を全額返済済みであることが「もしかしたら猶予がつくかもしれない」という可能性の最低ラインになりますが、それでも実刑となってしまうことの方が多いのが現実です。
なぜなら、裁判所は事件の重大性や社会全体に与えるダメージの大きさを重く見て、「今後同じような犯罪を防ぐには、見せしめとしても厳しい罰が不可欠だ」という考え方で判断を下すことがあるからです。
特に、3年も4年もかけて組織的に不正を働いていたケースや、最終的に会社を破綻させてしまったような事例では、裁判官から非常に厳しい目で見られることになります。
業務上横領の時効はどのくらい?

業務上横領という罪には、大きく分けて2種類の時効が存在しています。ひとつは「刑事事件として起訴できる期限」であり、もうひとつは「民事裁判で損害賠償を請求できる期限」です。
刑事の時効と民事の時効では、その性質も期間の設定も全く異なっていますので、ひとつずつ解説します。
刑事の業務上横領罪は7年
業務上横領罪の公訴時効期間は刑事訴訟法250条に基づき7年と定められています。この期間は、犯罪行為が終了した時点から計算が始まるため、横領行為を行った日から7年が経過すれば、検察官は起訴できなくなるのです。
ただし、逃亡している場合や、捜査機関が犯人を特定できない状況にある場合には、時効の進行が停止することもあります。
公訴時効の趣旨は、長期間経過した犯罪について証拠が散逸し、適正な裁判の実施が困難になることを防ぐという点にあるのです。また、長年にわたって平穏に生活してきた者を、今さら処罰することの社会的意義が薄れるという考え方も背景にあります。
ただし、時効期間が経過する前に新たな横領行為を行った場合には、それぞれの行為について個別に時効期間が進行することになるでしょう。
民事の損害賠償の場合3年または20年
業務上横領によって被害を受けた会社や個人は、横領を行った者に対して損害賠償を請求することができます。この民事上の損害賠償請求権には消滅時効が設けられており、被害者が損害および加害者を知った時から3年間、または不法行為の時から20年間で時効により消滅するのです。
3年の短期消滅時効は、被害者が横領の事実を知り、かつ横領を行った者が誰であるかを特定した時点から進行します。
たとえば、会計監査によって横領が発覚し、犯人が特定された日から3年以内に損害賠償請求の手続きを行わなければ、請求権が時効消滅してしまう可能性があるでしょう。
一方、20年の長期消滅時効は、横領行為が行われた時点から進行するため、被害者が横領の事実を知らなかった場合でも、行為時から20年が経過すれば請求権は消滅します。実務上は、横領が発覚した時点で速やかに損害賠償請求の手続きを開始することが重要になってくるのです。
業務上横領で初犯だと執行猶予や不起訴処分になる可能性について解説!

業務上横領罪で初めて刑事事件に関わることになった場合、執行猶予や不起訴処分となる可能性があります。事件発覚後の対応によって大きく左右されるため、適切な初動対応が極めて重要です。
以下では、初犯者がどのような処分を受ける可能性があるのかについて、統計データや実務の傾向を踏まえて解説していきましょう。
66%が執行猶予がつく
業務上横領罪における統計データによれば、初めて罪を犯した被告人のうち約66%に執行猶予が付されているとされています。
これは、裁判所が初犯者に対して更生の機会を与えることを重視しており、直ちに刑務所に収容することが必ずしも適切ではないと判断しているためです。執行猶予が付されれば、判決で言い渡された刑期の期間、刑務所に収容されることなく通常の社会生活を送ることができます。
執行猶予を獲得するための要素として、被害者との示談成立が挙げられるでしょう。被害弁償を完了し、被害者から許しを得ている場合には、執行猶予の可能性が大幅に高まるのです。
また、家族の監督が期待できることや、安定した職に就いていることなども、有利な事情として考慮されることになります。
被害額が大きいと実刑になる
業務上横領罪において、被害金額が極めて大きい場合には、初めて罪を犯した場合であっても実刑判決となる可能性が高くなります。
被害額が数千万円から億単位に達するような事案では、たとえ一部の弁償がなされていても、執行猶予を獲得することは困難になってくるのです。
裁判所は、犯罪の重大性や社会的影響の大きさを重視し、厳罰をもって臨む姿勢を示すことがあります。
特に、横領によって会社が倒産に追い込まれた場合や、多数の従業員が職を失うことになった場合には、社会的影響の大きさから実刑判決が避けられないことが多いでしょう。
また、横領した金銭をギャンブルや遊興費に浪費していた場合には、被告人の規範意識の欠如が問題視され、量刑が重くなる傾向にあります。長期間にわたって組織的に横領を繰り返していた事案や、会計処理を巧妙に偽装して発覚を免れようとしていた事案も、悪質性が高いと評価されて実刑判決となりやすいのです。
業務上横領で逮捕されないためにすべきこととは?

業務上横領の疑いがかけられている場合や、すでに横領してしまった事実がある場合には、逮捕を回避し、できる限り軽い処分を得るために適切な対応をとることが重要です。
早期に適切な行動を起こすことで、不起訴処分や執行猶予を獲得できる可能性が高まります。以下では、具体的にどのような行動をとるべきかを解説していきましょう。
すぐに弁護士に相談する
業務上横領の疑いがある場合には、できるだけ早く弁護士に相談することが最優先の対応となります。弁護士は法律の専門家として、現在の状況を客観的に分析し、今後の見通しや取るべき対応について的確にアドバイスができます。
特に刑事事件に精通した弁護士であれば、捜査機関との対応や被害者との示談交渉について豊富な経験を持つため、より適切なサポートを受けることができるでしょう。
弁護士に依頼するメリットとして、まず捜査機関からの取調べに対する適切な対応方法について助言を得られることが挙げられます。取調べでは、不用意な発言が不利な証拠となってしまう可能性があるため、弁護士のアドバイスに従って慎重に対応することが重要なのです。
また、弁護士は被害者との示談交渉を代理で行うことができるため、感情的な対立を避けながら冷静に話し合いを進めることが可能になります。
被害者と示談する
業務上横領事件において、被害者との示談を成立させることは、刑事処分を軽減するうえで極めて重要な意味を持ちます。
示談が成立し、被害弁償が完了している場合には、不起訴処分となる可能性が高まりますし、起訴された場合でも執行猶予を獲得しやすくなるのです。
検察官や裁判官は、被害回復がなされているかどうかを重要な判断要素として考慮するため、早期に示談交渉を開始することが求められます。
示談交渉においては、まず被害額を正確に算定し、それに見合った示談金を提示することが必要です。被害額全額の弁償が理想的ですが、一括での支払いが困難な場合には、分割払いでの合意を目指すこともあるでしょう。
示談の内容には、単に金銭の支払いだけでなく、被害者が処罰を望まない旨の意思表示(宥恕条項)を盛り込むことが重要になります。被害者が加害者の処罰を望んでいないという意思が示談書に明記されていれば、検察官が不起訴処分を決定する際の重要な判断材料となるのです。
業務上横領で弁護士に相談したい場合は須賀法律事務所へ!

業務上横領罪は、職務として預かっていた他人の財産を不正に自分のものにする重大な犯罪行為であり、法定刑は10年以下の拘禁刑と定められています。
業務上横領の疑いがある場合や、すでに横領してしまった場合には、できるだけ早く弁護士に相談し、被害者との示談交渉を進める必要があります。適切な初動対応により、不起訴処分や執行猶予を獲得できる可能性が高まるためです。
業務上横領に関する法律相談をお考えの方は、須賀法律事務所へご相談ください。須賀法律事務所は刑事事件の弁護に豊富な実績を持つ法律事務所として、依頼者一人ひとりの状況に寄り添いながら最善の解決策を提案しています。
ご相談はオンラインチャットツールやお電話で・受任契約は電子署名や郵送で完結しており、ご相談からご依頼までのハードルを極力下げる取り組みを行っているのが特徴です。不起訴処分や執行猶予の獲得に向けて、依頼者の権利を守りながら迅速かつ全力でサポートいたします。
業務上横領でお困りの際は、一人で悩まず、ぜひ須賀法律事務所にお気軽にお問い合わせください。相談しやすい環境を整えてお待ちしております。