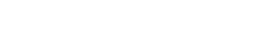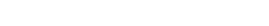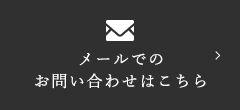2025/07/20 コラム
ストーカー警告に納得いかない?撤回方法と正しい対処法を徹底解説!

ストーカー警告を受けた際に「納得いかない」と感じる方は少なくありません。警告は法律に基づいて発せられますが、誤解や認識の違いから不当だと感じることもあるでしょう。
ある日突然、警察から「ストーカー警告」を受けたものの、身に覚えがない、あるいは正当な連絡だったというケースに遭遇した時、誤った対応を取ると重大な法的リスクに発展する恐れがあります。
本記事では、ストーカー警告の仕組みや法的な位置づけをわかりやすく解説するとともに、納得できない場合の具体的な対処法や撤回方法について詳しく解説。正しい知識を身につけ、F適切に対応するための情報を提供します。
ストーカー警告とは?強制力と法的リスクをわかりやすく解説

ストーカー問題は現代社会において非常に深刻な課題であり、被害者の安全確保は極めて重要なテーマです。こうした背景から、法律や警察による様々な対応策が整備されました。
しかし、その内容や手続きの仕組みは複雑で、一般の方には分かりづらい部分も多く存在します。本章では、ストーカー規制に関わる基本的な考え方や措置について理解を深めていただくため、前提となる法的枠組みと制度の概要について説明します。
規制法の概要と警告の位置づけ
ストーカー規制法は、ストーカー行為によって被害者の生命や身体、自由、名誉などが侵害されることを防止し、被害者の安全を確保することを目的として制定された法律です。この法律では、つきまといや待ち伏せ、連絡の強要など多様なストーカー行為を明確に禁止しています。
警察は、被害者の申告や相談を受けて捜査を行い、ストーカー行為が疑われる場合には、まず警告を発します。警告は、被疑者に対して行為の中止を促す行政指導であり、これにより自らの行動を見直し、改善する機会を与えることが狙いです。
法的には警告自体に法的拘束力や刑罰は課されませんが、これを無視してストーカー行為を続けた場合、都道府県公安委員会による禁止命令の申立てや刑事罰の対象となる可能性が高く、禁止命令に違反すると刑事罰の対象となります。したがって、警告は法的手続きの中で初期段階に位置し、違法行為を抑制し被害の拡大を防ぐための重要な役割を持つものです。
また、警告は被疑者の行動を法律的に明示し、その後の厳格な対応の根拠となるため、法的リスクを認識させる点でも意義があります。被害者保護の観点からも警告の発出は迅速かつ適切に行われるべきであり、警察の調査や判断が重要なポイントです。
総じて、ストーカー規制法の枠組みの中で警告は、被害者の安全確保と被疑者への法的抑止力の双方を実現するための基盤的な措置と位置づけられています。
被害届・告訴・禁止命令・逮捕の違い
ストーカー問題に関する法的手続きは段階的に進行し、それぞれの措置には明確な役割と法的効果があります。まず「被害届」とは、被害者が警察に対してストーカー行為の事実を申告し、捜査の開始を促すためのものであり、これは事件の発端となります。
次に「告訴」は、被害者が加害者の刑事処罰を正式に求める意思表示であり、告訴がなければ刑事手続きが進まないケースも。一方、「禁止命令」は都道府県公安委員会が発する法的拘束力を有する命令で、加害者に対し被害者への接近禁止や連絡禁止などの義務を課します。
最後に「逮捕」は、警察が犯罪の嫌疑が濃厚な被疑者を拘束する強力な法的措置です。これらの中で「ストーカー警告」は初期段階に位置し、行為の停止を促す行政的な措置として、被疑者に改善の機会を与えるものです。警告が無視されると、より強い法的手続きへと移行するため、警告の受領は非常に重要な意味を持ちます。
以上のように、各措置はストーカー問題の解決に向けて連携しながら段階的に適用されることが一般的です。
ストーカー警告に「納得いかない」状況が起こる3つのパターン

ストーカー警告を受けた際に納得いかないと感じるケースは多々あります。その背景には、警告が出されるまでの経緯や内容の理解不足、さらには誤認によるものなど、さまざまな事情が絡んでいます。
本章では、ストーカー警告に対して納得いかないと感じやすい代表的な3つのパターンを取り上げ、それぞれの特徴と問題点を明確に解説します。これにより、警告に疑問を感じる方が自らの立場や状況を冷静に分析し、適切な対応を検討する一助としてみてください。
被害者の申告による誤認ケース
ストーカー警告は、ほとんどの場合、被害者の申告に基づいて発せられます。被害者の感情や恐怖心は非常に重要ですが、その主観的な感覚が過剰に強まると、実際の行動以上にストーカー行為として誤認されることがあります。
この誤認は、警察が申告内容を基に判断を行うため、客観的な証拠が乏しい場合に起こりやすい問題です。被害者の申告が唯一の根拠となるため、加害者の意図や行動の正当性が十分に評価されないこともあります。こうした場合、本人としては納得いかないストーカー警告が発せられ、精神的な負担や社会的信用の低下につながる恐れがあります。
対処法としては、まず自身の行動記録や連絡の履歴を詳細に保存することが重要です。日付や時間、内容が明確な形での証拠は、誤認を正すうえで大きな助けとなります。また、法律の専門家に早期に相談することで、警察への説明や適切な対応を助言してもらえます。
誤認による警告は被疑者に大きな影響を与えるため、冷静かつ迅速に対応し、法的手続きを適切に進めることが不可欠です。こうしたケースにおいても、法律の専門家のサポートを受けることが被疑者の権利保護につながります。
正当な連絡との境界線
仕事上や家庭内での連絡は、通常、正当なコミュニケーションとして認められています。しかし、相手が望まない場合や、連絡の頻度や内容が過剰になると、ストーカー行為とみなされる可能性があります。どこまでが正当な連絡で、どこからがストーカー行為にあたるか、その境界線は曖昧であり、トラブルの原因となりやすいです。
例えば、業務連絡や親しい間柄での連絡であっても、相手の意思を尊重しなければ、受け手に不安や迷惑を与えてしまいます。特に、一方的に連絡を続けたり、断られているにも関わらず執拗に連絡を重ねる行為は、ストーカー規制法の対象となり得ます。
法律では「つきまとい等」として規定されていますが、具体的な線引きは事案ごとに異なるため慎重な対応が必要です。したがって、相手の反応や状況をよく観察し、連絡頻度や内容を調整することが重要です。
もし警告を受けた場合は、直ちに連絡を停止し、警察や弁護士と相談しながら今後の対応を検討することが望まれます。正当な連絡とストーカー行為の境界を理解し、適切に行動することがトラブル回避の鍵となります。
第三者の通報での誤認
ストーカー警告は、被害者本人だけでなく、第三者からの通報に基づいて発せられる場合もあります。友人や近隣住民、職場の同僚など、被害者の周囲の人々が不安を感じて通報するケースがこれにあたります。第三者の通報は被害者の安全を守るうえで重要ですが、その情報が断片的であったり誤解に基づく場合、警告の発出が誤認につながることがあります。
第三者の視点では、実際の状況や当事者間の事情が十分に把握されないまま判断されるため、加害者の行動が過剰に評価されるおそれがあります。このような誤認を防ぐためには、警察による十分な調査と証拠収集が不可欠です。誤った警告が出された場合には、事実関係を整理し、専門家の助言を仰ぎつつ適切な対応を検討することが求められます。
また、第三者通報が原因で警告を受けた場合でも、本人は法的措置に対して異議を唱えたり、説明の機会を求める権利があります。適切な法的サポートを受けることで、不当な警告による不利益を最小限に抑えられる可能性が高まります。
ストーカー警告を受けたらすぐにやるべきこととは?

ストーカー警告を受けた際は、冷静かつ迅速に対応することが非常に重要です。警告は(記録には残るが、法的な拘束力は持たない)(記録には残るが、法的な拘束力は持たない)法的な意味を持つ正式な文書(記録には残るが、法的な拘束力は持たない文書)であり、これを無視するとさらなる法的措置が取られる可能性があります。
ここでは、警告を受けた直後に取るべき具体的な行動と注意点を解説します。これにより、トラブルの拡大を防ぎ、適切な対応を進めるための指針としてみてください。
連絡・接近を停止しSNSも控える
ストーカー警告を受けた場合、最も重要な初動対応は、被害者への連絡や接近を即座に停止することです。これはストーカー規制法上の基本的義務であり、警告にもその旨が明記されています。警告を無視して接近や連絡を続ければ、禁止命令や逮捕など厳しい法的制裁を受ける可能性があります。
特に連絡手段として頻繁に利用される電話やメール、メッセージアプリは、被害者にとって心理的な負担が大きいため、警告を受けたら一切の連絡を控えることが求められます。例え誤解やトラブルの原因を説明したい場合でも、直接連絡を試みることは逆効果となり、状況を悪化させる恐れがあります。
また、SNS上の投稿やメッセージも注意が必要です。たとえ間接的であっても、被害者に気づかれたり、不快感を与える内容は新たな問題の火種となり得ます。特に投稿でのコメントやタグ付け、共通の知人を介した情報の拡散もストーカー行為とみなされることがあるため、警告を受けた段階ではSNSの使用も控えるのが賢明です。
さらに、誤解を避けるため、共通の知人への連絡も控えましょう。自分の意図とは無関係に、第三者が介在することでトラブルが拡大するリスクがあります。警告後は冷静に状況を見極め、法律の専門家に相談してから次の行動を決めることが重要です。
以上のように、ストーカー警告を受けた際は、被害者への直接・間接的な連絡を全面的に停止し、SNSや第三者を通じた接触も控えることで、事態の悪化を防ぐことが必要です。迅速かつ適切な対応によって、法的リスクを最小限に抑えることが可能となります。
履歴を保存して証拠を整理する
ストーカー警告を受けた際、自身の行動が誤認されていると感じる場合には、証拠の整理が極めて重要になります。具体的には、連絡の日時や内容、相手の反応などを詳細に記録し、可能であればメッセージや通話履歴のスクリーンショット、録音データなども保存しておくことが推奨されます。
また、証拠の保存は単に警察や裁判所に説明する際だけでなく、誤解を解くための話し合いや示談交渉においても役立ちます。日常的なやり取りであっても、感情的な行き違いが起こりやすいため、記録を整理することで客観的な状況把握が可能になります。
さらに、保存した証拠は速やかに専門家に見せることが望ましく、弁護士の助言を受けることで、適切な法的対応や警察との交渉がスムーズに進みます。証拠の欠如や不十分な記録は、誤認の解消を困難にし、場合によっては不利な結果を招く恐れもあるため、警告を受けたらすぐに行動することが肝要です。
被害届の写し確認と質問準備
ストーカー警告を受けた場合、まず重要なのは被害届の内容を弁護士を通じて確認し、どのような行為が問題とされているか把握することが重要です。被害届とは、被害者が警察に対して正式に被害事実を申告する文書であり、その中にはどのような行為が問題とされているのかが具体的に記載されています。
警告の根拠となっている申告内容を正確に把握しなければ、適切な対応や反論を行うことは困難になるため、被害届の内容を確認する際には、どの時点の行為が問題視されているのか、どのような証拠があるのかなどを細かくチェックしましょう。
また、申告内容に不明点や疑問があれば、事前に質問事項を整理しておくことが重要です。これにより、警察や弁護士に相談する際に、的確かつ効率的なコミュニケーションが可能となります。
さらに、被害届に記載されている内容と自身の認識が食い違っている場合は、その差異を明確に説明できる証拠の準備も必要です。警察の調査や手続きに積極的に協力しつつも、誤解や不当な申告がある場合は法律専門家の助言を得て、訂正や撤回を求める手続きを検討しましょう。
なお、被害届の写しを警察から入手する際には、手続きや対応方法についても確認しておくことが望ましいです。被害届の写し自体は通常、加害者側には交付されません。適切な手順を踏むことで、後の法的対応が円滑に進み、警告の内容に対する正当な異議申し立てが可能となります。
ストーカー警告を受けた際は、焦らず冷静に被害届の内容を把握し、専門家と連携しながら対応することが被害者との誤解を解く鍵となります。
被害者との誤解を招くコミュニケーションを避ける
ストーカー警告を受けた場合、被害者との直接的なコミュニケーションは避けることが非常に重要です。誤解を招く恐れがあるため、感情的なやり取りや一方的な説明はトラブルを深刻化させかねません。特に、被害者が不安や恐怖を感じている状況では、直接連絡を取ること自体がさらなる警告や法的処置の対象となる可能性があります。
また、被害者との接触を試みることは、警告の内容に反する行為であり、ストーカー規制法の違反と見なされるリスクがあります。警告に従わない場合は、接近禁止命令や逮捕など厳しい法的措置が取られることもあります。そのため、連絡や接近は控え、状況の改善や誤解の解消は法律の専門家を介して行うべきです。
専門家の助言を受けることで、冷静かつ適切な対応が可能となり、不必要なトラブルの拡大を防止できます。誤解がある場合は、弁護士を通じて被害者や警察と連絡を取り、話し合いや示談を進めることが望ましいです。自己判断での接触は避け、法的リスクを十分に理解した上で慎重に行動しましょう。
ストーカー規制法違反での罰則を解説!

ストーカー規制法に違反した場合には、厳しい刑事罰が科される可能性があります。
まず、つきまといや待ち伏せ、連絡の強要など、法律で禁止されているストーカー行為を行った場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。さらに、都道府県公安委員会から禁止命令等が出されたにもかかわらずストーカー行為を続けた場合は、より重い罰則が適用され、2年以下の懲役または200万円以下の罰金となります。また、禁止命令に違反したもののストーカー行為には至らなかった場合でも、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることがあります。
このように、ストーカー規制法は被害者の生命や身体、自由を守るために厳しい罰則を設けており、違反行為があった場合には迅速かつ厳格な対応が取られます。警告を受けた段階で法的リスクを十分に認識し、速やかに適切な行動をとることが重要です。
ストーカー被害者との示談は可能?

ストーカー被害が発生した場合、被害者と加害者が話し合いで解決を目指す示談が選択肢のひとつとなります。示談は双方の合意に基づき、損害賠償や今後の行動について取り決めることで、刑事事件の進行を緩和する効果も期待されます。
しかし、感情が絡む問題であるため示談が成立するまでには時間や慎重な対応が必要です。本章では、ストーカー被害者との示談の可能性について基本的な考え方や留意点を解説します。
示談金の相場
ストーカー被害に関する示談金の相場は、被害の内容や程度、被害者の精神的苦痛の度合い、加害者の経済状況など多くの要素によって左右されます。一般的には、軽度のケースでは数十万円程度から始まり、被害が深刻であれば数百万円に達することも珍しくありません。
示談金は被害者に対する損害賠償として支払われ、被害者の心の傷や生活への影響を考慮して決定されます。しかし、示談金の額は一律に決まっているわけではなく、双方の合意が必要です。
加害者が高額すぎる示談金を提示すると、示談自体が成立しにくくなるため、相場感を理解したうえで現実的な金額を提示することが重要です。また、被害者側も精神的苦痛の度合いや被害状況によって要求額に幅が出るため、交渉には時間と根気が必要となることが多いです。
示談交渉では、感情的な対立を避けるために弁護士などの専門家を介入させるケースも増えています。専門家の助言を受けることで、適切な示談金の設定や交渉の進め方が円滑に行われ、双方にとって納得のいく解決を目指すことが可能です。示談金はあくまで和解のための条件の一つであり、被害者の心情を尊重した誠実な対応が求められます。
示談の注意点
示談を成立させる際には、いくつか重要な注意点があります。まず、示談は口頭だけではなく、必ず書面での合意を作成し、双方が署名・押印することが必須です。これにより、後日のトラブル防止や証拠の確保が可能となります。
示談書には、示談金の支払い条件、今後の接触禁止の範囲、謝罪文の提出義務など具体的な内容を明記することが重要です。また、示談は刑事手続きに影響を与えることがありますが、示談成立が必ずしも刑事責任の免除を意味するわけではありません。
被害者の安全確保が最優先されるため、刑事事件として処理されるケースもあります。示談交渉を進める際は、法律の専門家に相談し、適切な法的アドバイスを受けながら行うことが望ましいです。
さらに、示談成立後も一定期間はトラブル再発のリスクがあるため、警察や弁護士と連携して経過を見守ることが重要です。示談の内容に不備や曖昧さがあると、再度紛争に発展する恐れがあるため、慎重な内容確認と合意形成が必要です。示談はトラブル解決の一手段ですが、法的リスクを十分に理解したうえで進めるべきです。
ストーカー警告に納得いかない方は須賀法律事務所へ

ストーカー警告に納得できない場合や、誤認による警告でお困りの方は、法律の専門家に相談することが最も重要です。ストーカー警告は警察による行政指導であり、法的拘束力や直接の罰則はありませんが、警告を受けた事実が記録として残るため、今後の対応や名誉回復のためには慎重な対応が必要です。
現行法上、ストーカー警告そのものを撤回・取消すための法的手続きは原則として存在しません。ただし、誤認が明らかな場合や不当な警告だと考えられる場合には、弁護士を通じて警察に事実関係を説明し、記録上の訂正や説明の添付を求めるなどの対応を検討することができます。
須賀法律事務所は、ストーカー規制法をはじめとした刑事事件やトラブル解決に豊富な実績を持ち、依頼者の立場に立った丁寧な対応を心がけています。状況の正確な把握から証拠の収集、警察や裁判所との交渉、示談交渉や刑事手続きの代理まで、包括的にサポート。依頼者の権利を守るために尽力いたします。
詳しくは須賀法律事務所公式サイトよりご確認ください。
当事務所では、軽犯罪法に関する法律相談を受け付けております。
お気軽にお電話またはLINEにてお問い合わせください。