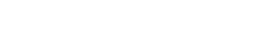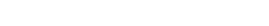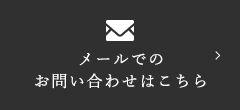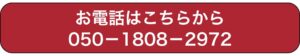2025/07/17 コラム
「突然の家宅捜索!警察が来たときに慌てないために知っておきたい対処法と弁護士に相談するメリットとは
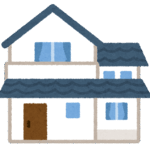

家宅捜索が行われる条件と基礎知識
◆ 家宅捜索とは何か?
家宅捜索(かたくそうさく)とは、捜査機関(警察や検察など)が被疑者の関係する住居や職場に立ち入り、証拠品を探して押収する手続きのことをいいます。
多くの場合、裁判所の発行した「捜索差押許可状(令状)」に基づいて行われます。
警察官がいきなり自宅にやってきて、「令状があります」と言って中に入ろうとするのは、この家宅捜索の典型的なパターンです。
驚いてしまうかもしれませんが、適法に行われている捜索であれば、原則として拒否することはできません。
◆ どんなときに行われるのか?
家宅捜索が行われるのは、主に以下のような状況です。
-
刑事事件の証拠を探す必要があるとき
-
被疑者がその場所に関係していると捜査機関が判断したとき
捜索には必ず「裁判所の令状」が必要です。
この令状には、以下のような内容が記載されています。
-
捜索する場所(自宅・車など)
-
押収する物(スマホ、パソコン、書類、薬物など)
-
日時と有効期間
-
発行した裁判官の名前と日付
令状の中身(対象物・場所・日付など)を確認することが重要です。
スマホで撮影しておくと、後日違法性を争う際の材料になります。
⚠️ 令状なしの家宅捜索は原則として違法です。
ただし例外もあります(後述)。
◆ 家宅捜索が実施される主なケース
一般の方にとっては「家宅捜索なんて無縁」と思われがちですが、実は下記のようなさまざまな事件で実施されています。
|
特にスマートフォンやパソコンは、あらゆる事件で押収対象になりやすいため、注意が必要です。
◆ 家宅捜索と逮捕が連動するケースも多数

家宅捜索は、逮捕と同時または直前に行われることが少なくありません。
たとえば、
-
警察が被疑者の自宅を訪ねて、まずは本人に立ち会いを求めた上で家宅捜索を実施し、捜索後に警察署へ任意同行→逮捕という流れ。
-
あるいは、すでに容疑者を逮捕・連行した上で、残された家族を立会人として家宅捜索を行うパターンもあります。
つまり、家宅捜索が始まった時点で、すでに刑事手続きが重大局面に入っている可能性が高いのです。
この時点で弁護士に連絡しておくことで、以降の逮捕・取り調べに備えることができます。
◆ 令状がない捜索は違法?
原則として、家宅捜索は裁判所の令状なしでは実施できません。
これを「令状主義」といい、憲法にも明記されています。
ただし、例外もあります。
1. 現行犯逮捕に伴う捜索・差押え(刑訴法220条)
- 要件:現行犯人を逮捕した直後で、証拠隠滅の恐れがある場合。
- 内容:逮捕現場やその周辺で、犯行に関連する証拠品を捜索・差押えできる。
- 制限:逮捕と密接に関連する範囲に限られ、広範な家宅捜索は不可。
2. 緊急捜索(刑訴法220条但書)
- 要件:逮捕令状による通常逮捕を行う場合。急を要し、令状を取る時間的余裕がない場合。
- 内容:逮捕に関連する証拠を確保するため、逮捕対象者の住居などを捜索できる。
- 制限:後日、令状を取得して事後的に適法性を担保する必要がある。
3. 任意捜査
- 要件:住人の明確な同意があること。
- 内容:同意に基づき、住居内を捜索することが可能。
- 注意点:同意は自由意思に基づく必要があり、強制や威圧があれば違法。同意の範囲を超えた捜索は違法となる。
判例の傾向と実務上の注意点⚖️
- 最高裁判例では、令状なしの捜索は「例外的かつ厳格な要件のもとでのみ許容される」としており、捜査機関の裁量には厳しい制限が課されています。
- 実務では、令状なしの捜索が適法とされるかどうかは、緊急性・必要性・相当性などを総合的に判断されます。
◆ 本人不在でも捜索できるの?
はい、被疑者本人が不在でも、家宅捜索は法的に可能です。
ただし、実際に本人が不在の状態で強行的に捜索が行われるケースはまれであり、現場では次のような対応が取られることが一般的です。
-
警察から本人に連絡が入り、帰宅を促される
-
本人の帰宅を待ってから、本人立ち会いのもとで捜索を実施する
それでも、どうしても本人が不在の場合には、
-
同居している家族や管理人などを立会人として捜索を実施
-
押収品の内容を記載した「差押調書」をその場に残す
といった方法で、手続きを進めることができます。
家宅捜索中にしてはいけないこと・やるべきこと
突然の家宅捜索。警察官が自宅に上がり込み、部屋を見て回り、物を手に取る…。そんな光景に驚き、慌ててしまう方も多いでしょう。しかし、間違った行動をとると「証拠隠滅」などと判断されてしまうおそれもあるため、注意が必要です。
ここでは、家宅捜索中に絶対にやってはいけないことと、自分や家族を守るためにできることをまとめて解説します。
◆ 片付け・隠す行為は絶対NG
警察官が玄関に現れたとき、つい「ヤバい物は隠さなきゃ」「部屋を片付けたい」と思ってしまうかもしれません。
しかしこれは絶対にやってはいけない行為です。
-
物を隠す・移動する:→ 証拠隠滅とみなされる可能性あり
-
部屋を片付ける:→ 証拠の状況を変えてしまうおそれがある
📌 捜索開始前に「ちょっと片付けさせて」は通用しません。
令状があれば、警察は強制的に捜索を開始できます。どんなに恥ずかしい状態でも、そのままにしておきましょう。
◆ 捜索中にできる最低限の自己防衛

家宅捜索は警察による強制捜査ですが、こちら側にできる対応もいくつかあります。
✅ 録音・録画する(スマホやカメラでOK)
→ 警察の言動や捜索の様子を記録することで、後日のトラブル防止になります。
→ 無理に警察に向けて撮影するのではなく、自分の視点で室内の状況や押収品などを静かに記録しましょう。
✅ 押収品リストをもらい、内容をその場でメモ
→ 何が持って行かれたのか、あとで確認するのに役立ちます。
✅ 家族や第三者の立ち会いを求める
→ 家宅捜索の立ち会いは原則として本人または家族などが行います。可能であれば弁護士など信頼できる人に同席してもらうと安心です。
◆ 「何も出てこなかった」としても油断禁物
家宅捜索を受けても、何も押収されなかった場合、「よかった、もう大丈夫」と思う方もいるかもしれません。
しかし、それで捜査が終わったとは限りません。
-
証拠が見つからなくても、捜査は継続される可能性あり
-
後日、任意同行や取り調べが行われるケースも
-
「押収なし=嫌疑なし」ではない
さらに、家宅捜索が行われたという事実だけで、家族や職場、近隣との関係に影響が出ることも。その後の対応や心のケアも含め、弁護士に相談しておくことで、安心して過ごすことができます。
◆ 家宅捜索後に「名誉毀損で訴えたい」は通るのか?
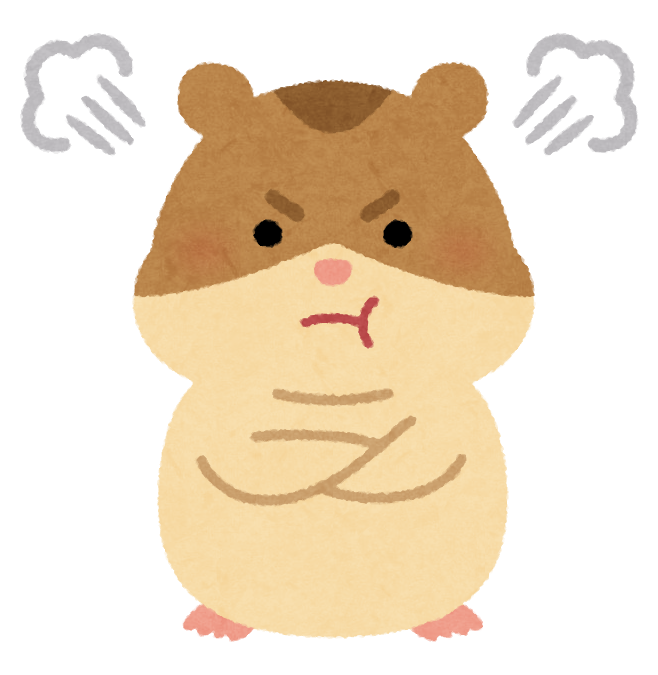
「何も悪いことをしていないのに捜索された。社会的信用が傷ついた。警察を名誉毀損で訴えたい!」
そんな気持ちになるのも無理はありませんが、家宅捜索自体が違法でなければ、名誉毀損で訴えることはほとんど困難です。
ただし、
-
捜索時に違法行為があった(例:令状の範囲を超えた押収、暴言など)
-
明らかに誤認逮捕・誤認捜査だった
というような場合には、国家賠償請求(国を相手に損害賠償を求める)が認められる余地があります。ですが、証拠が必要でハードルも高いため、まずは弁護士とよく相談することが先決です。
◆ 押収された物は返ってくる?返還請求の方法と注意点
押収されたスマホ・パソコン・通帳などは、捜査が終わるまで戻ってこないことがあります。
しかし、事件と無関係な物まで押収されていた場合は、弁護士を通じて返還請求や準抗告ができることがあります。
-
押収物のリストは必ず確認・保管
-
家族の私物など、無関係な物は返還を求められる
-
弁護士がいれば、適切なタイミングで返還交渉が可能
📌 押収品の扱いについて不安がある場合も、できるだけ早めに弁護士に相談するのが安心です。
家宅捜索の後はどうなる?警察の今後の動き
家宅捜索が終わったからといって、そこで一件落着…とはいかないのが現実です。
むしろ、家宅捜索は「これから捜査が本格化する」というサインでもあります。
では、その後に警察がどのような対応を取ってくるのか、そして、本人や家族はどのような備えをすべきかを具体的に見ていきましょう。
◆ 被疑者または参考人としての扱い
家宅捜索が行われたということは、何らかの事件について、あなたが「関係者」として警察に注目されている状態です。
-
令状に「被疑者宅」と明記されている場合は、すでに被疑者扱い
-
令状に名前がなくても、捜査上は参考人として呼び出されることがあります
📌 被疑者か参考人かによって、捜査機関の対応も変わってきます。
いずれにしても、黙って受け身でいるのではなく、自分の立場を正確に理解することが重要です。
◆ 今後の呼び出し(任意同行・取り調べ)への準備
家宅捜索の後、次に起こりやすいのが警察署への呼び出し(任意同行)や取り調べです。
呼び出しの方法には以下のパターンがあります:
-
警察から電話で「話を聞きたい」と言われる
-
捜索時に「後日、来てほしい」と口頭で依頼される
-
突然自宅を訪ねてこられる
この段階では、まだ逮捕されていないため「任意」とされますが、対応を誤ると逮捕につながる可能性もあるため慎重な対応が求められます。
📌 弁護士に相談しておけば、呼び出しにどう対応すべきか、何を話すべきか事前にアドバイスが受けられるため、非常に心強いです。
◆ 不起訴になるケースと、有罪になるケースの違い
家宅捜索のあと、起訴されるかどうかは、証拠の有無と質に大きく左右されます。
✅ 不起訴になる主なケース
-
証拠が見つからず、立証が困難
-
被害者との示談が成立している
-
犯行を否定しており、矛盾する証拠もない
-
初犯・軽微な事件で、社会的制裁が十分と判断された
⚠️ 一方で有罪になるケース
-
押収物がなくても証言や映像などで裏付けがある
-
他の証拠(通話履歴、SNSの記録など)で関与が明白
-
前科があるなど、処分が厳しくなる事情がある
つまり、「押収品がないから無罪」というわけではなく、総合的な証拠で判断されることを理解しておく必要があります。
◆ 証拠がなくても捜査は続く
捜査機関にとって、家宅捜索はあくまで証拠収集手段のひとつに過ぎません。
そのため、以下のような流れでその後も捜査が継続される可能性があります。
-
呼び出しによる任意の事情聴取
-
被害者や関係者への再聴取
-
電話・SNS・カメラ映像などの分析
-
他の関係先への追加捜索・押収
📌 家宅捜索後は、「今回は何もなかった」で済ませず、次のステップに備えて弁護士に相談し、取り調べ対応などの準備をしておくことが重要です。
◆ 弁護士と相談しておくべき具体的ポイント
弁護士に相談する際は、なるべく正確に状況を伝え、以下のような点についてアドバイスを受けておくと安心です。
-
捜索時に押収された物の内容と意味
-
現在の立場(被疑者・参考人)と今後の見通し
-
呼び出しを受けた場合の受け答えの仕方
-
家族や会社にどう説明すべきか
-
逮捕・勾留された場合の流れと必要な準備(着替えや連絡手段など)
📌 「まだ逮捕されていないから大丈夫」ではなく、今のうちに準備することで不測の事態に備えることができます。
弁護士が駆けつけると何が違う?
警察が自宅に押しかけ、突然始まる家宅捜索――。慣れない状況にパニックになってしまうのは当然です。
そんなとき、弁護士がその場に立ち会ってくれると、何が違うのか?
実は、家宅捜索の現場で弁護士が果たす役割は非常に大きく、後々の対応にも大きく関わります。
ここでは、弁護士が家宅捜索に立ち会うことで得られる6つの具体的メリットを紹介します。
◆ 弁護士ができること①:手続きの適法性チェック

家宅捜索は強制力を伴う手続きですが、あくまで法的ルールに基づいて行われるべきものです。
弁護士は現場で次のような点を確認し、不適切な手続きが行われていないかチェックします。
-
捜索差押許可状(令状)の記載内容の確認
-
捜索の対象となる場所・物の範囲が正確かどうか
-
押収物が令状に記載されたものと一致しているか
-
過剰な捜索や暴言・脅迫的な態度がないか
📌 違法な捜索があった場合、後に証拠の排除(違法収集証拠)を主張する根拠にもなります。
◆ 弁護士ができること②:押収品の記録と確認
家宅捜索では、スマホ・PC・書類・通帳など、さまざまな物が押収されることがあります。
弁護士が立ち会うことで、
-
押収品のリストを詳細にチェック
-
押収の様子を写真・メモ・録音などで記録
-
家族の私物など、無関係な物が押収されていないか確認
といった対応が可能です。
特に事件に無関係な物が押収された場合、その返還を求めるための証拠として重要です。
◆ 弁護士ができること③:返還請求や準抗告
不当に押収された物がある場合、弁護士を通じて返還請求を行ったり、準抗告(裁判所に異議を申し立てる手続き)をすることが可能です。
たとえば:
-
家族のパソコンやスマホが押収された
-
仕事で使う資料や端末が持ち去られた
-
事件とまったく関係ない物まで押収されている
このような場合、弁護士が速やかに行動することで、押収期間の短縮や損害の軽減につながります。
◆ 弁護士ができること④:今後の捜査・取り調べへの備え
家宅捜索が行われたということは、すでに刑事事件の重要な局面に入っているということです。
弁護士はその後の流れを見越し、以下のような準備をしてくれます。
-
警察からの呼び出し(任意同行・取り調べ)への対応アドバイス
-
供述の注意点や想定される質問へのシミュレーション
-
不利な供述を避けるためのアドバイス
📌 早期に弁護士が関与することで、不用意な発言による不利益を避けることができます。
◆ 弁護士ができること⑤:家族・仕事へのフォロー
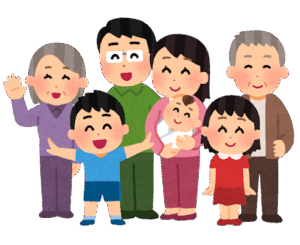
突然の捜索に家族が巻き込まれ、精神的に不安定になることも少なくありません。
また、仕事への影響も大きな問題です。
弁護士は、
-
家族への説明・精神的サポート
-
会社への報告方法のアドバイス
-
逮捕に至った場合の家庭・仕事への対応準備
など、生活面・精神面でのフォローも行ってくれます。
◆ 弁護士ができること⑥:早期の証拠保全や有利な事情の収集
弁護士が早い段階から関与すれば、こちらに有利な証拠や事情を収集・整理することが可能になります。
たとえば:
-
「その行為には正当な理由があった」ことを証明する資料
-
関係者からの有利な証言
-
過去のやりとり(メール・LINE・書面など)の整理
これらの情報は、不起訴や軽い処分につながる材料となり得ます。
📌 弁護活動は「逮捕後」ではなく、家宅捜索の時点から始まっていると考えるべきです。
◆ 弁護士に連絡が間に合わなかったときは?
家宅捜索は予告なく行われるため、弁護士が現場に間に合わないケースも多くあります。
その場合は、
-
捜索の様子をできる限り録音・撮影しておく
-
押収品のリストを写真に残す
-
捜索に立ち会った家族が、警察の名前・所属・時間帯などを記録する
これらの記録をもとに、後から弁護士と相談して適切な対応が可能です。
落ち着いて行動し、まずは弁護士に相談を

薬物・盗撮・ネットトラブル・誤認逮捕など、日常の中に潜むトラブルがきっかけで、ある日突然家宅捜索を受ける可能性は誰にでもあります。
そんなときにパニックにならずに済むよう、正しい知識と事前の準備が大切です。
そして、最も頼りになるのが弁護士の存在です。
◆ 弁護士に相談するメリットまとめ(一覧表)
| 項目 | 弁護士に依頼するメリット |
|---|---|
| 手続きの適法性確認 | 捜索や押収が法的に正しいかチェックしてくれる |
| 押収品の確認 | 家族の物など不当な押収がないか確認・記録 |
| 返還請求対応 | 不当な押収品の返還を求める手続きが可能 |
| 取り調べ対応 | 任意同行や事情聴取への対策を一緒に準備 |
| 家族・職場のフォロー | 周囲への説明や精神的サポートもしてくれる |
| 不起訴に向けた弁護活動 | 有利な証拠収集など、早期に対応できる |
◆ 弁護士が間に合わないときの対応メモ
家宅捜索は突然始まるため、弁護士が現場に間に合わないこともよくあります。
そんなときは、以下の対応を自分たちで行っておきましょう。
-
令状をスマホで撮影(全体が写るように)
-
押収品の内容をメモ・撮影(リストの写真も忘れずに)
-
捜索中の警察の対応を録音・記録(声だけでもOK)
-
警察官の所属・名前・時間をメモ
-
家族がいれば一緒に記録を手分けして対応
📌 後から弁護士に見せることで、違法な手続きがあったかどうかの判断材料になります。
◆ 相談時に伝えるべきことチェックリスト
弁護士に相談するときは、以下の情報を整理して伝えるとスムーズです。
-
捜索の日時・場所
-
警察官の所属や名前
-
押収された物の種類と数
-
令状に記載されていた内容(対象物、対象者など)
-
警察からのその後の連絡(呼び出し予定など)
-
今後の不安や希望(取り調べへの備え、返還希望など)
可能であれば、LINEやメールで写真・動画を共有しておくとベストです。
◆ 相談先の選び方と連絡のコツ
「どの弁護士に相談すればいいの?」と迷う方も多いでしょう。
以下のポイントを参考にしてください。
✅ 刑事事件に強い弁護士かどうか(ホームページなどで確認)
✅ 初回相談にすぐ対応してくれるか
✅ LINEや電話ですぐにやり取りできる体制があるか
また、連絡時には…
-
「家宅捜索を受けた」と最初に明確に伝える
-
可能なら「何の容疑か」「押収された物」も伝える
-
初動が重要なので、早朝・夜間でも対応可能な弁護士を選ぶと安心
◆ 家宅捜索は「その場限り」では終わらない
家宅捜索は、単なるスタート地点に過ぎません。
その後の取り調べ・起訴・裁判・処分にどうつながるかは、初動でどれだけ適切な対応ができたかに大きく左右されます。
もし家宅捜索を受けたら、とにかく冷静に対応し、すぐに信頼できる弁護士へ連絡することが最優先です。
あなたや家族を守るために、早期の相談を心がけましょう。