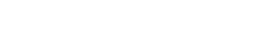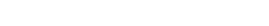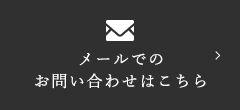2025/05/24 コラム
不同意性交等罪の構成要件とは?強制性交等罪との違いやよくある事例について徹底解説!

性犯罪に対する法的な見直しが進む中、2023年に新設された「不同意性交等罪」は、これまでの強制性交等罪に代わる重要な罪名として注目を集めています。被害者が声を上げにくい実態や立証の困難さを背景に導入されたこの法律は、性行為における「同意」の意味を根本から見直すものです。
本記事では、不同意性交等罪の構成要件を中心に、旧法との違いや実際によくある事例、さらには弁護活動の在り方までを詳しく解説します。
不同意性交等罪とは?

不同意性交等罪は、2023年に施行された改正刑法により新設された性犯罪の一類型です。この罪は、従来の「強制性交等罪」に代わるものであり、性行為における相手の「同意」の有無に注目した法改正がなされた点で非常に画期的です。従来は「暴行・脅迫」を伴うか否かが立件の主な焦点となっていましたが、現代社会における性被害の実態を踏まえ、より柔軟で実態に即した判断基準が求められるようになった結果、不同意性交等罪が制定されました。
この新たな罪は、たとえ暴力や強い脅しが伴っていなかったとしても、被害者が「同意していない」状況で性交等が行われれば、犯罪が成立する可能性があるという点で、旧来の性犯罪規定よりも保護範囲が広がっています。これにより、被害者が精神的に抵抗できなかった場合や、その場で意思表示が困難だったケースにも対応できるようになったのです。
不同意性交等罪の構成要件を解説

不同意性交等罪が成立するには、いくつかの明確な法的条件を満たす必要があります。法律の条文では抽象的に書かれている部分も多く、実際の適用には被害者の状況や相手との関係性、そして当時の具体的なやりとりなどが精査されることになります。
「同意がなかった」という主張がなされても、それが刑法上の「不同意」として認定されるためには、その背景にある心理的・社会的な要因が重要視されます。裁判では、被害者がその状況下で本当に自由に意思決定できたのかどうかが問われるため、証拠の収集や証言の重みが極めて重要になります。以下に、その構成要件をより具体的に解説していきます。
不同意性交等罪の構成要件は3つに分類される
不同意性交等罪が成立するためには、以下の3つの要素が揃うことが必要です。
1つ目は、被害者が同意する意思を形成・表明・全うすることができない状態にあったこと。
2つ目は、そのような状態であることを相手が認識し、または少なくともその可能性を認識しながら性交等を行ったこと。
3つ目は、性交等が実際に行われたという事実です。
これらの構成要件は、これまでの性犯罪における「暴行または脅迫」といった明確な行動要件よりも、被害者の心理的・環境的な脆弱性を重視する設計となっており、より実態に即した法運用が可能になることを目指しています。言い換えれば、形式的な「合意」があったように見えても、それが真に自由意思に基づくものでなければ、処罰の対象になりうるということです。
同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態とは?
「同意しない意思を形成・表明・全うできない状態」とは、単に身体が拘束されているというような物理的制限にとどまりません。たとえば、極度の酩酊状態や薬物の影響で判断力が低下している場合、あるいは睡眠中や意識が混濁している場合も該当します。さらに、心理的・社会的な圧力によって「ノー」と言えない状態、たとえば上下関係や恋愛感情、経済的依存などの背景も「困難な状態」と評価されることがあります。
こうした判断は、被害者がその場で抵抗しなかった、あるいは後から明確に「嫌だった」と述べたかどうかだけではなく、当時の会話やメッセージ、相手との関係性、そして被害者の置かれていた状況全体から判断されます。そのため、見た目には円満な関係であったとしても、内在的に強い支配や恐怖があった場合、それが犯罪構成要件に該当する可能性があるのです。
不同意性交等罪の施行はいつから?
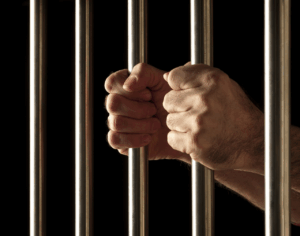
不同意性交等罪は、2023年7月13日に施行されました。この改正刑法は、長年にわたり性犯罪の被害実態と、既存法の限界について社会的な議論が続いてきた末に成立したものであり、性暴力被害者の保護を大幅に強化することを目的としています。
特に注目すべき点は、法施行と同時にこれまで立件が困難だった多くのケースで、再調査や再告発が行われるようになったという点です。社会的な啓発活動と連動して、被害者自身が被害を「声に出しやすくなった」という声も多く聞かれます。したがって、今後は不起訴になるケースが減り、実際に有罪判決が出る可能性も高まると予想されています。
不同意性交等罪の刑罰と罰則

不同意性交等罪が成立した場合の刑罰は非常に重く、原則として5年以上の有期拘禁刑が科されます。具体的な刑期は、行為の悪質性、継続性、相手との関係性などによって変動しますが、酌量減軽等が認められた場合でも<strong>2年6か月</strong>未満になることはなく、単発の行為であっても<strong>3年〜5年</strong>程度の実刑判決が下されるケースもあります。
また、被害者が未成年だった場合や、教師・上司など社会的に優越な立場を利用して行われた場合には、量刑が加重される可能性も高くなります。さらに、刑事処分だけでなく、社会的な信用失墜、職場での解雇、資格の喪失、教育機関からの退学処分といった民間レベルでの影響も甚大です。このように、不同意性交等罪は一度立件されれば人生を一変させる可能性を持つ重大な罪であるといえます。
不同意性交等罪と強制性交等罪の違い

不同意性交等罪は、従来の強制性交等罪とはいくつかの重要な点で異なります。最大の違いは、暴行や脅迫といった「物理的な強制力の行使」が構成要件から除外された点です。すなわち、相手が物理的に抵抗していなかったとしても、「本当は嫌だった」「言えなかった」「拒否する余地がなかった」といった心理的状況が重視されるようになったのです。
この改正により、実際に裁判で争われる争点も大きく変化しています。以前は暴行の有無が中心だったのに対し、今は被害者が置かれた環境や、同意の自由が本当にあったかどうかが重視されるため、証拠の収集や主張の立て方が根本的に変わってきています。
性交等の対象の拡大
改正前の強制性交等罪では、処罰対象は基本的に「性器の挿入」を伴う性交に限られていました。しかし、不同意性交等罪ではその対象が「性交等」に拡大され、性器以外の部位(口腔・肛門など)への侵入、または物を使用した性的行為も処罰の対象とされています。
これは、性被害の実態が性交の形態に限定されるものではなく、口腔や肛門を使った行為でも同等の身体的・心理的被害が生じるという認識に基づく改正です。したがって、行為の態様にかかわらず、同意がなければ処罰対象となるという点が、現代的な法制度の特徴です。
性交同意年齢の引き上げ
2023年の刑法改正により、性交の同意年齢が13歳から16歳へと引き上げられました。これにより、16歳未満の者との性交等は、たとえ本人の同意があったとしても処罰の対象となります。特に、成人との年齢差が大きい場合や、相手が未熟で判断力が乏しいとされるケースでは、より厳しく評価される可能性があります。
この改正は、未成年者を性的搾取から守るための措置であり、法的責任の有無にかかわらず、実際の年齢を確認せずに行為に及ぶことのリスクが非常に高くなっています。本人が年齢を偽っていたとしても、それは免罪の理由にはならず、加害者の「注意義務違反」として扱われる可能性があるのです。
構成要件の拡大
不同意性交等罪では、「同意のない性交等」がより広く処罰対象となるよう構成要件が拡大されました。従来の強制性交等罪では、暴行や脅迫など、相手が抵抗する余地を奪った明確な行動が必要とされていましたが、改正後は「同意を得ることが困難な状態」を利用した場合も含まれます。
これには、相手が酩酊していた、睡眠中であった、あるいは精神的に圧迫されていたなど、多様なケースが含まれ、物理的な暴力が伴わない場合でも処罰される可能性があります。加害者の意図や行動よりも、被害者の置かれた状況が重視される傾向にあり、慎重な対応が一層求められています。
公訴時効の延長
不同意性交等罪の施行に伴い、性犯罪全般に対する公訴時効の見直しが行われました。従来は性交等の罪について原則10年程度の時効が適用されていましたが、改正により、被害者が18歳未満である場合などは、一定の期間、時効が停止されたり延長されたりするようになっています。これにより、被害者が成長し、心理的に落ち着いた時点でようやく被害を訴えることが可能となり、従来は泣き寝入りせざるを得なかったケースにも光が当たるようになりました。
一方で、加害者にとっては過去の行為が何年も経ってから訴えられるリスクが生じ、事実関係や記憶の曖昧さが裁判上の争点となることも少なくありません。
不同意性交等罪の3つの問題点

不同意性交等罪は、被害者保護を強化する重要な改正ですが、一方でいくつかの懸念点も指摘されています。
特に「構成要件が曖昧でわかりにくい」「同意の証明が極めて難しい」「冤罪が発生しやすい」という3つの問題点は、被疑者の防御権とのバランスを考えるうえで非常に重要です。以下でそれぞれを詳しく解説します。
①構成要件が明確ではない
不同意性交等罪の特徴である「同意の困難な状態」という概念は、非常に幅広く、解釈に個人差が生じやすいものです。具体的なケースとして、酩酊や恐怖、精神的圧力などが挙げられますが、どこまでが「同意できない状態」と言えるのかは明文化されておらず、実際の判断は捜査機関や裁判所の裁量に委ねられる部分が大きいのが現実です。
これにより、事実関係が曖昧なまま立件される可能性や、行為の合意性に対して誤解やすれ違いがあった場合でも、犯罪とされるおそれがあるという課題が残っています。
②同意があったことの証明がしづらい
性行為が合意のもとに行われたかどうかを立証することは非常に困難です。口頭での同意があったとしても、それを記録に残していなければ証拠にはならず、客観的な裏付けを取ることがほぼ不可能な場合も多いです。相手が後から「同意していなかった」と主張すれば、被疑者側はそれに対抗する明確な証拠を出す必要があります。
たとえLINEやSNSのメッセージで和やかなやり取りがあったとしても、法的には「明示的な同意の証拠」としては不十分とされることもあり、合意を示す具体的な証拠のハードルは非常に高いといえます。
③冤罪を生み出すリスクがある
不同意性交等罪の構成要件の広がりは、正当な立件を可能にする反面、冤罪のリスクも増加させています。特に恋愛関係や知人間でのトラブルがこじれた際に、感情的なもつれから虚偽の被害申告がなされるケースも存在します。証拠が少ない中で供述だけをもとに逮捕・起訴が進めば、結果的に無実の人が有罪とされてしまう恐れもあるのです。
加えて、捜査機関による誘導的な取り調べや、弁護人がつかないまま自白を迫られる状況も、冤罪の温床となり得ます。こうした背景から、早期の弁護士相談と、適切な法的防御が不可欠です。
不同意性交等罪のよくある事例

不同意性交等罪は、思いもよらないタイミングで誰にでも起こりうる「身近な出来事」から発展することが多くあります。これらの事例は、特別な状況ではなく、普段の人間関係や性行動の中で頻繁に見られるようなシチュエーションです。
そのため、無自覚のうちに罪に問われるリスクを避けるためにも、日常的なリスクを理解しておくことが極めて重要です。意識的にリスクを把握し、行動することが、予期せぬトラブルを避けるための大切なポイントとなります。
後になって不同意だと言われた
行為が行われた当初には、特に問題がなかった場合でも、時間が経過してから「実は嫌だった」「無理やりだった」と言われるケースがあります。特に、恋愛関係が終わったり、別れ話が持ち上がったりした際に、過去の行為が突然掘り返され、不同意性交等罪として訴えられる可能性が高まります。
このようなケースでは、当人同士の認識のずれや、感情的な変化が大きな要因として作用します。自分自身が当時「同意があった」と確信していても、相手が「実際は同意していなかった」と主張した場合、警察に通報されることになり、捜査が行われるリスクが伴います。こうしたリスクが現実的に起こりうることをしっかりと認識し、自己防衛策を考えておくことが、最終的に自分を守る手段となります。
後から16歳未満だったと知った
出会い系アプリやSNSを通じて知り合った相手と関係を持ち、その後に相手が16歳未満であったことが判明した場合、その行為が同意を基にしたものであったとしても、処罰の対象となります。相手が実際には大人に見えたり、18歳だと嘘をついていたとしても、法律上はその言い訳は通用しません。
年齢確認を怠ることは非常に危険で、特に未成年との関係においては極めて高いリスクを伴います。未成年者が関わっている可能性が少しでもある場合、その行為が法的に問題となることを避けるためにも、必ず年齢確認を徹底する必要があります。
特に、相手が学生である場合など、さらに慎重に行動することが求められます。年齢確認をしっかり行わないことで、法的責任を問われる結果となり、長期的に影響が出る可能性もあるため、十分な注意が必要です。
風俗店で本番行為をし警察沙汰になった
風俗店では、法律により本番行為(性交)は禁止されています。しかし、たとえ相手の女性が同意しているように見えても、実際には店舗の規則や女性自身の意思に反していた場合、後になって「無理やりされた」と警察に通報されることがあります。
この場合、店側が「そのような行為は許可していない」と証言することによって、利用者が一方的に責任を問われることがあります。さらに、現場での軽はずみな判断が思わぬトラブルを引き起こすことが多く、風俗店を利用する際には法的なリスクを十分に理解し、自制心を持って行動することが極めて重要です。
店内での行動が後に問題となり、社会的な信用や個人の人生に大きな影響を及ぼす可能性もあります。そのため、事前に風俗店のルールや法的リスクを十分に認識し、慎重に行動することが必要です。
不同意性交等罪の弁護活動

不同意性交等罪で逮捕され、捜査の対象となった場合、迅速かつ適切な弁護活動が非常に重要です。この種の事件では、捜査段階と公判段階で弁護士が行うべき対応が異なりますが、いずれの段階でも事実を正確に伝える準備と、証拠の収集が不可欠となります。
弁護活動の進行においては、依頼者の権利を守り、最善の結果を得るための戦略的な対応が求められます。以下では、捜査段階および公判段階それぞれにおける弁護活動の特徴と重要性を詳しく紹介します。
捜査段階(起訴前)
起訴前の捜査段階では、取り調べへの対応準備が特に重要となります。この段階では、弁護士が依頼者に対し、不利な供述を避けるための助言を行い、黙秘権を行使するかどうかを検討するよう促します。事実関係を整理し、依頼者が不当な圧力や誤解から不利な状況に陥ることを防ぎます。さらに、捜査機関に対して事実に基づいた証拠を適切に提出することが求められます。
特に、被害者との示談交渉やアリバイ証明を行い、証拠を収集することが重要です。この段階で示談が成立すれば、検察による起訴を回避する可能性が高まり、依頼者の社会的な影響も最小限に抑えることができます。場合によっては、証拠が十分でないことが証明されることで、捜査が終了し、不起訴処分となることもあります。
公判段階(起訴後)
起訴後の公判段階では、裁判で無罪を主張することや、もし無罪が認められない場合には量刑の軽減を目指した弁護活動が本格的に開始されます。この段階では、弁護士が検察側の証拠を詳細に分析し、その証拠が依頼者に対してどれほど有利または不利であるかを見極める作業が行われます。
また、証人尋問や反証資料を提出することによって、依頼者が無実であることや情状の軽減を主張します。さらに、同意があったことを示す証拠として、LINEのやり取りや会話記録、第三者の証言などを活用し、依頼者に有利な証拠を裁判所に提出していきます。この段階では、裁判での発言や態度も非常に重要となります。
弁護士は、依頼者と密に連携を取り、事前に綿密な準備を行うことが求められます。弁護士と依頼者の協力により、裁判での有利な展開を導き出すための戦略を立て、依頼者を最善の結果に導くことが目標となります。
不同意性交等罪の心配がある方は須賀法律事務所へ

不同意性交等罪は、同意のない性交等を幅広く処罰対象とする新しい法制度です。被害者保護を目的とした制度である一方、構成要件の曖昧さや立証の難しさにより、加害者とされる側にも大きなリスクがあります。特に、無自覚のうちに犯罪と判断されるケースも多いため、慎重な行動と、何かあった際の早期相談が大切です。
不同意性交等罪への不安を感じたら、信頼できる情報源や弁護士に早めに相談しましょう。『須賀法律事務所』では、あらゆる刑事事件に関する情報をわかりやすくまとめてご紹介しています。
気になる方はぜひ公式サイトをご覧ください。
当事務所では、初回相談無料で法律相談を受け付けております。
お気軽にお電話またはLINEにてお問い合わせください。