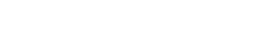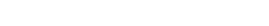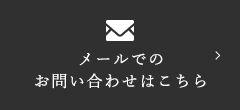2025/05/25 コラム
統合失調症なら罪を犯しても無罪?責任能力が争点になる裁判の仕組みと精神鑑定の重要性

「統合失調症だったから無罪に――」こんなニュースを目にして、驚いた方も多いのではないでしょうか。「精神疾患があれば罪に問われないの?」「それって本当に公平なの?」といった疑問や不安の声は、SNSでもたびたび話題になります。
実際、精神疾患を持つ人が重大な犯罪を起こした際、「責任能力がなかった」とされて無罪や不起訴になるケースは存在します。しかしこれは、「病気なら何をしても許される」という話ではありません。
この記事では、「統合失調症と無罪の関係」について、法律上の仕組みや裁判の流れ、精神鑑定の役割などをわかりやすく解説します。誤解されがちなこのテーマを、法律の視点から正しく理解していきましょう。
|
【目次】
|
【統合失調症で「無罪」になるのはどんなとき?】
【精神鑑定とは何をするのか?裁判での役割は?】
統合失調症などの精神疾患がある被疑者・被告人に対して、「責任能力があったのかどうか」を判断するために、重要な役割を果たすのが精神鑑定です。ニュースなどでも「精神鑑定の結果、心神喪失と認められ…」というフレーズがよく出てきますが、精神鑑定とは具体的にどんな手続きで、どう活用されているのでしょうか?
精神鑑定とは?
精神鑑定とは、刑事事件において「その人物が犯罪を犯した時点で責任能力を有していたかどうか」を専門家(主に精神科医)が評価するプロセスです。医師による診察・観察・心理検査・過去の病歴調査などを通じて、被疑者や被告人の精神状態の医学的な所見を報告書としてまとめ、裁判所に提出します。
鑑定を行うのは、主に精神科の専門医や法医学の知識をもった医師です。医師は中立の立場で、警察や弁護士、裁判所などの依頼を受けて鑑定を実施します。よって、鑑定医は加害者側の味方でも、被害者側の味方でもありません。
鑑定はどのタイミングで行われるのか?
精神鑑定は主に2つのタイミングで行われます。
- 捜査段階(起訴前)
簡易鑑(予備鑑定)
被疑者が逮捕された段階で、「精神的に異常があるのではないか」と警察や検察が判断した場合、まず行われることがあるのが簡易鑑定(予備鑑定)です。これは精神科医による1回~数回程度の面接や診察で、責任能力の有無についておおまかな見立てを得るためのものです。正式な鑑定ではありませんが、「本格的な精神鑑定が必要かどうか」「責任能力に重大な疑いがあるか」といった判断材料になります。
正式鑑定(本鑑定)
この簡易鑑定の結果、さらに詳しい検査が必要と判断された場合には、鑑定留置(かんていりゅうち)という手続きがとられます。これは、裁判所の決定により被疑者を一定期間(通常は1〜2か月)、専門病院などに入院させ、医師が継続的に観察・診察を行う正式な精神鑑定です。期間中には心理検査や病歴調査、行動観察などが行われ、責任能力の有無について医学的な評価がまとめられます。
- 公判段階(起訴後)
この段階では、被告人の弁護人(弁護士)が責任能力に疑問があるとして鑑定を請求することが多く、裁判所はその必要性を判断した上で鑑定を認めるかどうかを決定します。
鑑定が認められると、起訴前と同様に鑑定留置(一定期間病院などに入院して行う鑑定)や、外来通院による鑑定が実施されます。これらの手続きを通じて、精神科医が「犯行当時に責任能力があったかどうか」について詳細な鑑定書を作成し、裁判所に提出します。
この鑑定結果は、無罪か有罪か、あるいは減軽が認められるかといった判断に大きく影響する重要な証拠となります。
精神鑑定の内容とは?
鑑定には、次のような検査や調査が含まれます。
-
面接や行動観察
-
知能検査や心理テスト(ロールシャッハテストなど)
-
過去の精神科治療歴の確認
-
犯行動機や状況の分析
-
薬物やアルコールの影響の有無
-
日常生活での言動・対人関係の評価 など
このようにして作成された鑑定書には、「心神喪失」または「心神耗弱」の可能性が医学的にどう見られるかが詳細に記載され、裁判所に提出されます。
鑑定結果は絶対?裁判所はどう判断する?
ここで注意したいのは、精神鑑定の結果がそのまま無罪につながるわけではないということです。精神鑑定はあくまで一つの証拠です。最終的に有罪か無罪かを決めるのは裁判所(裁判官または裁判員)であり、鑑定結果に加えて、供述や証拠、現場の状況などを総合的に判断します。
たとえば、鑑定書では「心神喪失の可能性が高い」と記されていても、計画的な行動が見られた場合や、周囲の証言によって「判断能力があった」と推認できると判断されれば、有罪となることもあります。
また、逆に「心神耗弱」と認められた場合は、刑の減軽となるだけで、無罪にはなりません。つまり、精神鑑定の内容は裁判の行方を大きく左右する一要素ではあるが、絶対ではないという点が重要です。
精神鑑定は「逃げ道」ではない
一部では「精神鑑定を受ければ無罪になる」「弁護士がうまく持ち込んで減刑を狙う」といった見方もありますが、これは事実に反します。精神鑑定は医師による客観的評価に基づき、正当な手続きの中で行われるものであり、逃げ道や裏技ではありません。
統合失調症であっても、しっかりと薬を服用し、日常生活が問題なく送れている状態であれば、責任能力ありと判断され、有罪となるケースは数多く存在します。
【無罪=自由ではない?医療観察法による処遇とは】
精神障害が原因で無罪になった――。この一文だけを聞くと、「え?じゃあその人は釈放されて普通に生活に戻るの?」と驚かれる方も多いかもしれません。
しかし、責任能力がないと判断されて刑事罰を受けない場合でも、自由の身になるとは限りません。実際には、再犯防止や社会の安全確保の観点から、別の法制度が適用されます。それが「医療観察法(正式名:心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)」です。
医療観察法とは何か?
医療観察法は、2005年に施行された比較的新しい法律です。この法律の目的は、重大な犯罪を犯したものの、「心神喪失」などで無罪や不起訴となった人に対して、必要な医療を提供しつつ、再犯の恐れを減らすことにあります。
対象となるのは主に次の2パターンです。
-
裁判で「心神喪失」などの理由により無罪となった者
-
起訴されず不起訴処分となったが、精神鑑定で責任能力がないと判断された者
これらの人について、検察官が「再発の可能性がある」と判断した場合、家庭裁判所に医療観察手続きの申立てがなされます。そして、家庭裁判所が精神医療の専門家による鑑定などをもとに、今後の処遇(入院・通院のいずれか)を決定します。

「無罪でも入院」は普通にある
よくある誤解のひとつが、「無罪になったら即釈放される」というものです。実際には、無罪になったとしても、家庭裁判所の審判で入院が必要と判断されれば、医療機関に強制的に入院させられることになります。
この入院は刑罰ではありませんが、自由を大きく制限される点では刑務所に近い側面もあります。病状が安定しなければ、数年にわたって入院が継続されるケースも珍しくありません。しかもこの入院は「有期刑」ではないため、具体的な期限がありません。社会復帰が可能と判断されるまで、継続的な審査と医療支援が続きます。
通院処遇の場合でも自由ではない
医療観察法による処遇には、入院のほかに通院処遇もあります。通院と聞くと、自由に見えるかもしれませんが、これも実はかなり厳しい制限のある制度です。
通院処遇では、決められた医療機関に定期的に通院し、服薬状況や生活状況の報告を求められます。また、社会復帰調整官という専門職が付き添い、再発のおそれがないかを監督し続けます。無断で通院をやめたり、指導に従わなかったりすれば、再び審判が開かれ、入院処分に切り替えられることもあります。
つまり、医療観察法の通院は「自由な生活」ではなく、医療と監督がセットになった制度的支援下での生活なのです。
社会復帰と支援の仕組み
医療観察法の目的は、あくまで再犯防止と社会復帰の両立にあります。そのため、医療機関や福祉サービスが連携して、対象者が地域で生活を送れるようにサポートを行います。
たとえば、退院後にはグループホームへの入居、福祉就労支援、生活保護の手続きなど、医療以外のサポートも受けられます。これらの支援は、地域社会の安全と本人の自立の両立を目的としています。

被害者感情とのギャップも──「罰を受けていない」ことへの違和感
精神障害が原因で無罪や不起訴となった場合、医療観察法による処遇がなされるとはいえ、加害者が「刑務所に入らない」という事実は、被害者や遺族にとって強い違和感や怒りを生むことがあります。
特に、命を奪われた、重傷を負ったといった重大な被害に遭った遺族にとっては、「自分の大切な人が傷つけられたのに、加害者は病気を理由に“無罪”扱いで入院生活を送っている」という構図に納得がいかないというのが正直な感情です。「なぜ罰せられないのか」「謝罪も賠償もないまま自由に戻るのか」と感じる方も少なくありません。
しかし刑法は、「罰することが正当化されるのは、その人に責任能力がある場合だけ」という大原則に立っています。つまり、「善悪の判断もできず、自らの行動を制御できなかった人」に刑罰を与えるのは、人権の観点からも許されないとされているのです。
このような制度の理念は、一般社会では十分に知られておらず、結果として被害者感情との深いギャップが生まれてしまう現状があります。このギャップをどう埋めていくかは、今後の刑事司法と医療福祉の共通課題ともいえるでしょう。
【不起訴になるケースも多い?裁判にすらならない現状】
精神障害がある人による重大な犯罪が報道されると、「なぜ無罪になるのか」と世間の注目が集まりますが、実は統計的には無罪判決よりも、不起訴処分となるケースの方がはるかに多いのが現実です。
刑事事件では、警察が逮捕・送致した後、検察官が起訴するかどうかを判断しますが、被疑者の精神状態に疑問がある場合、起訴前の段階で精神鑑定が行われることがあります。この時点では、医師による簡易鑑定や、必要に応じて鑑定留置が実施され、「犯行当時に責任能力がなかった」と判断されると、そもそも起訴自体が見送られます。これは、刑法上「責任能力のない者には刑事責任を問えない」という原則があるためです。
このように、正式な裁判すら行われないまま、不起訴となる精神障害関連事件は相当数に上ります。一方で、無罪判決は公開の法廷で争われた結果として出されるため、ニュースなどで取り上げられやすく、目立つ傾向があります。そのため、「精神障害なら無罪になる」という印象が強まってしまう一因にもなっています。
また、不起訴処分になったからといって問題が解決するわけではありません。責任能力がないと判断された人が医療につながらず、家族が抱え込み、地域社会から孤立するといった問題が生じるケースも多くあります。医療観察法の対象にならない場合や、手続きがなされないまま本人が自宅に戻ってしまうこともあり、再発防止や周囲の不安に十分に対応できていない実態も指摘されています。
つまり、「不起訴=処分なし」「無罪=自由の身」ではなく、その後の支援体制こそが問われているのです。司法と医療、そして福祉が連携し、継続的なサポートが提供される仕組みづくりが今後ますます重要になります。
【まとめ:精神疾患による犯罪とどう向き合うべきか】
精神疾患が理由で無罪や不起訴となることは、決して「特別扱い」ではなく、法律に基づいた厳格な判断の結果です。責任能力がない人に刑罰を科さないという原則は、人権尊重の観点から重要である一方、被害者感情や社会の安全とも向き合わなければなりません。精神鑑定や医療観察法といった制度はそのバランスをとる仕組みですが、実際の運用には課題も残されています。私たち一人ひとりが正しい知識を持ち、偏見や誤解をなくしていくことが、より良い制度づくりと安心できる社会の第一歩となります。
当事務所では、初回相談無料で法律相談を受け付けております。
お気軽にお電話またはLINEにてお問い合わせください。